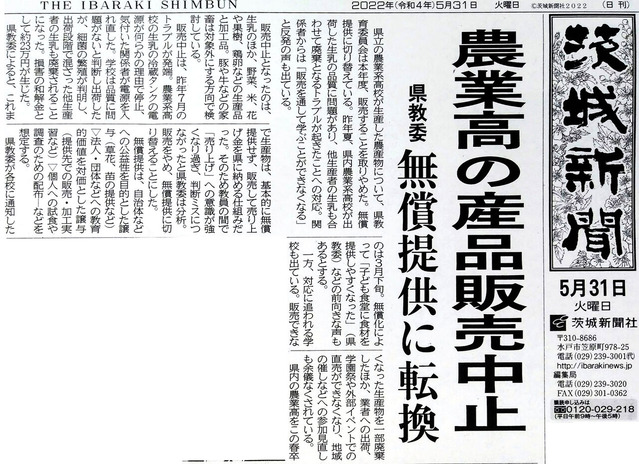最近、「CLT」という新たな建築資材が注目されています。CLTは「Cross Laminated Timber(クロス・ラミネイティド・ティンバー)」を略したもので、木の板を繊維の方向が交差するように重ねて接着し、厚くした集成木材のことです。
最近、「CLT」という新たな建築資材が注目されています。CLTは「Cross Laminated Timber(クロス・ラミネイティド・ティンバー)」を略したもので、木の板を繊維の方向が交差するように重ねて接着し、厚くした集成木材のことです。
1960年に86.7%だった日本の木材自給率は、2002年に18.2%まで下落しました。近年は公共建築物等木材利用促進法や木材利用ポイント制度などの後押しもあり、12年には27.9%まで回復しています。
日本は国土の約7割を森林が占めています。先進国中3位の森林大国なのです。にもかかわらず、国内林業は高度経済成長期をピークに衰退し、林業就業者も45年間で9分の1(約5万人)に減少しています。とはいえ、戦後、植樹された莫大な人工林は収穫期を迎えているのです。そこで、国産材の需要拡大に期待されているのが、欧州で開発されたCLTの実用化です。
国産木材のさらなる需要拡大策として中高層建築物の木造化が注目される中、強度があり、耐震性や断熱性、耐火性も高いとされるCLTは、コンクリートに代わる建築用材として期待が高まっているのです。
ヨーロッパではCLTの普及が急速に進んでいて、ロンドンには9階建ての建物もあります。低級材でもCLT工場に持ち込めば売れるようになったため、CLTが製材業の活性化を補完する役割を担っているといわれています。
日本では2013年12月にCLTの日本農林規格(JAS)が制定されたものの、建築基準法における構造材としてのCLTは認められていません。普及を促進するには、関連する法規制などの整備や、耐火性能の評価が欠かせないのです。
現在、CLTの実用化に取り組んでいる銘建工業株式会社などが出資する「高知おおとよ製材」(高知県大豊町)は、国土交通相の認定を受け、構造材にCLTを活用した社員寮(3階建て)を建築しました。
林野庁でも、16年度を目標に法令の整備に取り組み、20年の東京五輪の施設にCLTを活用したい考えです。日本の木材をアピールするために、選手村などにCLTを活用してはという意見もあります。
CLTの活用について公明党は、2013年7月に山口那津男代表が石田祝稔衆院議員らと共に高知おおとよ製材を訪れ、関係者から要望を受けたほか、13年8月には党農林水産部会が14年度予算の概算要求に向け、林芳正農水相にCLTの技術開発の促進を求めるなど、一貫して推進してきました。農水省(林野庁)は14年度予算案にCLTなどの技術開発のため、約5億円を盛り込みました。また、国交省も耐震強度などの基準づくりのための予算3億円を計上しています。
 参考:日本CLT協会のHP
参考:日本CLT協会のHP