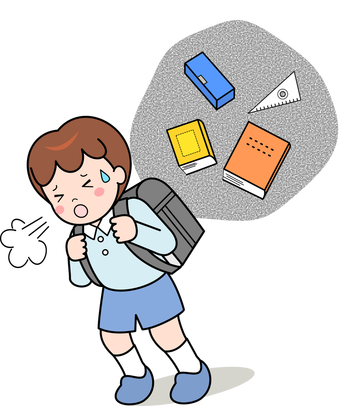 9月6日、文部科学省は「通学用の荷物が重すぎる」との声が児童・生徒、保護者から上かっていることを受け、全国の教育委員会などに対し、一部の教材を教室に置いて帰る、いわゆる「置き勉」を認めるなどの対策を検討するよう通知しました。子どもの荷物はどれだけ重いのか、その実態と理由を公明新聞(9月20日付け)の記事よりまとめてみました。
9月6日、文部科学省は「通学用の荷物が重すぎる」との声が児童・生徒、保護者から上かっていることを受け、全国の教育委員会などに対し、一部の教材を教室に置いて帰る、いわゆる「置き勉」を認めるなどの対策を検討するよう通知しました。子どもの荷物はどれだけ重いのか、その実態と理由を公明新聞(9月20日付け)の記事よりまとめてみました。
「ドスンッ!」という音とともに、通学用のリュックが床に置かれました。持ち主はわが家の中学1年の長女。中身を見せてもらうと、教科書4冊を筆頭に、ノートと問題集がそれぞれ4冊、各教科の資料などプリント類が入ったクリアファイルと筆記用具、水筒-など、その重さは8Kgを超します。これに部活用具を入れた補助バッグや体育着などが加わり、雨の日に傘も差すとなると、片道10分ほどの登下校であっても一苦労です。
都内の私立中学校に通う女子生徒の母親は、「重い荷物で腰への負担が気になる。常に前傾で歩いている感じで、姿勢も悪い」と話します。置き勉は禁止だという公立中学校の男子生徒の母親も、「帰宅後は全教科の予習・復習をするわけではないので、学校側も何を持ち帰るかは本人に任せてほしい」と訴えていました。
一方、小学生のいる母親にも聞くと、上履きや給食袋、体育着などを持って帰る金曜日と、それらを持って行く月曜日は特に荷物が多くなり、「両手がふさがって危ない」と心配との意見が出ます。教科書協会が2017年に行った調査によると、小中学校の主要教科の平均的なページ数は、2002年に小学校は3090ページ、中学校は2711ページだったのに対し。「脱ゆとり教育」後は小学校が4896ページ(2015年)、中学校は4182ページ(2016年)と、それぞれ1.5倍程度増えていることが分かりました。
教科書研究センター特別研究員の細野二郎さんは現在の教科書について、学習指導要領の内容が増えたことに加え、理解を深めるための図表なども増加しており、15年ほど前の教科書に比べ大判化していると説明。子どもたちの通学荷物が重いことに関しても、「副教材などが増えたこともあるが、学習の中心である教科書自体が重くなっているのは間違いない」と指摘します。
背骨や関節変形の恐れも
重い荷物を背負っての通学がもたらす健康への影響について、柔道整復師の陣川英幸さんは「まず、背骨がゆがむ側湾症が考えられる。さらに、日常的に体へ過度な負担がかかることで神経を圧迫し、ヘルニアの症状が出る可能性もある」と警鐘を鳴らします。
また陣川さんは、膝や腰、股関節など下半身への影響も懸念します。体重60kgの人の場合、立っているだけで腰には36kgの負荷がかかるとのデータを示し、子どもは関節が未発達なため、下半身の関節が変形する恐れもあると語っています。
一方、保護者に対しては「日頃から子どもの姿勢に注意を払つてほしい」と述べ、「左右の肩の高さが違うなど、気になることがあれば早めに医療機関や接骨院に足を運んでもらいたい。骨格が成長途中である分、早く治療を始めれば治るのも早い」と話しています。
見直しへの動きを歓迎
大正大学人間学部・白土健教授
昨年11月、都内の小学1~3年生の使っているランドセルについて、重さを測定しまし。結果は最高が9.7kg、平均は7.7kgで、体重が20kgにも満たない低学年の子どもの通学が“苦行”のようになっている実態が分かりました。
諸外国の事情も調べましたが、欧米諸国や韓国、オーストラリアなどでは鍵付きのロッカーが完備され、教材は置いて帰るケースが多くなっています。登下校もスクールバスや保護者がサポートするので、10分、20分と荷物を背負って歩くこともありません。まさに“重い荷物”は日本独自の文化だといえます。
置き勉を認めるか否かは学校の裁量だが、認めない主な理由としては、①家庭学習の習慣が身に付かない②教室の美観③盗難・紛失-などがあるようです。だが、体重の20~30%もある荷物を長時間持つと健康に悪影響があるとの調査もあります。今回、公明党の訴えを受けて、文科省が学校の対応を見直すよう通知したことは歓迎したいと思います。



