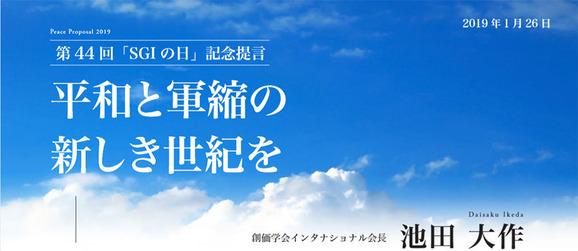令和の時代を迎え、初の国政選挙・参議院議員選挙が間近に迫っています。
公明党にとっては党の命運をかけた戦い。12年前の「亥年の選挙」で党は統一地方選で完勝しましたが、参院選では3選挙区で惜敗。その意味で今度の参院選は雪辱戦となります。埼玉、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫、福岡の7選挙区に擁立する7人の全員当選と比例区で6以上を何が何でも勝ち取ってまいりたいと思います。
この目標を達成できらば、参院公明党は非改選の14議席と合わせて27議席以上となり、現行の選挙制度となって過去最多の議席数となります。結党55年の節目を飾り揺るぎない党の基盤を築くためにも勝利へ全力をあげる必要があります。
この参院選の政策課題は何か?
日本が抱える最大の課題は、人口減少、少子高齢化の克服です。そのためには、子育てから高齢者福祉まで支援する全世代型社会保障の強化が不可欠。引き続き自民、公明両党による安定した連立政権で政策を遂行していくことが重要です。自民党ともしっかり協力し連立与党の勝利をめざします。
その上で、令和の新時代にあって、公明党の存在意義を再確認したい課題を3つ整理しておきたいと思います。
その3つとは、①国連の持続可能な開発目標SDGsの推進、②核兵器禁止条約批准、AI兵器規制実現、③防災減災対策の推進です。
発と使用を含めて全面禁止する条約の制定を、早急に目指すべきではないでしょうか。
与党の勝利、そして公明党の存在意義を示すことによって、自民党をもリードして、対立が激化する国際社会の中で、日本をマグネットの役割を果たせる国に変えていかな場なりません。公明党は平和の党であり、アメリカともヨーロッパとも、中東の国々とも、そして中国や韓国とも、広く協調できる政党です。その存在意義を大いに示していきたいと決意します。
このブログでは、②の核兵器禁止条約、AI兵器規制についてまとめておきたいと思います。(なお、参考のために池田大作SGI会長の「SGIの日記念提言」の一部を掲載します)
■核廃絶、AI兵器規制を/山口代表らが強調
5月2日公明党の山口那津男代表は、災害からの被害を軽減することも、人権を保障する政治の責務と強調。防災・減災や復興の取り組みについて、「社会の主流、政治の柱にしなければいけない。日本は国際社会の中でも防災・減災を担うリーダーとなっていくべきだ」と力説しました。
また、「人権を著しく損なう戦争や核兵器の使用は絶対にやめさせなければならない」と主張。核保有国と非保有国の有識者らで構成する賢人会議が取りまとめた核軍縮への進め方に関する提言について、2020年の核拡散防止条約(NPT)運用検討会議に反映させるべきだとの考えを示し、「核保有国と非保有国を橋渡しし、合意点を見いだす責務を日本が担っている。核軍縮を一歩でも進めることが重要だ」と述べました。
さらに、人工知能(AI)が標的を判断して殺傷する「自律型致死兵器システム(LAWS)」の開発規制について、公明党がいち早く政府に提言したことにも触れ、「人権を損なう大きな脅威から守る政策をわれわれは実行して、人権を保障していかなければならない」と訴えました。
一昨年7月に国連総会で採択された核兵器禁止条約は「核兵器は違法」との規範を初めて打ち立てました。公明党はこれを高く評価します。同時に、現実政治の中で核廃絶を実現するため、核兵器禁止条約を巡って対立する核保有国と非保有国の「橋渡し役」を日本政府が担うよう求めています。そのために、外務省が主催し、核保有国、非保有国双方の有識者からなる賢人会議が、核拡散防止条約(NPT)の中で核軍縮を進めるよう求めていることを重視し、支援していく決意です。
殺人ロボットとも呼ばれ、世界で開発競争が進む人工知能(AI)搭載の自律型致死兵器システム(LAWS)の規制も重要なテーマになっています。非人道的兵器に反対する公明党は、他党に先駆けて政府に申し入れを行い、特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)の中で規制のための合意をまとめるよう求めています。
人工知能(AI)を搭載し、人間の意思を介さず標的を定め殺傷する「自律型致死兵器システム(LAWS)」に関する国連公式専門家会議が、3月下旬にスイスで開催されました。会議で日本政府は、公明党の提言などを踏まえ、LAWSについて「開発する意図はない」との立場を表明するとともに、全ての兵器は「人間による関与が必須である」と訴え、国際的な開発規制の必要性を提唱しました。
LAWSは、安全保障や戦争のあり方を大きく変える可能性があると言われ、倫理的な問題や制御不能になるリスクなどが懸念されています。現在、非人道的な兵器を規制する特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)の枠組みで議論されていますが、利害が絡み、各国で考え方には隔たりがあるのが現状です。
3月下旬の会議は、CCWの枠組みの下、条約締約国などが規制すべきLAWSの特徴、人間の関与のあり方などを議論。日本政府は、高見沢将林軍縮大使らが出席し、「AIなどの技術の平和利用を妨げてはならない」とした上で、全ての兵器には人間の関与が必須であり、武器の非人道的使用を禁じた国際人道法の順守を訴えました。また、議論の内容を成果文書にまとめることも要請した。次回会合は8月下旬に開かれます。
■河野外相「公明党の提言も参考に」
公明党は、LAWSについて、「国際人道法や倫理上の観点から到底看過できない」として、今年2月の参院代表質問で山口那津男代表が国際的な開発規制の必要性を主張しました。さらに、いち早く党プロジェクトチームを立ち上げ、政府に対し「全ての兵器に有意な人間の関与が必要」などとする提言を河野太郎外相に申し入れました。
河野外相は、今回の会議で表明した政府の見解について、3月25日の参院予算委員会における公明党の平木大作氏の質問に対し、「公明党の提言などを参考にして、日本の考え方をまとめた」と答えています。
公明党は引き続き、LAWSの開発規制に関する国際世論を日本がリードするよう求めてまいります。
池田大作SGI会長の記念提言2019
(2019/1/26)
第三の提案は、AI兵器やロボット兵器と呼ばれる「自律型致死兵器システム(LAWS)」を全面禁止する条約の制定です。LAWSはいくつかの国で開発されている段階で、実戦配備には至っていません。
しかし、戦闘行為を自動化する兵器を導入する国がひとたび現れれば、核兵器の誕生にも匹敵するような世界の安全保障環境を一変させる事態になりかねないとの懸念が、国際社会の間で広がっています。
人間が戦闘に直接介さないことで軍事行動への垣根が格段に低くなり、国際人道法の精神が著しく損なわれる恐れもあるからです。
加えて、国連の「軍縮アジェンダ」の中で指摘さていた、LAWS特有の問題に目を向ける必要があります。
第2次世界大戦時に無人の攻撃機として使用された「V1ロケット」から、今も埋設されたままの地域が残る「対人地雷」まで、人間の操作を必要としない多くの兵器が開発され、使用されてきたものの、LAWSにはそれらの兵器とはまったく異なる危険性があるとして、次の問題が指摘されていたのです。
それは、AIに操作を依存するがゆえに、「予期しない行動や説明できない行動を起こす可能性」を常に抱えているという点です。
私も以前、平和学者のクレメンツ博士との対談で、LAWSの規制を巡る非公式の専門家会合が2014年に国連で初開催されたことを受け、LAWSの危険性について語り合ったことがあります。
その際、私は、良心の呵責も逵巡も生じることなく自動的に攻撃を続けるロボット兵器には、人道的観点からも極めて重大な問題があることを訴えました。
その上、惨事が引き起こされる前に、あらかじめ全面規制を図ることが急務であり、開発と配備を禁止する枠組みづくりを早急に進めるべきであると呼び掛けたのです。
クレメンツ博士も、NGOが進める「ストップ・キラーロボット」のキャンペーンに触れて、こう述べていました。
「こうした市民社会による運動や国連事務局、そして各国の外交関係者などの広範なアクター(行動主体)が積極的に連携を強めていくことが、この問題解決の大きなカギとなります」と。国連に提出したSGIの声明
昨年4月に行われた政府専門家会合では、「兵器の使用に人間の判断が介在すること」の必要性を大多数の国が認めたほか、26カ国がLAWSの全面禁止を求めました。
私は、国連の「軍縮アジェンダ」における警告と、政府専門家会合で示された各国の懸念を基盤に、「LAWS禁止条約」の交渉会議を早期に立ち上げることを強く求めたい。
日本も昨年2月に、人間が関与しない完全自律型の兵器の開発を行う意思はないとの方針を示しています。また欧州議会が、国際規制の枠組みづくりの交渉を早急に開始することを呼び掛ける決議を9月に採択しました。
市民社会の間でも、「ストップ・キラーロポット」の活動に参加するNGOが、51カ国の89団体にまで広がっています。
SGIも昨年10月、国連総会第1委員会に代表が出席した際、二つの声明を同委員会に提出しました。
一つは、キリスト教、イスラム教、ヒンズー教、仏教などの信仰を基盤にした14の団体と個人の連名で出した「宗教コミュニティーによる共同声明」で、核兵器禁止条約の重要性とともに、LAWSを禁止するための多国間の議論を呼ひ唯トけたものです。
そしてもう一つがSGIとしての独自の声明でLAWSが深刻な軍事的脅威をもたらすだけでなく、「生命の権利」と「人間の自律と責任と尊厳に関する原則」を著しく脅かす存在に他ならないことを警告したものです。
もし、LAWSが規制されないまま、実際に使用される事態が起きた時、紛争の性格は根源から変わってしまうに違いありません。
そこでは、すでにドローン兵器の場合にみられるような、攻撃をする側と攻撃される側の人間が同じ空間にいないという“物理的な断絶性”に加えて、実際の戦闘行為が攻撃を意図した人間と完全に切り離されるという“倫理的な断絶性”が生じるからです。ヴァイツゼッカ一大統領の戦争体験
軍事的脅威の深刻さもさることながら、この“倫理的な断絶性”が何を意味するのかを考える時、私の胸に浮かんでくるのは、統一ドイツのリヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカー初代大統領が自身の体験として紹介していた話です。
物理学者のヴアイツゼッカー博士の弟君でもある大統領とお会いしたのは、ドイツの統一から8カ月後(1991年6月)のことでした。
その際、戦時中に日本とドイツが経験した「閉じた社会」の危険性について語り合いましたが、大統領は回想録で次のような体験を紹介していました(『ヴァイツゼッカー回想録』永井満彦訳、岩波書店を引用・参照)。
一一大統領は、西ドイツの議員を務めていた時期(1973年)にソ連を初訪問し、レニングラード(現サンクトペテルブルク)にある墓地に足を運んだ。
そこは、第2次世界大戦中にドイツ軍による包囲戦で亡くなった大勢の人々が眠る場所だった。
その夜、会食会に出席した大統領は、あいさつに立った時、ソ連の人々の前で告白を始めた。
実は自分も、あの時の包囲戦に参加していたドイツ兵の一人であった、と。
思いもよらない言葉に、場内が沈黙に包まれる中、大統領は言葉を続けた。
「われわれはすべての前線、とりわけレニングラード市内における苦しみを充分承知していました。われわれ自身が体験したことを、子孫が決して繰り返してはなりません。われわれはそのために応分の責任を果たすべく、今ここにいるのです」。その率直な言葉に触れ、最初は沈黙していたソ連の人々も次第に心を開き、温かささえ感じる雰囲気に変わっていった一一と。
翻って今後、紛争地域でLAWSが実際に使用された場合に、かつての敵同士のこうした対面は果たして成立するでしょうか。
自身が関わった行為に対する“深い悔恨”と、戦争に対する“やりきれない思い”、そして、次の世代のために平和な関係を築き直したいと切実に願う“一人の人間としての決意”が入る余地は、そこにあるでしょうか。
私も、大統領がソ連を初訪問した翌年(74年9月)に、そのレニングラードの墓地を訪れて献花し、平和への誓いを込めた祈りを捧げたことがあります。
ソ連滞在の最終日にコスイギン首相とお会いし、墓地に献花したことを伝えた時、首相は当時の包囲戦の苦しみを思い返すかのように、「あの時、私もレニングラードにいました」との言葉を発したきり、しばし沈黙されました。
しかしその瞬間から、コスイギン首相との胸襟を開いた対話が大きく進んだのです。世界が直面する課題に取り組むには、戦争という考えをまず捨てる必要がある一一その思いを率直に語られた時のコスイギン首相の真蟄な表情は、今も忘れることができません。
それだけに、ヴァイツゼッカー大統領とソ連の人々との心の交流が、どれほど得がたいものだったかを強く感じます。
ヴァイツゼッカー大統領はまた、戦時中の鮮烈な思い出をこう記していました(前掲『ヴァイツゼッカー回想録』)。
「戦線の両側では、自分の命を気遣い、したがって、互いにとてもよく似た心配をしている人間同士が対峙していた」
「ある夜、長い列を組んで音もなく行進していた時のことだが、突然もう一つのきわめて静かな隊列が向こうからやってきた。互いの姿は見えなかったが、それでもこれがロシア人だということはすぐに分かった。双方の側とも冷静さを失わないことがなにより必要だった。われわれは沈黙のまま、互いに無傷でやり過ごした。殺し合うべきだったのだろうが、むしろ抱き合いたいくらいだった」
AIが制御する兵器において、敵味方に分かれた相手に対する複雑な思いや、「冷静さ」という言葉に込められた人間性の重みを感じて、一時的であれ、戦闘行為を踏みとどまることはあり得るのでしょうか。
もちろん、LAWSの規制においては、国際人道法の法的な観点一一すなわち、「文民保護の原則」をはじめ、戦闘員であっても不必要な苦痛を与えることを禁じた「不必要な苦痛禁止の原則」、人道法の適用上の問題がないかを確認する「新しい兵器の検証義務」など--に照らした論議も重要でありましょう。
しかしその上でヴァイツゼッカー大統領の述懐が浮かび上がらせていたような、LAWSに潜む“倫理的な断絶性”に目を向けることを忘れてはならないと訴えたいのです。
このように核兵器とは別の意味で、攻撃される側の国にとっても、攻撃する側の国にとっても取り返しのつかない結果を招くのが、LAWSに他なりません。
LAWSの禁止を求める国々と、日本のように開発をしない意思表明をする国々が、「ストップ・キラーロボット」の活動に参加するNGOと協力して、LAWSの開発と使用を含めて全面禁止する条約の制定を、早急に目指すべきではないでしょうか。