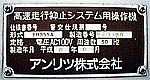第3回公明茨城県本部大会重点政策
はじめに
21世紀を目前にして、茨城県は、大きな歴史の節目にさしかかっています。
世界は本格的な「大競争の時代」(メガ・コンペティション・エイジ)へと大きく変転しています。競争を生き抜くため、我が地域の産業の国際的移転が進み、製造業の空洞化が深刻化しています。かつて全国第2位を誇った茨城県の農業生産高は、平成2年をピークに減少を続け、深刻な後継者問題など展望なき状態が続いています。県南地域は、急激な都市化や宅地化に都市の基盤整備が追いつかない状態が続き、県北の中山間地域では、人口の流失が顕著となり産業の活性化が急務となっています。昭和45年7.9%であった茨城県の高齢化率は、平成6年末には14.4%と倍増し、反面2.3人あった合計特殊出生率は1.57人に低下しました。近い将来、4人に1人が高齢者という超少子高齢社会に突入することが予想されます。
私たち公明茨城県本部は、こうした現状認識のもと21世紀を展望して、次の6大政策を掲げてその実現をめざします。
Ⅰ.市民参加と男女共生の開かれた社会を構築
政治不信・行政不信がかつてないほどに高まっている現在、国・地方ともに政策決定への市民参加が何よりも重要な課題になっています。
参加の前提には情報公開・行政手続の厳正な運用が要求されます。
また、社会のあらゆる面で男女共生の視点を取り入れた政策を積極的に進めていきます。
1.国や地方自治体の情報公開の推進
国における情報公開法の制定を進め、行政手続法を周知徹底します。
地方自治体の情報公開を徹底し、開かれた行政を目指します。
情報公開制度の適切な運用を図り、「政治倫理条例」等の制定を進めます。
2.男女が“共に生きていく”社会の実現
市町村における女性行動計画の策定を進め、その実現に全力を挙げます。また、女性行政の窓口の一元化を推進します。
地方自治体の指導的地位につく女性の割合を増やすクォータ(割り当て)制導入を進めます。
現行の「男女雇用機会均等法」を実効性あるものに改善するよう、国に働きかけます。その普及推進に努めます。
男女平等の意識を啓発するため、学校教育の中において平等教育を進めます。
Ⅱ.地方主権の確立と地方行革の推進
生活者の視点に立った住民本意の地域行政を自らの判断と責任で行うには、中央集権体制を改め、地方自治体への大胆な権限移譲と地方自治体の受け入れ体制の整備が不可欠です。そのためには、市町村合併を積極的に進め、この新しい基礎的自治体の財政や事務能力の強化と地方行革を徹底的に推進し、地方主権を確立します。
1.地方主権の確立
「地方主権基本法」を制定し、都市計画や社会福祉、教育、環境などについては、条例で決定できるようにします。
機関委任事務は、原則廃止します。
必置規制の廃止、国の出先機関の整理・縮小、国の許認可の積極的な縮減を図ります。
2.地方自治体の財政強化
国庫補助金については、統合・メニュー化、一般財源化を進めます。
地方債の許可制度については、原則廃止とします。
超過課税や法定外普通税等の課税権を拡大し、その自主的執行を促進します。
3.地方行革の推進
県内85市町村の合併を積極的に進めるとともに、地方公務員の削減を計画的に推進します。
食糧費など自治体の公費支出をチェックする外部監査制度を導入します。
入札制度の一層の透明化・公正化を図ります。
外郭団体の整理・統合の促進、職員のいわゆる天下り規制の強化を図るとともに、自治体直営から民間委託への切り替えを積極的に推進します。
4.地域における外国人の法的地位と権利の保障
定住外国人については、地方参政権を付与します。
地方公務員への外国人の採用については、国籍条項の撤廃を推進します。
Ⅲ.教育の分権化とゆとりある教育の推進
これまでの画一的な教育ではなく、多様な価値観を認め合い、福祉や地域生活に結びついていくような教育の分権化を進めます。
1.教育の分権化の推進
通学区制度の弾力的運用を図り、生徒や父兄が学校を選択できるシステムを検討します。
教員採用試験の受験資格要件を緩和し、社会人への受験資格を付与します。
県教育長の文部大臣承認制及び市町村教育長の県教育委員会の承認制を廃止します。
2.ゆとりある教育制度へ改革
学校5日制の完全実施を早期に実施します。週末も開設する保育所や放課後児童クラブ等の拡充を行います。
児童生徒の地域社会への積極的参加やボランティア活動、環境・福祉・平和教育等を充実させて知育偏重教育を是正します。また、マルチメディアを活用した教育を進めます。
県の高校進学率95.7%の実情を踏まえ、希望者全員が入学できるようにします。また「中高一貫教育」の導入や「総合学科制」「累積単位制」の拡大など多様な選択ができるシステムを実現し、学制改革を進めます。
いじめ対策として、スクールカウンセラー(臨床心理専門家)制度等の充実を図ります。
教育費の父母負担の軽減を図り、私学への助成の強化を推進します。
各種の就学奨励費・奨学金制度を拡充・強化するとともに、入学時における教育費融資制度の充実を図ります。
余裕教室の有効利用の促進を図り、地域に開かれた教育環境を整備します。
2002年サッカーワールドカップの成功を積極的に支援します。
病原性大腸菌O157による食中毒事件等をふまえ、学校給食の安全管理体制の充実を図ります。
Ⅳ.総合的都市政策と産業の育成、活性化
我が国では、農業地域では減反政策で余剰農地を持て余す農業者がおり、一方、都市地域ではマイホームの夢も叶わぬサラリーマンがたくさんいます。地方分権と規制緩和・撤廃で縦割り行政の弊害を廃して、個性豊かな都市と農業地域の整備を一体的に進めます。
更に、地域産業の空洞化をくい止め、新産業の育成を図る必要があります。
1.安全で快適な県土とまちづくり
大規模地震など自然災害から県民の生命と財産を守るため、自治体の防災体制の強化を図ります。
市町村ごとの地域防災計画の策定、見直しを進めます。
防災都市化の視点から、都市再開発を地域のコンセンサスを形成して積極的に進めます。また共同溝化、電線地下化などを進めて災害に強いライフラインの整備を図ります。
交通災害から県民の命を守る対策を強化します。交通安全施設の充実と踏切の安全対策を進めます。
2.製造業、商業の育成と活性化
製造業経営の安定を図り技術指導を充実させます。
新産業(ベンチャービジネス)の育成策の展開を図ります。
商業経営の充実安定に努めます。
中小企業の経営支援のため有利な融資制度を創設します。
恵まれた自然環境と歴史的資源を有効に活用した観光産業の育成を図ります。
3.農林水産業の振興
農林水産業後継者の育成を積極的に図ります。
農林水産業者の企業的経営を支援し、国際競争に強い体制づくりを行います。
適地適産の地域農政を積極的に進めます。産地によるブランド化を促進します。
4.都市計画法、農地法等の抜本改正
個性豊かなまちづくりを進めるため、「都市計画法」や「建築基準法」など関係法律を総合的に見直し、国の開発許可権等は地方へ移管します。
農地転用の許可権限と農業振興地域の解除権限を国から都道府県へ移譲します。また、都市計画の決定や市街化区域の設定は、都道府県や市町村が独自の判断で行えるようにします。
5.余剰農地と住宅問題等の一体的解消
余剰農地を計画的に住宅・居住環境空間の整備のために有効活用します。
「新食糧法」のもとでも事実上、半強制的に行われている減反政策を廃止するため、コメ作りにかかわる諸規制を緩和・撤廃します。
農業地域においては、余剰農地を吸収して規模拡大に誘導するなどの方策を講じて経営の安定化を図ります。
6.住宅対策と都市基盤整備
全国でも低水準の上下水道の整備を促進させます。
すべての県民がマイホームを取得できるよう制度の整備と支援策を充実させます。
高齢者・身障者・母子世帯等に配慮した公共住宅の供給と既存公共住宅のリフォームを推進します。
市街化調整区域でも宅地開発条件の整っている区域については宅地化等を認めます。特に休耕田については地元の意向を尊重して住宅供給のための転用を進めます。
慢性的な交通渋滞の緩和を図り、経済・文化の動脈としての主要道路・生活道路の整備を進めます。
北関東自動車道の早期完成と東関東自動車道の延伸を目指します。
Ⅴ.少子高齢社会にふさわしい医療・福祉制度の充実
成熟化社会に伴う国民のニーズの多様化・高度化、価値観の変化等に対応する医療・福祉制度への改革を進めます。とくに少子高齢社会にふさわしい子育て支援と介護対策の推進を図ります。
保険給付の適正化を図るため、薬価・検査料等の大幅に引き下げを促します。また、1997年度改正は医療保険制度の抜本的改革に手をつけないまま患者負担増を図るとしており、これに反対します。
老人保険制度の見直しを行い、各医療保険者からの同制度への拠出金を廃止します。
救急医療体制の充実強化を目指し、病院群輪番制、ドクターカー、救急救命センター等の充実を図ります。
糖尿病・脳卒中・骨粗鬆症・アレルギー性疾患等の異常の早期発見、専門的治療の体制整備を図ります。
県内どこでも身近に、専門的にエイズ検査が受けられる予防体制の整備を図ります。
腎バンク・アイバンク・骨髄バンク等、各バンクの整備促進を図ります。
個人の病歴・診療歴・投与中の薬等を記録した健康カードによる、健康管理システムの導入を促進します。
2.介護に対する社会的支援の強化
新しい高齢者介護システムの構築に当たっては介護保険制度の創設を柱にサービス供給体制の早急な整備を進めます。
介護保険制度は保険者となる自治体及び介護現場の意見・要望が十分に反映されたものとします。
全国平均以下のホームヘルパー、ディサービス、ショートスティ事業のハード・ソフト両面における充実を図ります。
特別養護老人ホーム、老人保健施設などの福祉施設の拡充を図ります。
高齢者や障害者・難病患者と、その家族に対する看護・介護体制をつくるため、在宅介護支援センター・老人訪問看護ステーション等の「地域ケアシステム」の整備を図ります。
介護慰労金の増額を図り、在宅看護者の負担軽減を促進します。
住民参加によるボランティア活動の活性化を図り、ボランティア活動の基盤の強化を促進します。
3.安定した年金制度への改革
高額所得者の給付制限、恩給等との併給調整など給付の適正化を図ります。
基礎年金の国庫負担の引き上げを国に働きかけます。
4.子育て支援対策の拡充
多様なニーズに対応した利用しやすい保育サービスを整備します。保育措置制度や利用料金体系の見直しを行い、保育料負担の軽減を図ります。
乳幼児医療費の無料化、児童手当制度の充実、放課後児童クラブの拡充、児童館・児童センター等の整備の促進等の諸施策を推進します。
「育児休業法」を民間企業等のも実効性あるものに改善するよう、国に働きかけます。またその普及推進に努めます。
Ⅵ.自然と共生する環境政策の展開
環境行政機能を強化し、環境汚染に対する対症療法型から未然予防型の環境政策への転換を図るとともに、生活者重視の視点からのわが地域の環境行政を見直します。
1.環境保護行政の強化
公害のない郷土づくりに努めます。地球温暖化対策、オゾン層対策、酸性雨対策、ダイオキシン対策など地球環境を守る施策を展開します。
霞ヶ浦をはじめとする湖沼と河川を汚濁から守り、貴重な森林を涵養し、水と緑の郷土づくりを進めます。
環境と調和した省エネルギー・省資源型のエコポリス(環境共生都市)づくりを目指し、緑・水・土壌等の適切な管理、都市景観、廃棄物の減量・リサイクルを計画的に進めます。
2.環境アセスメント法の制定
良好な環境に悪影響を与えるおそれのある開発・計画を抑制するため、自治体や専門家・住民参加と情報公開に基づく、実効ある「環境アセスメント法」を目指します。
事業実施の決定以前の計画・立案段階の環境影響行為についても環境アセスメントを実施します。具体的な評価対象には、生態系の保全や循環型社会の形成に資する廃棄物対策も加えます。
3.リサイクル社会への転換
リサイクル(資源循環型)社会への転換をめざし、事業者がすべての生産物の最終処分・再資源化まで責任を持つようにするため「廃棄物処理法」を強化します。
製品・容器等への廃棄規格表示や再生利用基準の導入、品目ごとの分別収集・リサイクル目標の明確化を推進するとともに、ゴミ収集有料化等を含めた減量対策を図ります。また、最終処分場の処分・構造基準及び維持管理基準を大幅に強化します。
自然保護や環境教育、環境の修復、新しい環境関連産業の育成・振興と、そのための規制撤廃を図ります。
義務教育における環境学習や体験学習、地域での環境保護・美化活動を充実するとともに、環境ボランティアやアドバイザー等環境マンパワーの育成・支援を拡充します。
| このページは、茨城県議会井手よしひろの公式ホームページのアーカイブ(記録保管庫)の一部です。すでに最終更新から10年以上経過しており、現在の社会状況などと内容が一致しない場合があるかもしれません。その点をご了解下さい。 |