「子ども誘拐した」 全県で発生、振り込め詐欺未遂
茨城新聞(IBARAKI-WEB 2005/11/7)
電話で「子どもを誘拐した」と脅し、現金を要求する振り込め詐欺未遂事件が今月、県内で続発している。県警捜査二課によると、11月1日~7日に11署管内で計21件を認知、7日だけで12件に上った。同課は「同様の手口は以前から散発的にあったが、この一週間ほぼ全県で集中発生している」と警戒を強めている。県教委は7日、各県立学校と市町村教委あてに注意を呼び掛ける緊急通知を出した。
手口は、いずれも男の声で小・中・高校生の自宅に「子ども(娘)を誘拐した」との電話がかかり、高額な現金を要求。応対した母親を動転させ信用させようと、「お母さん助けて。首を絞められている」などと子どものような泣き声を聞かせたり、携帯電話番号を聞き出して加入電話と携帯両方を通話中にし、警察や家族と連絡を取らせないようにするなど、卑劣で巧妙な共通点があるという。最も多い要求額は300万円。
ネット関連の事件の2つ目は、児童生徒を誘拐したと身代金を要求する悪質な振り込めさぎの問題です。
8日、井手よしひろ県議が県教育庁ならびに警察本部に聴取した内容によると、10月下旬から11月7日にかけて、小中学校の児童生徒の自宅に不審な電話が、数多くかけられているとのこと。電話の向こうで、子供のような泣き声で、「助けて、首を絞められる」「お母さん助けて。おじさんに誘拐された」などと話した後に、男が電話口に代わり、「子供を誘拐した」、「娘を預かっている」などと脅かし、高額な金銭を要求するそうです。
子供の名前を正確に聞き返したり、事件の詳細を追及すると、そのまま電話は切られてしまいます。
今までの事例では、誘拐したとされた児童、生徒は全員無事でした。
こうした悪質事犯に対して、教育長や警察は以下の対応策を強調しています。
1.冷静に対応する。
2.こちら側の情報はもらさない。相手の状況をできるだけ詳しく聞き出す。
3.電話を切ったのち学校に連絡し、児童生徒の安否を確認する。
4.金銭を要求されても絶対に振り込まない。
5.未遂であっても警察と学校に通報・連絡する。
2.こちら側の情報はもらさない。相手の状況をできるだけ詳しく聞き出す。
3.電話を切ったのち学校に連絡し、児童生徒の安否を確認する。
4.金銭を要求されても絶対に振り込まない。
5.未遂であっても警察と学校に通報・連絡する。

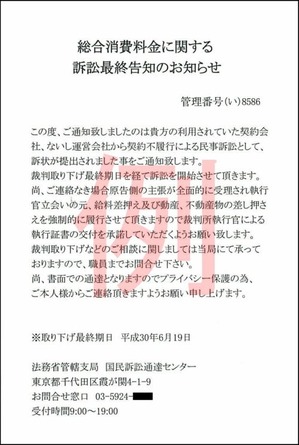
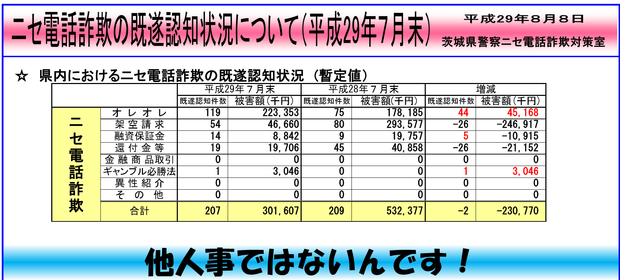

なんとも悪質な振り込め詐欺が発生しています。「子どもを誘拐した!金を振り込め!」という手口です。子どもの声まで使ってだますわけですから、悪質この上ありません。今日地元の大曽根小学校では、学校から各家庭へ「注意を呼びかける文書」を配布しました。もし、このような電話がかかってきたら、あわてずに学校に確認しましょう。