高騰を続けてきたガソリン価格が、9月に入り、やっと少し値下がりしてきました。
ガソリン高騰の原因は何だったのか。また、2カ月前から原油は下がっているのに、なぜすぐにガソリン価格に反映されないのか。石油価格の問題を整理したいと思います。
今回のガソリン高騰の原因は
ガソリン高騰の原因のひとつは、中国やインドなど新興国の経済発展で石油の消費量が伸びたことです。特に中国は今回の北京オリンピックに伴って急激な景気拡大が起こり、石油の需要も急増しました。インドも先頃発表された20万円台の自動車に象徴されるように、今後は車の普及がいっそう進み、石油の消費量はさらに増えると見込まれます。先進国は温暖化防止の一環として、省エネに向かって努力していますが、世界的に見ると、石油の消費量を減らしていくことは難しいのが実情です。
石油の消費が増えているのに、産油国の生産能力は増えていないのが、原油高騰の第2の理由です。90年代までは原油の価格は安く、需給バランスもとれていたので原油産出国のOPEC(石油輸出国機構)も、生産を増やす必要はないと考えていました。今は需要が増えているのですから増産すればいいじゃないかと考えられますが、中東地域は政情が安定していないため、石油関連施設などもテロの標的になることがあります。そのため増産に踏み切るにはリスクが高すぎるという判断があるようです。
最大の原因は投機マネーの流入
今回の原油高騰の最大の原因は、投機的資金が原油市場に流れ込んだためだと言われています。サブプライムローン問題で行き場を失った投機資金は原油や金など金属などの市場に向かいましたの中には国富ファンドと呼ばれる中東湾岸産油国の政府系投資機関が運用する資金もあり、原油の市場は混乱を極めることになりました。もともとさほど大きくないニューヨーク市場などに世界の巨大ファンドが入ってきたことを、ある金融関係者は「池にクジラが入って暴れている」と表現しました。
その結果、原油価格は2007年の8月には1バーレル(約159リットル)72ドル程度だったものが、2008年7月には131ドルと、約2倍に跳ね上がりました。専門家の意見では、このうち需要と供給の関係での価格は90ドル程度で、あとは投機資金によるバブル的な値上がりではないかと言われています。
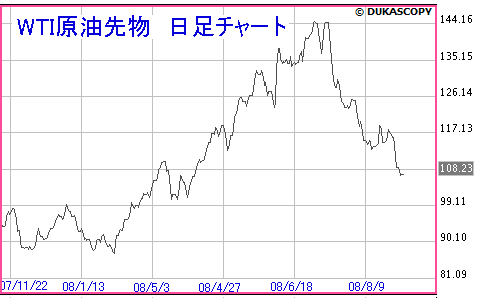
価格決定が遅くなる理由
一時、200ドルまで上昇するなどの噂も飛び交いましたが、7月の147.27ドルをピークに原油価格は鎮静化しつつあり、9月の原油価格は直近で109ドル辺りまで落ち着きいてきています。
一般のガソリン価格も前週比5.5円安の176.2円(9月3日、石油情報センター発表)と185円のピーク時に比べ、10円近く下がってきました。
とは7月以降の原油価格の急落に比べると、ガソリン価格の値下がりは遅いという印象はぬぐえません。
これは石油元売り各社の価格の決め方が、原油価格の変動とは、時間的なずれが生ずるためです。元売りの価格は、「前月1カ月間の原油の平均価格と為替レートをもとに月初めに卸価格を決め」れるので、原油価格の推移がガソリン価格に反映するまで、1カ月近くかかってしまうのです。この仕組みにより、値上がりの時も駆け込み給油などで混乱が起きました。
一部の元売りでは10月から、この卸価格の決定方式を変更し、原油価格の変動がすぐに卸価格に反映されるように改めるそうです。
石油価格を実需に沿ったものに
先物市場とは本来、石油を安定した価格で将来も手に入れるための危機回避の手段であったはずです。たとえば航空会社が燃料を現在の価格で確保して、将来値上がりしても困らないようにするといった目的で使うならば有用なのですが、現在は投機目的のマネーゲームの舞台となってしまっているのです。
このような実態を実需主体の市場に戻すためには、実際に石油を消費する企業(航空会社や石油販売会社)だけが参加できるように制限するとか、それが無理だとしても、空売りなどができないように規制するなど、投機的な動きを押さえることが求められます。原油市場に限らず世界的なマネーの暴走を抑えるには、何らかの国際協調による施策が必要なのではないでしょうか。
(このブログは、公明党ホームページの内容を参照しました)



