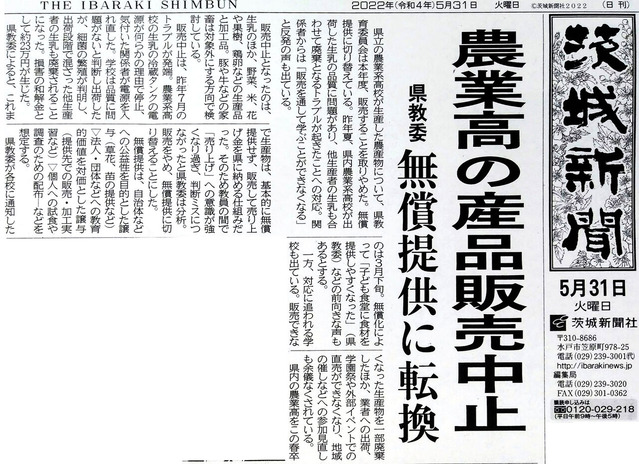1月8日のNHKクローズアップ現代では「故郷(ふるさと)はよみがえるか~検証・過疎対策の大転換~」と題して、新たな過疎対策の切り札として期待されている「集落支援員」について紹介していました。
故郷(ふるさと)はよみがえるか
~検証・過疎対策の大転換~
NHKクローズアップ現代(2009/1/8放送分)
今年3月、国の過疎対策が大きく変わる。これまでの公共事業中心、つまり「モノによる支援」から「人による支援」に転換するのだ。始まるのは「集落支援員制度」。過疎に悩む全国の集落に専門の相談員を置き、集落の課題や要望(例えば、高齢者の交通手段や農林業の人手不足など)を聞き取る。そのうえで対策案を作り、市町村と連携して実現を図る。その人件費や活動費を国からの交付税でまかなう仕組みだ。背景には、昭和45年の過疎法制定以来、道路や施設建設などに合計75兆円の予算が注がれながら過疎化がストップしなかったことがある。この新制度には可能性と課題が混在する。モデルの一つとなった新潟県の限界集落には、活気が戻りつつある一方で、集落支援員の人選やバックアップ体制、活性化策の継続性など解決すべき課題も多い。過疎対策の「最後の一手」とも言われる新制度を実り多きものにするために何が必要なのか、検証し提言する。
総務省は昨年(平成20年)8月1日付で、「過疎地域等における集落対策の推進について」との通知で、人口減少や高齢化が深刻な集落を巡回し、地域活性化策などを助言する「集落支援員」制度を自治体に導入するため、支援員を雇用する市町村に特別交付税を配分することを公表しました。
集落支援員は、地域事情に明るい人材を確保するため(1)職員OBや農業委員などの経験者を非常勤の嘱託職員として自治体が採用、(2)特定非営利活動法人(NPO法人)に自治体が業務を委託、などを想定しています。集落自体の存続が危惧される「限界集落」や、市町村合併で役場が廃止された旧町村地域などを定期的に巡回し、住民らと協力して人口や生活状況などを把握するための「集落点検」を実施することになっています。
総務省は支援員の人件費や集落点検にかかる費用を財政支援するほか、都道府県が管内市町村でモデル事業を行う場合も支援の対象とします。
さらに、集落点検の結果に基づいて住民と支援員が協議して取り組む地域活性化策の必要経費についても財政支援を検討しています。
この「集落支援員」は、新潟県上越市の若者を中心とするNPO法人「かみえちご山里ファン倶楽部」の取り組みがそのモデルケースとなっています。「かみえちご山里ファン倶楽部」は、上越市の西部中山間地域(桑取、谷浜、中ノ俣、正善寺地区)を中心に、水源の森から海まで、川に育まれた豊かなフィールドを活動の拠点とするNPO法人です。この地では、かつて農業と養蚕を中心に山里の文化を形成してきました。現在も、雪国の民俗文化を色濃く残す伝統技術、伝統行事・芸能などが多数残っています。しかし、深刻な過疎化と少子高齢化に悩まされ、地域社会そのものが崩壊する危険性もありました。7年前から、この地域の自然、景観、文化、及び地域の農林水産業を「守る、深める、創造する」ことで、豊かな地域文化を育み、地域資源を生かした様々な活動を行っているのが8名の若者スタッフです。
彼らは通信販売などで資金を調達していましたが、活動を継続させるには資金の調達が最大の課題でした。そこで、国や自治体が最低限の活動費を支援することで、“人”による過疎地域の活性化を行おうとするのが、「集落支援員」制度の発想です。
茨城県を含む関東近県(栃木、群馬、千葉)では、未だに「集落支援員」を配置している自治体はありません。平成21年度からの実施を目指して、茨城県内でもモデルケースを作ることを検討しています。
 参考:「集落支援員制度」について(総務省のHP)
参考:「集落支援員制度」について(総務省のHP)
 参考:NPO法人「かみえちご山里ファン倶楽部」のHP
参考:NPO法人「かみえちご山里ファン倶楽部」のHP