1月8日、公明党総点検運動推進本部は、「介護総点検の調査結果」の第一次集計分(速報値)の概要を発表しました。
この介護保険総点検は、全国3000人超の公明党議員が、昨年(平成21年)11月から12月にかけ、(1)街角アンケート用、(2)要介護者および介護家族用、(3)施設・事業者用、(4)介護従事者用、(5)市区町村用―の5種類の調査票を基に、基本的に訪問聞き取り調査を実施したものです。なお、街角アンケートは党ホームページでも回答を受け付けました。
街角アンケート(回収数:7万6689件)
- 介護保険制度の開始から10年を経過し、7割近くの人が制度を知っていると答え、認知度の高さがうかがえたが、知らない人も3割に上りました。今後さらに普及啓発に努めることが必要との結果になりました。
- 介護に対する将来の不安は、「経済的負担」「自分自身や家族が寝たきりや認知症になるかもしれない」が、ともに約6割に達しており、「家計」や「健康面」に不安を感じています。また、自宅の介護に対する不安、特別養護老人ホームなど、介護施設不足に対する不安の声がともに3割に上りました。
- 介護を受けたい場所は、「入所系の介護施設」(45.8%)と「自宅」(42.3%)がともに高率でした。病院は12.8%と少数でした。
- 回答者のうち、8割近くの人が、家族の中で誰も介護保険サービスを受けていませんでした。要介護者が家族内にいた人は3割強で、このうち、介護保険を利用していない人が4割強を占め、その理由で最も多かったのは「家族介護で間に合っている」(19.1%)との回答でした。
- 介護保険料については、「高すぎる」が約4割と最も多く、「将来どこまで増えるのか心配」「上限、月額5000円が限界」などの意見が寄せられました。その一方で、保険料の月額を知らない人も3割もいました。
- 「介護職に就いてみたいか」との問いには、4割の市民が重労働、低賃金を理由に、「あまりやりたいと思わない」と答えました。
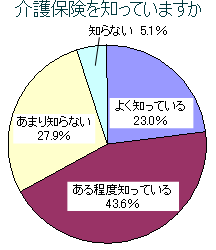
要介護者・家族調査(回収数:6265件)
- 要介護認定基準については、5割強(52.5%)の人が「適当」と答えたものの、「軽すぎる」「やや軽い」は3割に上っています。
- 介護を受けている場所は、7割以上の人が「自宅」と答え、特別養護老人ホームやケア付き住宅などで暮らす人は2割でした。
- 自宅で介護を受けている人のうち、困っていることは、「介護する家族の負担が大きい(身体的、精神的、経済的)」(35.8%)が最も多い。「本人や家族の具合が悪くなった時に一時入所できる施設がない」(18.8%)、「利用料が高い」(18.6%)が続いています。「介護施設への入所待ち」は11.2%でした。
- 自宅での介護サービス利用は「デイサービス」(40.3%)、「ショートステイ」(17.4%)、「福祉用具貸与」(16.9%)、「ホームヘルプサービス」(15.6%)の順となっています。
- 介護保険に対する不安や不満は「制度が分かりにくい」(32.5%)、「利用料の負担が重い」(30.4%)が多くなっています。次いで「要介護認定の方法」(21.8%)が続いています。
- 介護保険料の負担感については、負担を感じる人が7割弱を占め、「適当」と答えた人の3倍強に達しています。
- このほか、介護保険制度が複雑で分かりづらく、受けたいサービスが受けられていない。申請の簡略化や、もっと周知徹底してほしいという意見が多く寄せられています。
- 年金収入のみの高齢者夫婦が負担できる介護保険料にしてほしいとの訴えがありました。
- 在宅介護は家族の負担が重い。緊急時に入所できる施設を増やしてほしいとの意見も多く寄せられました。
介護事業者調査 (回収数:4587件)
- 事業所の介護従事者の人員が足りているか聞いたのに対して、半数近い事業所が「足りている」(44.5%)と答えたものの、一方で、介護従事者が「不足している」と答えた事業所は、「介護職」が27.2%、「看護師」が23.7%、「ホームヘルパー」が18.2%の順になりました。
- 介護従事者の平均勤務年数は5年以上働いている人が24%を占めましたが、勤務年数が比較的短い人が多い傾向にあります。勤務年数が短い理由として、「業務内容に対して収入が低い」「心身の負担が大きい」ことが挙げられています。
- 勤続年数や有資格者が必ずしも給与体系に結び付いていないことへの不満もあります。
- 事業所で、最も力を入れていることは、「スタッフの技術の向上」で、9割近くを占めました。
- 介護保険制度の見直しについては、「事務量の軽減」「要介護認定のあり方」「情報公表制度」「公費負担分の増額」を望む声が格段に多くありました。
- 介護報酬の見直しについては、業務量や難易度に応じた介護報酬体系への改善、24時間稼働する施設の介護報酬の引き上げを求める声が圧倒的に多く寄せられました。また介護報酬の加算の見直しではなく基本部分の見直しを求める声も強いことがわかりました。
- 介護保険料の徴収を20歳からに引き下げて財源に回してはどうかとの意見もありました。
- 介護職員処遇改善交付金への事業所の対応では、「一時金の支給を行い今後の様子を見る」が5割を超えました。
- そのほか、介護職員以外への対応では、看護職員や事務職員との兼ね合いに悩んだという意見が多くありました。対応については、介護職員のみの事業所や、介護職員以外にも一時金を出した事業所など、対応が分かれました。
- 介護保険制度に対する要望では、「事務量の軽減」や、「利用者の自己負担額は年金以内にすべき」「24時間体制の介護職員の給料が低い」「施設入居の希望が多く入居待ちが多い」「認知症に対応した制度の充実」「情報公表制度は必要ない」など、見直しを求める声が多く寄せられました。
介護従事者調査 (回収数:1万1286件)
- 介護の仕事を選んだ理由については、「人の役に立つ働きがいのある仕事だから」が6割弱を占め、次いで「介護に興味があったから」「今後もニーズの高い仕事だから」と続いています。
- 仕事に対する満足度の高いものは、「仕事内容にやりがいを感じる」が6割強で、仕事に誇りを持って携わっていることがうかがえます。次に「福祉に貢献できる」「知識・専門性が発揮できる」の順でした。
- 今後も仕事を続けていきたいかとの問いには、7割が「働ける限り続けたい」と答えました。
- 離職率が高い原因は、「業務内容に対して収入が低い」「心身の負担が大きい業務内容」と答えた人が、それぞれ約8割(複数回答のため)を占めました。
- このほか、介護従事者の処遇改善については、女性にとって働きやすい職場環境へ、保育所等を近くに併設したり、産休後のバックアップ体制の充実が必要との意見がありました。
- 介護従事者の相談に乗ってくれる専門員や電話相談体制の構築、リフレッシュ休暇など、メンタルケアの充実を求める声がありました。
- 人員の確保では、せめて利用者対職員が2対1になると、もっと高齢者とかかわることができ、高齢者も生き生きとした生活ができるとの意見もありました。
- 利用者からのセクハラも多い。社会的に存在意義を高める方策を国が考えてほしいとの声がありました。
- 経験年数や資格等のキャリアにあった報酬単価への改善を求める意見が寄せられました。
- 介護職員処遇改善交付金の対象職種を拡大して永続を希望する声がありました。
- 事務処理が複雑で多すぎることを指摘し、簡素化を求める声が多く寄せられました。



