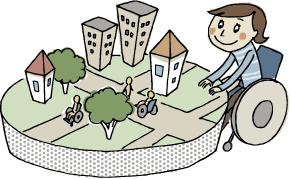 昨年(2010年)12月24日、中央教育審議会(中教審)の特別委員会は、特別支援教育の在り方について「論点整理」を公開しました。その中では、障がいの有無にかかわらず「共に学ぶ」重要性を確認しながらも、現在の特別支援教育が抱える課題を明示しました。現在、文部科学省では国民からの意見を募集しています。
昨年(2010年)12月24日、中央教育審議会(中教審)の特別委員会は、特別支援教育の在り方について「論点整理」を公開しました。その中では、障がいの有無にかかわらず「共に学ぶ」重要性を確認しながらも、現在の特別支援教育が抱える課題を明示しました。現在、文部科学省では国民からの意見を募集しています。
 参考:中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の在り方に関する特別委員会論点整理に関する意見募集の実施について
参考:中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の在り方に関する特別委員会論点整理に関する意見募集の実施について
日本では、障がいのある一人一人の児童生徒の教育的ニーズに応じて適切な指導を行うための特別支援教育が、2007年度から本格スタートしました。盲・聾・養護学校は特別支援学校に、特殊学級は特別支援学級に改められ、注意欠陥・多動性障害(ADHD)や高機能自閉症など発達障害についても適切な教育を行うことが明文化されていまする。
一方、政府は国連で採択された「障害者の権利に関する条約」(2007年9月に署名)の批准をめざしており、同条約で掲げられているインクルーシブ教育システム(包容する教育制度)と調和する特別支援教育の在り方について、議論が続いています。
すでに、内閣府に設置された「障がい者制度改革推進会議」は昨年6月、「障害の有無にかかわらず、すべての子どもは地域の小・中学校に就学し、かつ通常の学級に在籍することを原則とする」などの見解を盛り込んだ「第一次意見」を発表しています。
今回、昨年8月からの8回にわたる審議を経て、中教審の特別委員会が公開した論点整理では、インクルーシブ教育の重要性を認めながらも、障がいの状態などを無視して進めれば、「将来、社会に参加し市民として生きる時になって、障害のある子ども本人に対しより大きな不平等をもたらす可能性がある」と指摘。現場の声を反映し、拙速を避けた内容になっています。
審議会の論議でもたびたび指摘され、今回の論点整理にも盛り込まれているが、わが国では、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導を受けている児童生徒は約2%にすぎません。近年、特別支援の対象となる児童生徒が急増しているとはいえ、米国の約10%、英国の約20%に比べ、かなり低いという実態があります。これは、本来、教育支援を必要とする子どもたちが通常の学級で学んでいる可能性が高いことを示しています。乳幼児期を含め早期から教育相談や就学相談を行う体制を整備し、就学先の決定が円滑に行われる制度改革は不可欠です。
一人一人を大切にする教育をどう実現するか。今回の中教審の論点整理を契機に、特別支援教育の充実へ、議論を深めていきたいと思います。
中央教育審議会初等中等教育分科会
特別支援教育の在り方に関する特別委員会
論点整理概要
1.インクルーシブ教育システム構築に向けての特別支援教育の方向性について○インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)の理念とそれに向かっていく方向性に賛成。
○インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある児童生徒に対して、その時点で教育的ニーズに最も的確にこたえる指導を提供できる多様で柔軟な仕組みを整備することが重要。子ども一人一人の学習権を保障する観点から、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要。
○障害のある子どもと障害のない子どもが共に学ぶことは、共生社会の形成に向けて望ましいと考えられる。同じ社会に生きる人間として、お互いを正しく理解し、共に助け合い、支え合って生きていくことの大切さを学ぶなど、個人の価値を尊重する態度や自他の敬愛と協力を重んずる態度を養うことが期待できる。
○インクルーシブ教育システム構築に向けての今後の進め方については、短期と中長期に整理し段階的に実施していくことが必要。2.就学相談・就学先決定の在り方について○一人一人の教育的ニーズに応じた支援を保障する就学先を決定するため、また、本人・保護者、学校、教育委員会が円滑に合意形成を図るため、医療や福祉の関係部局等との連携を図りながら、障害のある子どもの教育相談・支援を乳幼児期を含め早期から行うことが必要。
○就学基準に該当する障害のある子どもは、特別支援学校に原則就学するという従来の就学先決定の仕組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、専門家の意見等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みとすることが適当。その際、本人・保護者に対し十分情報提供をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と教育委員会、学校等が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とし、最終的には市町村教育委員会が決定。本人・保護者と教育委員会、学校等の意見が一致しない場合の調整の仕組みについて、今後、検討していくことが必要。
○就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図り適切な支援を行っていくことが適当。
○市町村教育委員会は、障害のある子ども本人・保護者に対して十分な相談・情報提供ができる体制を整備することが必要。その支援のために都道府県教育委員会は、専門的な相談・助言機能を充実・強化することが必要。3.インクルーシブ教育システムを推進するための人的・物的な環境整備について○発達障害も含め、特別支援教育の更なる充実のため、現場での意識改革、指導方法の充実、人的・物的な環境整備等が必要。
○合理的配慮については、ソフト・ハードの両面が必要であり、今後、障害種別の内容も含めて一層の検討が必要。
○特別支援学校と幼稚園、保育所、認定こども園、小・中・高等学校等との間で行われる交流及び共同学習を一層推進するとともに、例えば、居住する地域の小・中学校に副次的な学籍を持たせるなど一層の工夫が必要。
○特別支援学校のセンター的機能を一層活用することが必要。4.教職員の確保及び専門性向上のための方策について○インクルーシブ教育システムの構築のため、教職員の確保や教員の専門性の向上を図るための具体的方策として、大学での教員養成の在り方、管理職を含めた現職教職員の研修体系、採用・配置などについて、今後検討していくことが必要。



