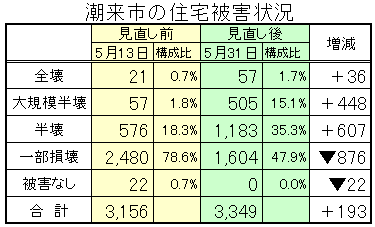 6月6日、東日本大震災による液状化被害に見舞われた茨城県の5市と千葉県の2市の市長が、細川厚生労働相と松本防災担当相に液状化被害に遭った住宅に対し、国の支援拡大を求める要望書を提出しました。茨城県からは内田俊郎鹿嶋市長、田口久克稲敷市長、保立一男神栖市長、伊藤孝一行方市長、松田千春潮来市長の5市長が参加。千葉県からは宇井成一香取市長、浦安市の松崎秀樹市長が参加しました。
6月6日、東日本大震災による液状化被害に見舞われた茨城県の5市と千葉県の2市の市長が、細川厚生労働相と松本防災担当相に液状化被害に遭った住宅に対し、国の支援拡大を求める要望書を提出しました。茨城県からは内田俊郎鹿嶋市長、田口久克稲敷市長、保立一男神栖市長、伊藤孝一行方市長、松田千春潮来市長の5市長が参加。千葉県からは宇井成一香取市長、浦安市の松崎秀樹市長が参加しました。
市長らが提出した要望書によると、内閣府が5月2日に液状化被害を受けた住宅を救済するために発表した被害認定の新基準でも、多くの救済されない世帯が残っていると指摘。その上で、基準のさらなる緩和や、被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給対象外とされている半壊世帯への支給を求めました。
また、厚労省所管の災害救助法による、半壊した住宅の応急修理に支援金(最大52万円)の支給要件が「液状化被害を受けた住宅の現状にそぐわない」として、災害救助法の弾力的な運用などを求めています。
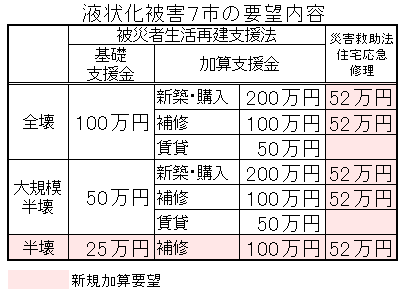
また、潮来市の松田市長は、「住宅の修理のために二重ローンを組まざるをえないなど被災者の置かれている状況は厳しい。液状化の被災者救済は地方だけでは力不足なので国の支援をいただきたい」と、強く訴えました。
こうした要望に対し、細川厚労相からは「前向きに検討したい」、松本防災相からも「必要に応じて見直したい」との回答を得たと、参加した市長らは語っています。
6月7日、井手よしひろ県議が潮来市の柚木巌市議を通して提供を受けた資料によると、潮来市では日の出地区を中心に約2100棟が液状化の被害を受けました。旧基準では全壊21棟、大規模半壊57棟、半壊576棟、一部損壊2480、損害なし22棟でしたが、基準の見直しで全壊57棟(+36棟)、大規模半壊505棟(+448棟)、半壊1189棟(+607棟)、一部損壊1604棟(▼876棟)、損害なし0棟(▼22棟)となりました。
被災者生活再建支援法では、世帯当たり「基礎支援金」として全壊世帯に100万円、大規模半壊世帯に50 万円が支給され、「加算支援金」として、住宅を建設・購入する場合は200万円、補修する場合は100万円、賃借する場合は50万円が加算されます。
液状化被害を受けた世帯の多くは、住宅自体の解体や建て直しを行うことなく、地盤の改良と住宅の補修を行うことになります。その場合、全壊認定を受けても最大200万円しか支援金はありません。大規模半壊の場合は、150万円、一部損壊では全く支援金が支給されません。したがって、潮来市の場合は、何らかの支援が受けられる家屋が78棟から562棟に7倍以上に増えましたが、全体の被災世帯のわずか16.8%にすぎません。
一方、液状化して不等沈下した建物を正常に戻すには、500万円から1000万円の費用が掛かるとされ、そこで、認定基準の更なる緩和が必要になっています。
また、半壊と診断された住宅には、災害救助法の応急修理の規定を適用すべきだとの声があります。災害救助法23条の6項には、「災害にかかつた住宅の応急修理」が認められており、厳しい所得制限や申請期間の制限があるものの52万円の修理費が認められています。そこで、申請条件の緩和がぜひ必要です。
また、千葉県では県が独自に、国の支援制度の対象とならない住宅について、千葉県単独で100万円を上限に支援金を支給する制度を創設しました。約8000棟の適用を見込み、総事業費は78億円です。
支援金は、住宅を解体するか地盤を修復すれば100万円を支給します。半壊で補修する場合は25万円が支給されます。茨城県も、こうした支援策を検討する必要があります。
 平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、大規模な液状化現象が起こり住家等に甚大な被害が発生いたしました。このことにより、液状化被害を被った多くの自治体から支援策等に対する要望に前向きに受け止め、被災地視察など現状把握に努めていただきました。その結果、平成23年5月2日付け内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(災害復旧・復興)付事務連絡をもって、「地盤に係る住家被害認定の調査・判定方法について」で示されたとおり、傾斜判定の拡大及び潜り込みの新基準など被害認定の運用基準の見直しを行っていただきましたこと、誠にありがとうございました。
平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、大規模な液状化現象が起こり住家等に甚大な被害が発生いたしました。このことにより、液状化被害を被った多くの自治体から支援策等に対する要望に前向きに受け止め、被災地視察など現状把握に努めていただきました。その結果、平成23年5月2日付け内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(災害復旧・復興)付事務連絡をもって、「地盤に係る住家被害認定の調査・判定方法について」で示されたとおり、傾斜判定の拡大及び潜り込みの新基準など被害認定の運用基準の見直しを行っていただきましたこと、誠にありがとうございました。しかしながら、今回の認定基準の見直しだけでは、まだまだ救われない被災者が大勢おります。液状化被害を受けた被災者が再建するには、多額の費用と時間が掛かり、住民にとって多大な負担と不安を抱えている現状を再認識していただき、更なる認定基準の緩和及び半壊世帯への支援の拡充、さらには、液状化被害に対する新たな支援のための特別立法の制定など、少しでも多く被災者の生活再建に繋がるものとなるよう、以下の要望事項の実現を強く要望いたします。
1.災害に係る住家の被害認定基準の更なる運用見直しについて
災害に係る住家の被害認定基準運用指針の見直しで、不同沈下住宅が大規模半壊となる傾斜基準は、60分の1(2センチメートル)以上20分の1(6センチメートル)未満と示されたが、更なる基準緩和として、80分の1(1.5センチメートル)以上20分の1(6センチメートル)未満とすること。傾斜の判定基準では、住家の外壁の四隅または四隅の柱の傾斜を計測し、その単純平均したものとなっている。これを計測値の最大値をとることとすること。
また、住家の潜り込み判定において大規模半壊となる基準は、床まで地盤面下に潜り込んでいる場合と示されたが、基準が非常に厳しく、潜り込み被害のほとんどが被災者生活再建支援法に基づく支援の対象外となる半壊以下の被害に認定されていることから、大規模半壊となる基準を基礎の天端下25センチメートルまで地盤面下に潜り込んでいる場合とすること。
なお、今回の指針の見直しを「特例」ではなく、恒久的なものとすること。
※(○センチメートル)は、垂直高さ120センチメートルに対する水平方向のずれ
2.半壊世帯を対象とする被災者生活再建支援制度の見直しについて
内閣府(防災担当)発表のとおり、医療関係者等のヒアリングを行い設定した居住者が苦痛を感じるとされる値となる傾斜100分の1(1.2センチメートル)以上80分の1(1.5センチメートル)未満では半壊判定となり、被災者生活再建支援制度の対象とはならず、ほとんどの支援が受けられない現状にある。このことから、半壊世帯に対しても被災者生活再建支援制度の対象とすること。(別表参照)
3.被災者生活再建支援法の適用要件の緩和について
現行の被災者生活再建支援法の適用要件は、施行令の第1条で、住宅の全壊被害が発生した世帯数で示されている。今回、被害認定基準が見直されたが、市町村によっては新基準でも全壊認定が難しく、同じ震災で被災しても被災者生活再建支援法が適用されない状況にある。このたびの液状化被害は広範囲の市町村に及ぶものであり、公的支援制度の弾力的な適用、拡充が求められる。被災者生活再建支援法の適用要件の全壊世帯のみの判断だけでなく、大規模半壊または半壊2世帯を全壊1世帯として扱うなどの弾力的な適用を図ること。
4.住家の地盤面下への潜り込み被害に対する支援について
降雨の際、恒常的に床下・床上浸水することなどから設定された潜り込みの住家被害の判定基準が新たに設けられたが、被害認定の対象とならない住家が敷地ごと沈下し同様に床下・床上浸水する住家も含め、このような被害を受けた住家に対しては、抜本的な被害解消のためにジャッキアップなどの住宅改修費に対し助成する制度を創設すること。
5.災害救助法に基づく住宅の応急修理の抜本的見直しについて
半壊住宅に対する応急修理については、災害救助法に基づく住宅の応急修理を活用できることとなっているが、昭和20年代にできた法律に基づくものであり、現状にそぐわない内容となっている。特に、今回の液状化被害の住宅は、地盤を含めた根本的な改修をしないと居住が困難な状況にあるため、応急的な修繕では避難解消には繋がりづらい状況にある。よって、所得制限の撤廃など対象世帯の要件緩和や期間の延長、応急修理のみならず住宅改修や解体撤去費用としても活用できるよう、より被災者支援に繋がるための「災害救助法に基づく住宅の応急修理」を抜本的見直しをすること。(別表参照)
なお、5月2日の新基準のにより、新たに半壊以上になった住宅で、すでに自費で応急修理を行った世帯に対しても、災害救助法に基づく住宅の応急修理を適用すること。
6.液状化被害等に対する新たな支援のための特別立法の制定について
今回の震災では、広域にわたり甚大な液状化被害が発生し、住宅のみならず農地や農業施設にまで及んでおり、多くの方々が被災されているが、現行制度では十分な支援が受けられない現状にある。また、同様な地震が発生した場合、再び液状化被害に見舞われる可能性が高い。そこで、今回の液状化被害等及び対策に対する新たな支援のための特別立法を制定すること。



