3月16日行われた県議会予算特別委員会では、茨城県議会公明党の高崎進県議が、国の出資による震災復興基金の早期設立を強く求めました。高崎県議は、県内で12万棟を超す一部損壊住宅の世帯は被災者生活再建支援法の支援金の対象外となるため、修復もままならない例を挙げ、「総合的な支援のために復興基金の創設が必要」と強調しました。東日本大震災からの復旧・復興のためには莫大な資金が必要となります。その財源確保は、税金や国債(県債)などの通常の調達方法では、とても調達できません。特別な枠組みが必要となります。また、現行法では対応できない被災者の救済や自立支援など、震災対策を長期的に進めることが必要であり、これも災害復興基金が必要な大きな理由です。
これに対して、橋本昌知事は復興基金設立に意欲を示しました。知事は地方六団体などが復興基金を被災県ごとに早期に創設するよう国に求めている経緯を招介し、財政的支援について「強く要望していく」と述べました。
橋本知事は「支援法の大きな課題」とし、救済の対象になるない被災者には「大変大きな負担がある」と理解を示し、阪神大震災や新潟県中越地震では「国の交付税に裏打ちされた復興基金が生活の再建に大いに役立った」と述べました。
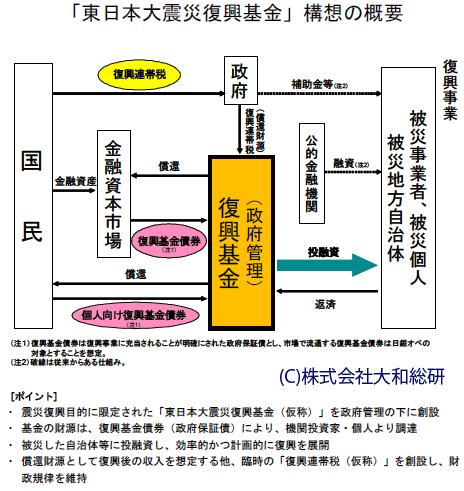
阪神大震災では8800億円の復興基金が立ち上がり、運用益など3600億円以上が、自立支援金、住宅ローンや中小企業融資の利子補給などに使われました。
東日本大震災では、大和総研が「未曾有の大震災からの復興へ“復興基金”と“復興連帯税”の創設」をとの提言を発表しています。地方の復興のキーポイントは、どのような形で「震災復興基金」を立ち上げるかに掛かっていると言っても過言ではありません。



