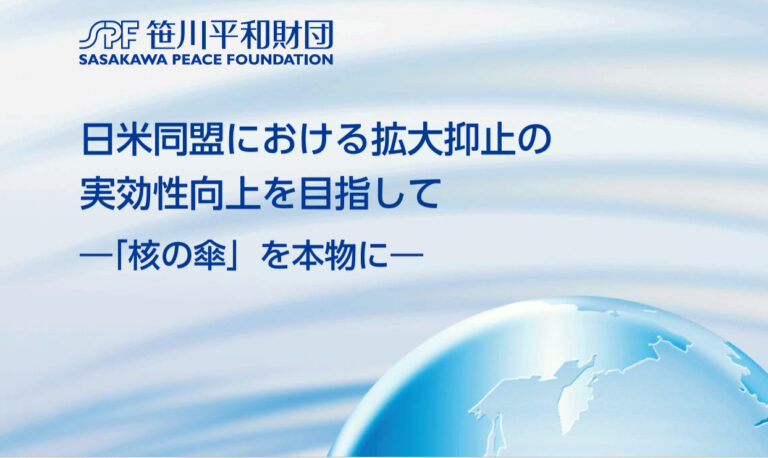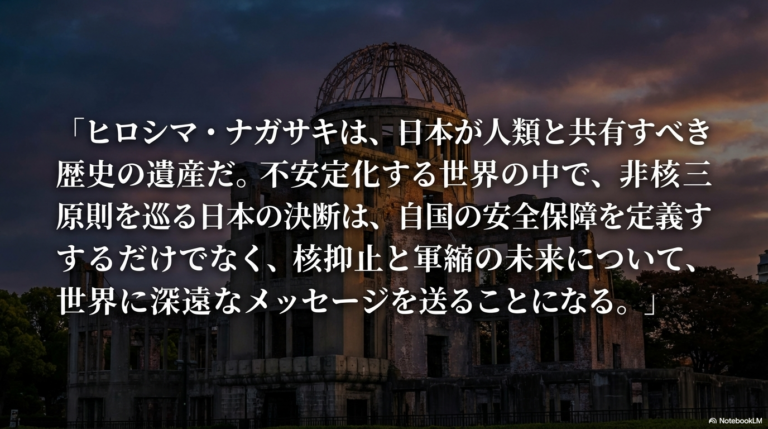6月10日、井手よしひろ県議は、JR常陸多賀駅前で行こなった県議会報告で、県議会6月定例議会の一般質間の内容などについて報告しました。あわせて、国会における「平和安全法制」の関連法案審議についての見解を述べました。
6月10日、井手よしひろ県議は、JR常陸多賀駅前で行こなった県議会報告で、県議会6月定例議会の一般質間の内容などについて報告しました。あわせて、国会における「平和安全法制」の関連法案審議についての見解を述べました。
6月4日の衆院憲法審査会の参考人質疑で、憲法学者が「これまでの政府の憲法解釈を超えている」などと発言。関連法案を「違憲」であると述べました。これを受けて野党は一勢に、法案に対する対決姿勢を強めています。
こうした憲法学者の意見は、今回始めて提示されたものではありません。憲法学者の意見は真摯に受けとめた上で、国や政府が国民の生命と国土を守る責務を負っていることは否定できない事実あることを再確認すべきです。
私たち公明党は、憲法9条を断固守る立場です。国際間の紛争解決に武力を使用することは認めません。他国を攻撃するための軍隊は持ちません。しかし一方、憲法13条には、国民の幸福追求権が認められ、国民を守る義務が政府には課せられています。
この憲法9条と13条をどのようにバランスを取って、国民を守っていくか、これが平和安全法制の”肝”なのです。
自衛権について、政府や自民党の一部には、他国の防衛を目的とした国際法上の集団的自衛権の行使を認めるべきだとの考えもありました。しかし、これでは憲法解釈の枠を超えてしまいます。
そこで、公明党が憲法の番人ともいわれる内閣法制局などの意見を充実に尊重して、1年半にわたる与党協議を通じて「日本の自衛のための武力行使に限る」という制約を強く主張し、実現させました。今回の平和安全法制関連法には、この方針に基づいた「新3要件」など二重、三重の歯止めが設けられたのです。
公明党が与党協議などで実現させた制約が、平和安全法制の法体系をバランスの良いものにしました。この平和安全法制は憲法解釈の枠を超えるものではありません。今後、仮に司法の判断を受ける機会があったとしても、充分にそれにたえられるものであると確信します。
こうした公明党の役割は、本来野党第一党の民主党がやるべき仕事です。健全野党とは、ただ「反対」するだけではなく、「あるべき国の姿を示すための健全な批判者」としての役割が求められます。民主党には、それができていません。公明党は与党内の健全な批判者として、その責任を果たしてきました。
自衛隊の活動について、「ある」「なし」を論じることは全く意味がありません、大事なことは、リスクを減らすために、いかに効果的な措置を十分に講ずることができるかです。そのために行動基準を見直すこと、マニュアルを改定して訓練を行い、現地の情報を十分に得る手段を設け、指揮者が適切な判断をし、派遣される隊員が高い士気の下で任務を遂行できる。こうした体制を作ることが肝心なのです。
これらのことを考えると、特措法に代わって恒久法である「国際平和支援法」を制定することは、常に自衛隊のリスク軽減のために準備できるという点で、大きなメリットがあります。
野党はリスクを減らすために、これから何をどうするかという視点で議論すべきです。
共産党のように「米軍の戦闘に巻き込まれる」という批判を繰り返すことも不見識です。自衛隊による他国軍隊への支援活動は、現に戦闘が行われている現場では行わないことになっており、「血で血を洗う」と、いたずらに国民の不安を煽るだけの”ため”にする議論にすぎません。