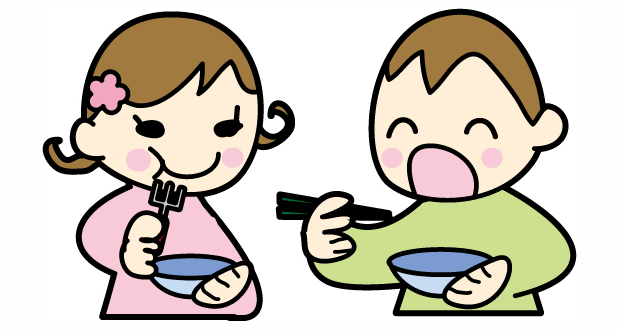
日本では2014年に、子どもの貧困率が16.3%に達し、実に6人に1人が貧困状態にあることが発表されました。今年2月に公表された東京都の調査によっても、全体のおよそ20%が『生活困難層』にあたることがわかりました。(“子どもの貧困”にあたる家庭が約20%に:東京都が実態調査http://blog.hitachi-net.jp/archives/51650376.html)
こうした状況に対して、国は「子どもの貧困対策連関連法」を制定して、子どもの貧困対策に本腰を入れています。と同時に、子どもが一人でも安心して利用できる「子ども食堂」をつくる動きが広がっています。子ども食堂が広がり、注目を浴びる背景は、“食”という人間の基本的な行為を通じて、社会に置かれた子どもの状況を様々な視点から確認できるというメリットがあるからです。
子ども食堂は、単に貧困家庭の子ども対象にしているものではありません。もちろん、金銭的に困窮して食べ物に窮している子供に食を提供しようという目的はあります。しかし、その多くはお金はあっても一緒に食べる人がいない「孤食」、いつも同じものしか食べない、偏食が多いなどの「個食」や「固食」などに対応しています。
単に食堂だけの機能ではなく、学童保育や無料塾などと連係して学習支援の機能をもった子ども食堂もあります。高齢者や障がい者と子どもとの交流の場を提供している食堂もあります。ども食堂に参加する子ども達と運営する大人やボランティアと交流によって、児童虐待やより深刻な貧困の実態などが明らかになる場合もあります。
現在展開されいる子ども食堂には5つのパターンがあるといわれています。一つは対象が子どもだけか大人もいっしょに参加するのか、二つ目は貧困の子どもたちだけに限るのか、三つ目は会員制にするのか誰でも来て良いとするのか、四つ目は純粋に食事だけの提供とするのか学習支援や自立支援なども一緒に提供するか、五つ目は安い料金(100~300円)を徴収するか無料で提供するかなどの形態の違いがあります。
運営主体も、行政または社会福祉協議会など行政に関わりの深い団体が行うケースや、行政から助成を受けてボランテアやNPO、地域コミュニティが運営するケース、
行政とは一線を画し民間団体が独自に行うケース、企業や農協、生協大学などが地域連係・地域貢献活動として行うケースがあります。
子ども食堂の多くは、現在月1回開催している事例が多いようですが、つくば市内のNPOは週2回精力的に開催しています。
このように子ども食堂は多種多様な形態があり、これが理想形であるという結論はだせません。
日立市では新年度より行政が補助金、南部と北部の2か所に子ども食堂開設
井手よしひろ県議の地元、日立市では社会福祉協議会と地域のボランティアとが協力して、昨年秋から北部の十王地区に子ども食堂がオープンしました。月一回開催し、毎回20人前後の子どもたちとボランティアが参加しています。料金は一回300円です。
日立市では、来年度予算42万円を計上して、子ども食堂事業を支援することになりました。 会場を南部地域にもう一か所追加し、2会場で実施します。運営主体は地域の
ボランティア、NPO団体に移行します。放課後児童クラブなどとの連携を視野に入れて、会場や時間帯を検討する考えです。また、経済的に困窮する子ども達に、安心して参加してもらえるように、民生員の協力を得て生活保護世帯に事前に食券を配布することなどを検討しています。
地域で子ども中心に、 行政、民間団体、地域コミュニティ、学校などが、子ども食堂という舞台で繋がることが重要です。
また、この子でも食堂について、北海道大学の吉田徹教授の言葉は説得力があります。吉田教授は、昨年(2016年)4月、札幌市にオープンした子ども食堂「Kaokao(かおかお)」の運営に携わっています。
私が子ども食室をやっている理由の一つは、子どものときに社会や親以外の大人たちが「自分のことをケアしてくれる」「自分のためにご飯を作ってくれる」という経験があるかないかで、子どもの社会に対するイメージが大きく変わってくるのではないかと思うからです。社会がちゃんと気にも掛けていることを子どもたちが感じることができ
れば、彼らが大人になったときに、社会のことを考えて恩返しをしようと思うかもしれない。そういう好循環がつくれれば、日本の未来は明るくなる」はずです。「生活者優先」と「シェア」つまり支え合いの仕組みをつくることが基本的な戦用各でしょう。それをしないと、日本の将来はどんどん貧しいものになっていきます。
(月刊公明2017年2月号より引用)



