5月26日、井手よしひろ県議が所属する県議会総務企画委員会では、茨城県のおけるIT施策の現状と課題を調査する目的で、参考人聴取を行いました。
午前中、青山学院大学大学教授の松尾明先生より「ITの最新動向と公共サービスへの利活用例<2006年新たなIT戦略が始まる>」とのテーマで、ご意見をお聞きしました。
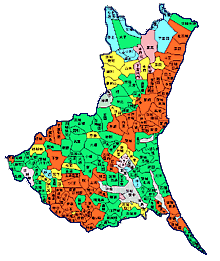 松尾教授は、「日本のIT投資はさまざまな批判も浴びながらも、2006年から新たなステージに突入した。昨年までの第1ステージで、インターネットの通信基盤は世界のトップクラスに立った。しかし、そのコンテンツについては、国民に恩恵を及ぼすまでには至っていない」「2010年までの第2ステージで、すべての国民がブロードバンドにアクセスできる環境を作る。また、構造改革や利用者・生活者の利便性の向上、国際貢献や国際競争力の強化に役立つシステムの構築に力点を置く」などと語り、国のIT戦略の概要を説明しました。具体的な説明の中では、医療現場でのレセプトの100%オンライン化、源泉徴収情報のオンライン申請などを実用化しオンライン申請の50%達成、遅れている高度なIT人材の育成などが課題となっていることが、重点的に説明されました。
松尾教授は、「日本のIT投資はさまざまな批判も浴びながらも、2006年から新たなステージに突入した。昨年までの第1ステージで、インターネットの通信基盤は世界のトップクラスに立った。しかし、そのコンテンツについては、国民に恩恵を及ぼすまでには至っていない」「2010年までの第2ステージで、すべての国民がブロードバンドにアクセスできる環境を作る。また、構造改革や利用者・生活者の利便性の向上、国際貢献や国際競争力の強化に役立つシステムの構築に力点を置く」などと語り、国のIT戦略の概要を説明しました。具体的な説明の中では、医療現場でのレセプトの100%オンライン化、源泉徴収情報のオンライン申請などを実用化しオンライン申請の50%達成、遅れている高度なIT人材の育成などが課題となっていることが、重点的に説明されました。
説明聴取後の意見交換では、IT化の進展と法整備の問題やWEB2.0の流れと公共機関のシステム整備の考え方などの議論が交わされました。
松尾教授は、「IT化の進展の中では、自分の情報を守るのは自己責任が原則であり、あまり大きな期待を国や公的なものに望むべきではないと考える。日本の警察のインターネット上の捜査能力は、世界的に見ても決して低いものではない。しかし、こうしたものに過度の期待を寄せることは慎むべきである」「WEB2.0の考え方では、あちら側とこちら側といったことがよくいわれる。行政は自らの手元に住民情報を置きたがるが、一番確実に情報を守るためには、しっかりとセキュリティが管理されたサーバーに置くほうが安全であり、発想の転換が今後必要になる。また、システムの開発や保守費用は非常に安価になる」といった見解をしめしました。
(イラストは「いばらきブロードバンドマップへのリンク」です)
5月26日に行われた総務企画委員会の参考人聴取では、午後からNTT東日本茨城支店の桐山学支店長より意見を伺いました。
最初に、桐山支店長は、茨城県内のブロードバンド環境について報告しました。それによると、茨城県のブロードバンド普及率は、39.2%で全国23位。契約件数は40万9000回線で全国13位。その内訳は、光ファイバー(FTTH):4万件(全国19位)、ADSL:33万5000件、CATV:3万2000件となっています。NTT東日本としては、今年度(平成18年3月末)世帯普及比率45%を、平成19年3月までに62%に引き上げる意向を示しました。
その上で、ブロードバンド格差を是正する手法として、IRU制度、助成金制度、県市町村事業の活用の3点を上げ説明しました。
- IRU制度:地方自治体が設備を整備しNTTなどの通信事業者が、その設備の貸与を受ける制度(秋田矢島町などの事例)
- 助成金制度:自治体が独自で整備し、通信事業者が協力する(神奈川県清川村などの事例)
- 県市町村の整備事業:ブロードバンド化の要望が強い工業団地を対象に、県のブロードバンド幹線を無料開放し、市町村とともに通信事業者に費用を助成する(茨城県商工労働部の事例)
●このブログに掲載させていただいたイラストは、「いばらきブロードバンドマップ」様のスクリーンショットを使用させていただいています。県内のブロードバンド環境が非常にわかりやすく整理掲載されています。是非、ご一読下さい。



