都道府県横断型の検索システムが必要
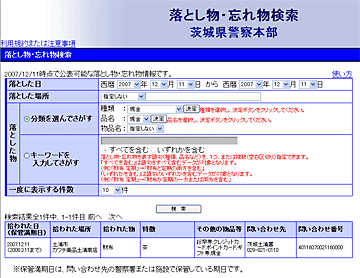 12月10日、茨城県警察本部は、改正遺失物法に伴い、県内各警察署に届けられた落とし物の情報をインターネット上で公開する「落とし物検索サービス」の運用をスタートさせました。
12月10日、茨城県警察本部は、改正遺失物法に伴い、県内各警察署に届けられた落とし物の情報をインターネット上で公開する「落とし物検索サービス」の運用をスタートさせました。
47都道府県の警察でも同じサービスが一斉にスタートし、県内だけでなく全国の落とし物の情報を閲覧することができるようになりました。
遺失物を取り扱う県警会計課によると、2006年の県内の落とし物は、金銭が6億5499万円余り。物品が17万6448点となっています。落とし物が持ち主に戻った割合(返還率)は金銭が65.4%、物品が50.2%となっています。
落とし物が交番や警察署に届けられると、警察署ごとに端末に登録され、県警本部会計課に集約されます。集まった情報は県警のインターネットホームページの「落とし物の取り扱いについて」のコーナーで公開されます。
警察庁のホームぺージには、全国の警察本部の落とし物検索のリンク集が掲載され、他県の落とし物も検索できるようになっています。
検索のページでは、遺失物、色、中身、拾得日時、場所、問い合わせ先の警察署などの情報を閲覧することができます。この情報は、土曜、日曜、祝日を除き毎日更新されます。保管期間の3カ月を過ぎれば情報は消去されます。また、12月9日以前のデータは収録されていません。
この落とし物のインターネットによる検索システムは、大変便利な仕組みです。ただし、折角インターネット上でのシステムを構築したのであれば、都道府県横断型のシステムを目指すべきだと考えます。人々の活動が都道府県の枠を越えて大きく広がっています。例えば、東京に通勤する人にとって、財布を落としてしまった場合は、茨城県と東京都、そして沿線の千葉や埼玉の県警のホームページを検索する必要があります。都道府県の横断検索によって、利便性の向上を図る必要があります。
 参考:茨城県警察本部「落とし物検索サービス」
参考:茨城県警察本部「落とし物検索サービス」
迷い犬、ねこなどのペットの取り扱いも変化
改正前の遺失物法によれば、迷い犬やねこ、その他のペットが保護され警察に届けられた場合、2週間各警察署に保管され、その後、動物愛護法により処分されることになっていました。改正遺失物法では、こうしたペットを遺失物の範囲から除外したため、ただちに動物愛護法による対応がとられることになります。処分に至る期間が、大幅に短くなることが懸念されます。
動物愛護行政を担当する県、市町村の役割が重くなり、迷い犬、ねこなどの対応をより充実させる必要があります。



