救急隊員が、患者の受け入れを各病院に要請し、受け入れが認められるまでの回数を調査した総務省消防庁によって取りまとめられました。その結果、4回以上受け入の紹介を行った回数は、茨城県は459件に上り、その件数比で全国ワースト9位であることが分かりました。
全国的にみた場合、東京都が4769件と3分の1を占めるなど、救急体制の不備が改めて明確になりました。
医療機関に10回以上断られた例があったのは、茨城を含む22都府県。茨城県は14件ありました。最大で15回断られた事例がありました。 妊婦の搬送を巡っても県内の厳しい実態が浮き彫り、13回断られたケースがあったほか、3回以上断られたケースも35件に上っています。
受け入れを断った理由は、処置困難(31.5%)、ベット満床(23.8%)、手術中・患者対応中(17.7%)などとなっています。
こうした救急医療の現状を改善するために、茨城県では救急医療情報システムの更新が、平成20年度予算化されました。各病院の空床情報などをリアルタイムで更新されるシステム作りを検討します。
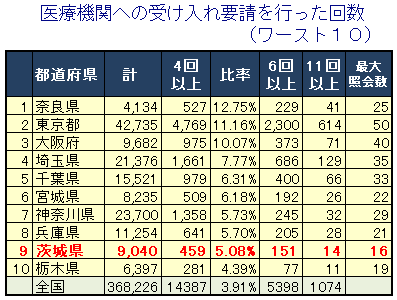
 参考:救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査の結果について
参考:救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査の結果について
重症救急「拒否」14件、10回以上の事例 茨城県、全国ワースト9位
読売新聞(200/3/12)
県内で昨年1年間に救急搬送された重症以上の傷病者(転院搬送を除く)約9500人のうち、医療機関に10回以上受け入れを断られたケースが14件あったことが、総務省消防庁が3月11日に公表した全国実態調査の結果でわかった。兵庫(28件)、宮城(26件)に次ぐワースト9位で、県内の救急搬送態勢が十分でない実態を裏付ける結果となった。
最高で15回受け入れを断られたケースがあったほか、受け入れを3回以上断られる割合は5・1%(459件)に達し、全国平均(3・9%)を上回る結果になった。
受け入れ先が決まって搬送を始めるまでに30分以上かかったケースは313件に上った。1時間以上が15件、1時間30分以上が7件で、2時間30分以上かかったケースも1件あった。
医療機関が受け入れを拒んだ理由は「専門外」が25・4%で最も多く、次いで「(医師が)手術・診察中」が22・6%だった。
10回以上断られた例があったのは、茨城を含む22都府県。計1074件のうち、東京が614件と突出しているほか、埼玉129件、大阪71件など、首都圏や近畿圏で多発している。
妊婦の搬送を巡っても県内の厳しい実態が浮き彫りになった。受け入れを13回断られたケースがあったほか、3回以上断られたケースも35件に上った。
今回の実態調査は、救急患者が医療機関に受け入れを相次いで断られる、いわゆる「たらい回し」が社会問題化したことを受け、初めて実施された。
県消防防災課は「全国との比較で、受け入れ拒否が多いことが改めてわかった。今年度から救急医療態勢の強化を図っており、調査結果を今後の対策に反映させていきたい」としている。



