平成18年10月の自殺対策基本法の施行、自殺総合対策大綱の策定(平成19年6月)など、政府は自殺対策を進めていますが、国内の自殺者が年間3万人を超える事態はなかなか変わりません。最近では硫化水素による自殺が急増するなど、自殺対策を巡る状況は、より厳しさを増しています。
自殺者が減らない要因として、そもそも自殺の実態が解明されておらず、実態に即した対策が実行できてこなかったとの指摘があります。
そうした中、自殺問題に取り組む民間非営利団体(NPO)や精神科医、経済学者らによる民間の「自殺実態解析プロジェクトチーム」が自殺に至る過程や社会的要因などに関する初の「自殺実態白書」をまとめ、7月4日に岸田文雄内閣府特命担当相(当時)に提出しました。
その中でも注目したいのが、第1章の「自殺実態1000人調査」です。この調査は、正式名称を 「『1000人の声なき声』に耳を傾ける調査」といい、①自殺に至るまでのプロセスを明らかにすることで、具体的かつ実践的な自殺対策の立案・実施につなげること、②死から学ぶことで、同じような形で自殺に追い込まれていく人を一人でも減らすこと、を目的に行われました。実施機関は、NPO法人ライフリンクと東京大学経済学部SOSプロジェクトで、2007年7月~2008年6月まで行われました。現在305名に方からの聴取分が分析され公表されています。調査方法は、面接による聞き取り調査で、平均聞き取り時間は2時間30分となっています。
- 自殺の背景には様々な「危機要因」が潜んでいる(計68項目)
- 自殺時に抱えていた「危機要因」数は一人あたり平均4つ
- 「危機要因」全体のおよそ7割が上位10要因に集中
- 自殺の10大要因が連鎖しながら「自殺の危機経路」を形成
- 危機連鎖度が最も高いのが「うつ病→自殺」の経路
- 10大要因の中で自殺の「危機複合度」が最も高いのも「うつ病」
- 「危機の進行度」には3つの段階がある ~危機複合度を基準にして~
- 危機要因それぞれに「個別の危険性」がある
こうした分析をもとに、精神科医の島悟氏は、「うつ病などの心の病への適切な医療体制の確保は必要であることは論を待たないが、より早期の段階における医療以外の対策も同などに重要であると考えられる。何事も早期であるほどに効果的な対策が打てると考えられるし、時間的余裕もあろう。最終段階に近づけば近づくほど、余裕がなくなり、個別的対策を十分に検討する時間がなくなる。また早期対応は、より少ない費用で、より多くの効果が期待し得ることからも、早期の対策を充実化することが求められている」と記しています。
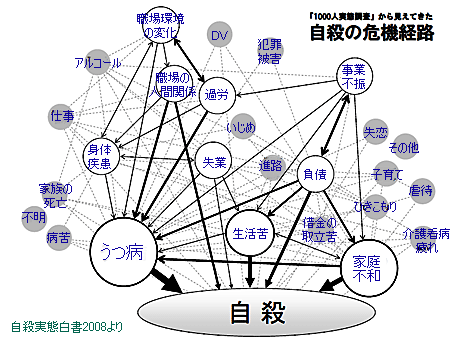
 参考:NPO自殺対策支援センター「ライフリンク」
参考:NPO自殺対策支援センター「ライフリンク」
 参考:平成19年中における自殺の概要資料[PDF](平成20年6月、警察庁生活安全局地域課)
参考:平成19年中における自殺の概要資料[PDF](平成20年6月、警察庁生活安全局地域課)




脳脊髄液減少症患者です。
脳脊髄液減少症と
自殺の因果関係について、
気づいている方はまだまだ少ないと思います。
どうか、このことに気づいていただきたいと思います。