自然エネルギーへの大規模投資で、金融危機、エネルギー不足、温暖化の“三つの危機”の克服を図る
世界的な経済危機の打開策として、各国政府は今、環境・エネルギー分野への巨額の集中投資と、それによる雇用の創出、いわゆるグリーン・ニューディールの実施にカジを切り始めました。
経済成長を支え、雇用を生み出すことが期待される再生可能エネルギーは、20世紀に自動車が果たした役割と同じものを21世紀に果たすといわれています。このため、各国は、低炭素社会インフラへの大規模な投資で、金融危機、エネルギー不足、温暖化の“三つの危機”の克服を図る考えです。
今後は、再生可能エネルギーのほかにも、断熱住宅投資や次世代自動車、送電ネットワークの更新などのインフラに対しての投資が期待されています。
アメリカ・オバマ新大統領への期待
今月就任する米・オバマ新大統領は、風力、太陽光、バイオマスなど再生可能エネルギーの開発・導入に、10年間で1500億ドルを投じ、500万人の新規雇用創出を公約しています。
オバマ氏の大統領選向けエネルギー政策では、2015年までに100万台のプラグイン・ハイブリッド車を走らせ、自然エネルギー電力を12年までに10%、25年までに25%を達成し、温室効果ガスを50年までに1990年比で80%削減することなどが盛り込まれました。
これまでは、環境への支出が経済成長を抑えるとの懸念から、温暖化問題に対する国際的な議論はなかなか進展が見られませんでした。
しかし、京都議定書を離脱し、温暖化対策に消極的だったブッシュ政権との違いが米国で示されたことで、いまや状況は一変しました。国連気候変動枠組み条約のデ・プア事務局長も、オバマ氏について「国際的なレベルでのリーダーシップに期待する」と表明しており、温暖化対策の実効ある前進に向けた機運は高まっています。
2020を掲げ先駆けるEU諸国
欧州連合(EU)も、昨年12月の首脳会議で、20年までに温室効果ガスの排出量を90年比最低20%削減する目標などを盛り込んだ包括的な気候 変動対策で最柊合意に達しました。
EUは各国に先駆け、20年までの中期目標を表明。EU議長国フランスのサルコジ大統領は記者会見で、「われわれが合意した規制のように拘束力のある規制を持っている大陸は他にない」「歴史的な合意だ」と断言しています。
EUの包括対策には、①再生可能エネルギーへの依存度を20年までに20%に高める(いわゆる2020政策)②運輸部門の燃料に占めるバイオ燃料の割合を10%に高める--などの目標が盛り込まれました。最近の急速な景気悪化で、「気候変動対策よりも経済対策を優先すべき」などの主張もみられたが、最終合意を得たことで気候変動問題に関して、EUは強い発言力を維持したといえます。
今、必要な日本版ニューディール政策
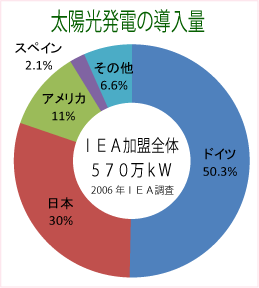 こうした世界的な潮流の中で、日本政府も、“日本版グリーン・ニューディール”を3月にもまとめる方針を固め、麻生太郎首相、斉藤鉄夫環境相は1月6日、構想の具体化に着手しました。
こうした世界的な潮流の中で、日本政府も、“日本版グリーン・ニューディール”を3月にもまとめる方針を固め、麻生太郎首相、斉藤鉄夫環境相は1月6日、構想の具体化に着手しました。
大枠では、15年までに環境ビジネス市場を06年の約1.4倍となる100兆円規模にし、雇用も80万人増の220万人の確保をめざす方針です。環境分野に投資する企業に対する無利子融資制度の創設のほか、省エネ家電や電気自動車など次世代自動車の購入を促す施策の拡充、省エネ住宅の新たな普及策などが想定されています。
すでに、政府として、05年以降ドイツに譲っている太陽光導入量世界一の座を奪還する姿勢を打ち出しており、経済産業省は先月、次世代のエネルギー、太陽電池を、自動車や電機のような基幹産業に育成することを目的とした「ソーラー・システム産業戦略研究会」を設置。基礎研究体制の整備や海外進出への課題などが検討され、2月にも報告書をまとめ、10年度から事業を具体化する予定です。
環境省は08年度、地球温暖化防止の観点から家庭用の太陽光発電の導入を支援する補助金制度を復活させ、09年度予算と合わせて13万5000世帯に補助するなど、国内の普及策は動き出しています。
環境技術で反転攻勢に出る日本企業
世界的な景気悪化で投資計画の中断や先送りばかりが目立つ中、一部企業は環境分野などで追加投資を断行します。「今投資をしなければ、景気が底打ったときにチャンスを逃す」(積水化学工業)と反転攻勢を意識したものです。不況期の“種まき”は、景気回復後には先行メリットでライバルに大きな優位に立つ可能性を秘めています。
旭化成は、高出力が特徴のリチウムイオン電池の材料を増産するため、守山工場(滋貿県守山市)と建設中の日向工場(宮崎県日向市)に計90億円を投資。三菱樹脂と三菱化学も同電池材料の生産を拡大します。また、東芝は新潟県柏崎市に新工場を建設し、10年秋に同電池の量産を始める計画です。
リチウムイオン電池は、パソコンなど向けに需要が伸びているほか、「ハイブリッド車への搭載をはじめ、新たな用途への採用も見込める」(三菱化)と有望視されています。電池に強みを持つ三洋電機の買収を決めたパナソニックも、1000億円の投資の相当部分を同分野の強化に充てる意向で、今後も新規投資が続きそうです。
海外では、シャープが1000億円を投じ、イタリアで太陽光発電事業に参入。積水化学はオランダ工場に100億円を投資し、自動車や建物のガラスに挟んで遮音・断熱性を高める「中間膜」の生産能力を引き上げます。
また、新日本製鉄グループで自動車部品向け線材を手掛ける鈴木金属工業は、欧州のライバル企業を90億円で買収します。鈴木金属の杉浦登社長は「この値段で買えるのはチャンス。円高が追い風になった」と語っています。輸出産業に打撃を与える円高も、海外でのM&A(企業の合併・買収)費用を抑える側面があります。
「これからの苦しい時期には成長路線の強化も面白い選択ではないか」(新日鉄の三村明夫会長)との見方もあり、今後も設備投資やM&Aといった前向きな動きが続けば、沈滞ムードが漂う日本経済の下支えにつながりそうです。
(このブログは公明新聞2009/1/9付け記事などを参考に編集しました)



