親が滞納でも医療を保障、4月からスタート
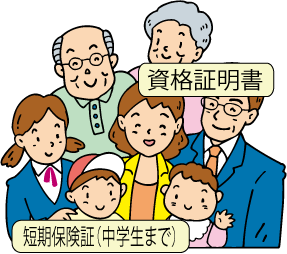 市区町村が運営する国民健康保険(国保)の制度で、医療機関の窓口で一度は医療費を全額自己負挺しなければならない資格証明書の交付世帯の子ども(いわゆる「無保険の子」)の医療を保障するため、国民健康保険法が改正され、今年(平成21年)4月1日から、資格証明書交付世帯であっても、中学生以下の子どもには短期保険証(6カ月)が交付されることになりました。
市区町村が運営する国民健康保険(国保)の制度で、医療機関の窓口で一度は医療費を全額自己負挺しなければならない資格証明書の交付世帯の子ども(いわゆる「無保険の子」)の医療を保障するため、国民健康保険法が改正され、今年(平成21年)4月1日から、資格証明書交付世帯であっても、中学生以下の子どもには短期保険証(6カ月)が交付されることになりました。
改正国民健康保険法は昨年12月の参院本会議で全会一致で可決、成立しています。
国保では、病気や失業などの特別な事情がある場合や支払い能力がない場合は、その生活状況に応じた納付相談(分割納付や徴収猶予)を行い、ケースによっては生活保護の申請を支援することになっています。保険料の減免・徴収猶予の要件は各市区町村が条例で定めています。
しかし、そうした事情がないにもかかわらず、世帯主が保険料を1年以上、滞納した場合には保険証と引き換えに資格証明書が交付され、世帯に属する家族全員が医療機関の窓口で医療費を全額自己負担(10割負担)しなくてはなりません。
もちろん、後に市区町村に申請すれば保険給付分(7割または8割)が払い戻されるものの、窓口での経済負担の大きさから受診抑制につながるという課題がありました。
特に子どもは保険料の滞納に関しては何の責任もないだけに、必要な医療は確保されなくてはならないとの考え方から、国保法を改正し、中学生以下の子どもには資格証明書を交付せず、6カ月の短期保険証を交付することになりました。
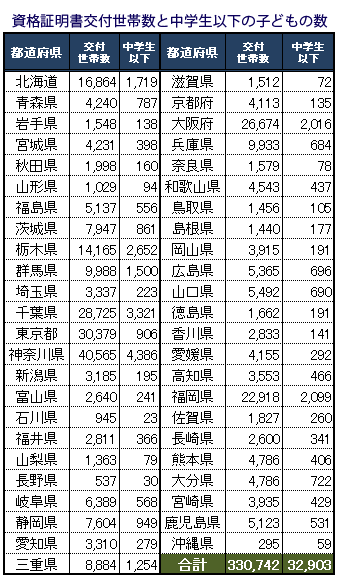 一方、低所得でも懸命に保険料を支払っている人との公平性や確信犯的な悪質な滞納者とのバランスも考慮しなくてはなりません。当初の民主党など野党3党案は、18歳未満を対象に短期でない通常の保険証を交付する内容でしたが、納付者との公平性を保つため、対象者を義務教育である中学生以下とし、保険証の有効期間を短窮(6カ月)とすることで与野党の修正協議が決着しました。
一方、低所得でも懸命に保険料を支払っている人との公平性や確信犯的な悪質な滞納者とのバランスも考慮しなくてはなりません。当初の民主党など野党3党案は、18歳未満を対象に短期でない通常の保険証を交付する内容でしたが、納付者との公平性を保つため、対象者を義務教育である中学生以下とし、保険証の有効期間を短窮(6カ月)とすることで与野党の修正協議が決着しました。
短期保険証の更新時は、保護者との間で納付相談が行われることが望まれます。そもそも滞納の状態かから、早期に脱却できるよう、世帯に抱える課題に光を当てて解決へとつなげていく機会を大切にする必要があるからです。 厚生労働省の調査(昨年9月15日現在)によると、資格証明書交付世帯の中学生以下の子どもの数は、国で3万2903人に上り、茨城県内でも2652人に上っています。



