県住宅公社 解散前倒し検討
茨城新聞(2009/09/17)
県、三セク債活用視野に
県議会の県出資団体等調査特別委員会(西條昌良委員長)が16日開かれ、債務超過に陥り県の支援を受けている県住宅供給公社の経営について議論した。県執行部が、国の「第三セクター等改革推進債(三セク債)」の活用を視野に、解散の前倒しを早急に検討するとし、これに対し複数の委員が、解散前倒しのシミュレーションを早期に示すよう求めた。
同公社は2005年度決算で約461億円の債務超過に陥り、県が06年度から10年間の改革工程に沿って、債務超過額の1割(約46億円)を毎年補助するなどの支援を実施。同公社は保有土地の早期処分を目指している。
しかし、大規模団地は現在218ヘクタールが未分譲。低価法の導入により昨年度決算で約67億円の損失を計上し、今後も土地の評価損の発生による損失が見込まれることなどから、解散前倒しの議論が浮上していた。
今後、県は、同公社が抱える特定優良賃貸住宅事業やケア付き高齢者賃貸住宅「サンテーヌ土浦」の譲渡などの課題解決に取り組みながら、県民負担を抑制する狙いで解散の前倒しについて検討するとしている。
三セク債は新設された制度。経営が悪化した公営企業や第三セクターの解散などの際、地方自治体が求められる一定の経費に三セク債を充て、原則10年間で償還する仕組み。同公社の場合、借入金のうち県が損失補償する部分などに活用が見込めるという。
9月16日、県議会出資団体調査特別委員会が開かれ、県住宅供給公社について、県は、自主解散か破産かいずれかの方法で、当初計画の2015年度より前倒しして解散する方針を明らかにしました。
国は2009年度から、地方自治体の出資団体などの清算を集中的に行うために「第三セクター等改革推進債(三セク債)」を創設しました。県ではこの三セク債を活用して、県住宅供給公社を前倒しで清算することを検討することを明らかにしました。
県住宅供給公社は、2005年度決算で約461億円の債務超過に陥り、県が2006年度から10年間の改革工程表に沿って、債務超過額の1割(約46億円)を毎年補助するなどの支援を実施しています。
しかし、大規模団地は現在218ヘクタールが、事業が凍結されています。さらに分譲中の団地も残戸数126件に対して、今年分譲が出来たのはわずか2戸のみです。
こうした売れ残った土地は、2008年度から資産の評価法が低価法に変更されたために、2008年度決算で約67億円の損失を計上しました。今後も土地の評価損の発生による損失が増えることが見込まれることなどから、三セク債を活用した解散前倒しの議論が具体化しました。
三セク債を活用した場合、解散以降は公社の人件費や運営費の軽減が図れる(約10億円程度)ことや、利子の一部について国の特別交付金が受けられるなどのメリットがあります。
現在、県住宅供給公社の負債額は、民間金融機関からの146億円(県が債務保証しています)、県から公社への貸付金355億円、さらに、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)からの借入金が104億円、国からの借り入れが10億円、合計620億円に上っています。
この内、県の貸付金と債務保証分の501億円が三セク債の対象となります。県は三セク債を発行することで、501億円プラス金利を10年にわたって、返済していくことになります。
住宅金融支援機構からの借入金は、現在、簿価で140億円ある所有する土地を処分して清算することになります。
特別委員会では、特定調停などの自主的な清算を行うのか、破産によって清算するのかなど、早急に県民への影響が少ない手法や時期を検討することになりました。
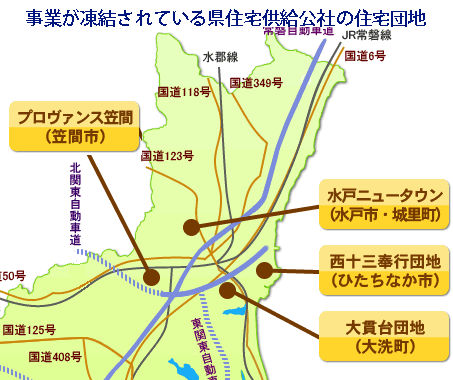
第3セクター等改革推進債の概要と留意点について
大阪府総務部市町村課財政グループ(自治大阪2009-6)
大阪府総務部市町村課財政グループ(自治大阪2009-6)
1.第三セクター等改革推進債(以下「三セク債」という。)をめぐる経緯
第三セクター、地方公社及び公営企業(以下「第三セクター等」という。)については、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)の施行を踏まえ、早期に抜本的改革に取り組み、将来的な財政負担の明確化と計画的な削減に取り組むことが求められているところです。
このため、「経済財政改革の基本方針2008」(平成20年6月27日閣議決定)、「債務調整等に関する調査研究会」の議論等を踏まえ、「第三セクター等の改革について」(平成20年6月30日付け総財公第112号)において地方公共団体による存廃を含めた第三セクター等の抜本的改革を集中的に推進することとされました。これに伴い、第三セクター等の整理又は再生に伴う債務処理を円滑に実施することができるよう、地方財政法の一部改正(平成21年4月1日施行)により、三セク債を発行できるようにしたものです。
なお、これは平成21年度から平成25年度までの時限措置となっています。
2.三セク債の概要
三セク債は、上記改正により新たに設けられた地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「地財法」という。)第33条の5の7を根拠としています。
すなわち、①公営企業の廃止、②土地開発公社の解散又は業務の一部の廃止、③損失補償を行っている法人等の解散又は事業の再生に取り組む地方公共団体において、当該取組が当該地方公共団体の将来の財政の健全な運営に資すると認められる場合に、発行することができると定められています。(第1項)
①公営企業の廃止とは、当該地方公共団体、地方公共団体の組合又は地方開発事業団が当該公営企業に係る事業を行わないこととして当該公営企業に係る特別会計を廃止することを示します。公営企業の廃止に要する経費に係る三セク債の発行可能額は、地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号。以下「省令」という。)附則第2条の3各号に規定する経費の額の合算額から当該公営企業の資産の処分による収入をもって充てることができると見込まれる額を控除した額です。
②土地開発公社が行う業務の一部の廃止とは、当該公社の定款の変更により明らかにされるもので、原則として、土地の再取得又は売却等の処分により、当該業務に係る借入金が確実に返済されると見込まれるもの以外のすべての業務を廃止することを示します。土地開発公社の解散又は業務の一部の廃止に要する経費に係る三セク債の発行可能額は、省令附則第2条の5各号に規定する経費の額の合算額から当該公社の解散又は業務の一部廃止の際に公社の資産の処分による収入をもって充てることができると見込まれる額を控除した額です。
③損失補償を行っている法人等の解散又は事業の再生については、地方公共団体が締結している損失補償に係る契約に基づき負担する必要がある額が対象となります。ただし、地方公共団体が、平成21年度以降に損失補償を行っている法人等の損失補償の額を増額し、又は貸付金の増額を行った場合には、当該増額された部分については、原則として、三セク債の発行は認められません。
三セク債発行にあたっては、都道府県及び政令指定都市は総務大臣の、市町村は都道府県知事の許可が必要です。(第2項)
また、償還期限については、対象となる事業の性質、三セク債を発行することによる当該地方公共団体の財政の健全化の効果、将来の見通し及び財政規模等を総合的に勘案して必要な最小限の期間とすることとし、10年以内を基本としますが、必要に応じ10年を超える償還年限を設定することができるものとされています。
資金は、原則民間等資金(市場公募資金及び銀行等引受資金)とされ、充当率は原則100%となっていますが、据置期間については合理的な理由がない場合は据置期間を設けないこととなっているところです。
3.三セク債の活用について
第三セクター等の抜本的改革に取り組むにあたっては、それぞれ以下のような課題が考えられます。
(1)公営企業
公営企業は、一般会計との適切な負担区分を前提としつつ、独立採算制を原則として経営されています。しかしながら、たとえ公営企業が区分されているといっても、あくまでも地方公共団体の一部であり、公営企業が抱える債務も地方公共団体の債務の一部であることに違いはありません。
こうした公営企業のうち、経営状況が思わしくなく、今後も改善の見込みが少ない状態に置かれているものについては、将来的に長期に渡り地方公共団体の財政に負担を強いる恐れがあり、存廃を含めた抜本的な改革を行う必要があるものもあります。
このような問題を有する公営企業については、事業の廃止や地方独立法人への移行などの改革方策が考えられますが、いずれの場合であっても、特別会計を廃止するにあたって多額の解消すべき負債が生じる可能性があり、その処理が財政的課題として生じることになります。
(2)土地開発公社
土地開発公社の経営健全化対策については、これまで国において平成12年度及び平成16年度の二度にわたり策定され、同対策に基づき公社経営健全化団体として指定を受けた団体は、土地開発公社経営健全化計画(以下「健全化計画」という。)に基づき保有量を削減する取組を行ってきたところです。
第二次土地開発公社経営健全化対策に基づく指定を受けた団体数は、大阪府内(大阪市・堺市除く。以下同じ)で既に計画を達成した団体を含めて24団体に上ります。これらの団体は、健全化計画に基づき、平成17年度から19年度の3年間で債務保証等対象土地の保有量を約460億円削減するなど、一定の成果を挙げてきたところです。
健全化計画に基づいて行われる取組に対しては、供用済土地の再取得や有効利用を目的とした土地の取得に係る地方債措置が講じられているところですが、この措置は健全化計画に基づいた取組を行っている間に限られており、同計画期間の終了後は、このような措置なしで健全化を進めなければなりません。また、処分に長期間を要する土地を多く保有する公社については、地方公共団体の財政にも長期にわたって影響を及ぼすことになります。
さらに、地方公共団体が公社の借入金に対して債務保証を行っている場合は、公社の解散等によって一時的に多額の財政負担が生じる可能性があります。
(3)第三セクター
第三セクターについては、平成11年に自治省が定めた「第三セクターに関する指針」において、累積赤字等で経営が苦しい第三セクターについて、地方公共団体は運営改善や統廃合等に積極的に取り組むことが求められました。
その後、平成15年に指針の一部改正が行われ、平成20年には総務省により第三セクター等の改革についてのガイドラインが策定されました。
この間、指定管理者制度の導入や公益法人制度改革等、第三セクターをとりまく状況が変化していく一方、経営が著しく悪化した第三セクターについては、存廃も含めた抜本的な経営改善策が求められるようになりました。
しかし、第三セクターの資金調達にあたり損失補償を行った地方公共団体にとっては、第三セクターを清算する場合、損失補償によって一時的に生じる多額の財政負担への対応が困難であることから、抜本的な対策を先延ばしにせざるを得ない状況に陥ることが考えられます。
これらの課題については、三セク債を活用することにより、一定の対策が可能となると考えられます。
一方で、三セク債の起債の許可の申請にあたっては、起債に係る予算案とは別に、三セク債を発行することについてあらかじめ議会の議決が必要であると地財法で定められています(第3項)。これは、地方公共団体に対して、第三セクター等の抜本的改革にあたって、それらが実施している事業の意義、採算性、事業手法の選択等を可能な限り広範かつ客観的に検討し、現状に至った経緯及びその責任を明らかにすると共に、処理方針が最善のものであることについて議会・住民に対し説明していくことが求められているからです。(「第三セクター、地方公社及び公営企業の抜本的改革の推進に関する報告書」平成20年12月5日債務調整等に関する調査研究会を参照)
第三セクター等の抜本的改革を推進する地方公共団体においては、すでにこれらの取組を進めている団体もあるかと思いますが、初めから三セク債の活用ありきではなく、その活用を決めるに至った経緯及びその理由、財政健全化の効果、健全化法の指標の将来見通しなどについて、広く情報を公開し、議会・住民の理解を得ることが重要です。
4.最後に
府内市町村では、公営企業・第三セクターにおいて、経営の深刻化しているものや事業の存続が困難と思われるものが存在します。
また、土地開発公社においては、第二次健全化計画終了後も、相当数の長期保有地を抱える見込みです。
健全化法の施行により、健全化判断比率・資金不足比率が毎年公表されるようになったことから、経営の厳しい第三セクター等を抱える地方公共団体は、その実態がより明確に開示されるようになりました。
三セク債の発行は、地方公共団体に第三セクター等の集中的な抜本的改革を促すため、平成25年度までの5年間の時限措置となっています。
第三セクター等に課題を抱える市町村は、三セク債の活用による将来の財政負担への対応策にも留意しつつ、この機会に第三セクター等の抜本的改革に取り組むことが必要です。
第三セクター、地方公社及び公営企業(以下「第三セクター等」という。)については、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)の施行を踏まえ、早期に抜本的改革に取り組み、将来的な財政負担の明確化と計画的な削減に取り組むことが求められているところです。
このため、「経済財政改革の基本方針2008」(平成20年6月27日閣議決定)、「債務調整等に関する調査研究会」の議論等を踏まえ、「第三セクター等の改革について」(平成20年6月30日付け総財公第112号)において地方公共団体による存廃を含めた第三セクター等の抜本的改革を集中的に推進することとされました。これに伴い、第三セクター等の整理又は再生に伴う債務処理を円滑に実施することができるよう、地方財政法の一部改正(平成21年4月1日施行)により、三セク債を発行できるようにしたものです。
なお、これは平成21年度から平成25年度までの時限措置となっています。
2.三セク債の概要
三セク債は、上記改正により新たに設けられた地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「地財法」という。)第33条の5の7を根拠としています。
すなわち、①公営企業の廃止、②土地開発公社の解散又は業務の一部の廃止、③損失補償を行っている法人等の解散又は事業の再生に取り組む地方公共団体において、当該取組が当該地方公共団体の将来の財政の健全な運営に資すると認められる場合に、発行することができると定められています。(第1項)
①公営企業の廃止とは、当該地方公共団体、地方公共団体の組合又は地方開発事業団が当該公営企業に係る事業を行わないこととして当該公営企業に係る特別会計を廃止することを示します。公営企業の廃止に要する経費に係る三セク債の発行可能額は、地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号。以下「省令」という。)附則第2条の3各号に規定する経費の額の合算額から当該公営企業の資産の処分による収入をもって充てることができると見込まれる額を控除した額です。
②土地開発公社が行う業務の一部の廃止とは、当該公社の定款の変更により明らかにされるもので、原則として、土地の再取得又は売却等の処分により、当該業務に係る借入金が確実に返済されると見込まれるもの以外のすべての業務を廃止することを示します。土地開発公社の解散又は業務の一部の廃止に要する経費に係る三セク債の発行可能額は、省令附則第2条の5各号に規定する経費の額の合算額から当該公社の解散又は業務の一部廃止の際に公社の資産の処分による収入をもって充てることができると見込まれる額を控除した額です。
③損失補償を行っている法人等の解散又は事業の再生については、地方公共団体が締結している損失補償に係る契約に基づき負担する必要がある額が対象となります。ただし、地方公共団体が、平成21年度以降に損失補償を行っている法人等の損失補償の額を増額し、又は貸付金の増額を行った場合には、当該増額された部分については、原則として、三セク債の発行は認められません。
三セク債発行にあたっては、都道府県及び政令指定都市は総務大臣の、市町村は都道府県知事の許可が必要です。(第2項)
また、償還期限については、対象となる事業の性質、三セク債を発行することによる当該地方公共団体の財政の健全化の効果、将来の見通し及び財政規模等を総合的に勘案して必要な最小限の期間とすることとし、10年以内を基本としますが、必要に応じ10年を超える償還年限を設定することができるものとされています。
資金は、原則民間等資金(市場公募資金及び銀行等引受資金)とされ、充当率は原則100%となっていますが、据置期間については合理的な理由がない場合は据置期間を設けないこととなっているところです。
3.三セク債の活用について
第三セクター等の抜本的改革に取り組むにあたっては、それぞれ以下のような課題が考えられます。
(1)公営企業
公営企業は、一般会計との適切な負担区分を前提としつつ、独立採算制を原則として経営されています。しかしながら、たとえ公営企業が区分されているといっても、あくまでも地方公共団体の一部であり、公営企業が抱える債務も地方公共団体の債務の一部であることに違いはありません。
こうした公営企業のうち、経営状況が思わしくなく、今後も改善の見込みが少ない状態に置かれているものについては、将来的に長期に渡り地方公共団体の財政に負担を強いる恐れがあり、存廃を含めた抜本的な改革を行う必要があるものもあります。
このような問題を有する公営企業については、事業の廃止や地方独立法人への移行などの改革方策が考えられますが、いずれの場合であっても、特別会計を廃止するにあたって多額の解消すべき負債が生じる可能性があり、その処理が財政的課題として生じることになります。
(2)土地開発公社
土地開発公社の経営健全化対策については、これまで国において平成12年度及び平成16年度の二度にわたり策定され、同対策に基づき公社経営健全化団体として指定を受けた団体は、土地開発公社経営健全化計画(以下「健全化計画」という。)に基づき保有量を削減する取組を行ってきたところです。
第二次土地開発公社経営健全化対策に基づく指定を受けた団体数は、大阪府内(大阪市・堺市除く。以下同じ)で既に計画を達成した団体を含めて24団体に上ります。これらの団体は、健全化計画に基づき、平成17年度から19年度の3年間で債務保証等対象土地の保有量を約460億円削減するなど、一定の成果を挙げてきたところです。
健全化計画に基づいて行われる取組に対しては、供用済土地の再取得や有効利用を目的とした土地の取得に係る地方債措置が講じられているところですが、この措置は健全化計画に基づいた取組を行っている間に限られており、同計画期間の終了後は、このような措置なしで健全化を進めなければなりません。また、処分に長期間を要する土地を多く保有する公社については、地方公共団体の財政にも長期にわたって影響を及ぼすことになります。
さらに、地方公共団体が公社の借入金に対して債務保証を行っている場合は、公社の解散等によって一時的に多額の財政負担が生じる可能性があります。
(3)第三セクター
第三セクターについては、平成11年に自治省が定めた「第三セクターに関する指針」において、累積赤字等で経営が苦しい第三セクターについて、地方公共団体は運営改善や統廃合等に積極的に取り組むことが求められました。
その後、平成15年に指針の一部改正が行われ、平成20年には総務省により第三セクター等の改革についてのガイドラインが策定されました。
この間、指定管理者制度の導入や公益法人制度改革等、第三セクターをとりまく状況が変化していく一方、経営が著しく悪化した第三セクターについては、存廃も含めた抜本的な経営改善策が求められるようになりました。
しかし、第三セクターの資金調達にあたり損失補償を行った地方公共団体にとっては、第三セクターを清算する場合、損失補償によって一時的に生じる多額の財政負担への対応が困難であることから、抜本的な対策を先延ばしにせざるを得ない状況に陥ることが考えられます。
これらの課題については、三セク債を活用することにより、一定の対策が可能となると考えられます。
一方で、三セク債の起債の許可の申請にあたっては、起債に係る予算案とは別に、三セク債を発行することについてあらかじめ議会の議決が必要であると地財法で定められています(第3項)。これは、地方公共団体に対して、第三セクター等の抜本的改革にあたって、それらが実施している事業の意義、採算性、事業手法の選択等を可能な限り広範かつ客観的に検討し、現状に至った経緯及びその責任を明らかにすると共に、処理方針が最善のものであることについて議会・住民に対し説明していくことが求められているからです。(「第三セクター、地方公社及び公営企業の抜本的改革の推進に関する報告書」平成20年12月5日債務調整等に関する調査研究会を参照)
第三セクター等の抜本的改革を推進する地方公共団体においては、すでにこれらの取組を進めている団体もあるかと思いますが、初めから三セク債の活用ありきではなく、その活用を決めるに至った経緯及びその理由、財政健全化の効果、健全化法の指標の将来見通しなどについて、広く情報を公開し、議会・住民の理解を得ることが重要です。
4.最後に
府内市町村では、公営企業・第三セクターにおいて、経営の深刻化しているものや事業の存続が困難と思われるものが存在します。
また、土地開発公社においては、第二次健全化計画終了後も、相当数の長期保有地を抱える見込みです。
健全化法の施行により、健全化判断比率・資金不足比率が毎年公表されるようになったことから、経営の厳しい第三セクター等を抱える地方公共団体は、その実態がより明確に開示されるようになりました。
三セク債の発行は、地方公共団体に第三セクター等の集中的な抜本的改革を促すため、平成25年度までの5年間の時限措置となっています。
第三セクター等に課題を抱える市町村は、三セク債の活用による将来の財政負担への対応策にも留意しつつ、この機会に第三セクター等の抜本的改革に取り組むことが必要です。


