 2月5日、茨城県の橋本昌知事は定例の記者会見で、日立製作所日立総合病院(日製病院)の産科を4月から再開できるとの見通しを公表しました。井手よしひろ県議は、午後、県保健福祉部の担当者より、再開に向けての具体的な取り組みについてヒアリングを行いました。
2月5日、茨城県の橋本昌知事は定例の記者会見で、日立製作所日立総合病院(日製病院)の産科を4月から再開できるとの見通しを公表しました。井手よしひろ県議は、午後、県保健福祉部の担当者より、再開に向けての具体的な取り組みについてヒアリングを行いました。
それによると、日製病院は東京医科大学より3名の産科医の派遣を受け、4月から出産の体制を再開します。東京医科大は、原則3名のチーム体制で医師を派遣。チームのリーダークラスの医師、中堅の医師、若手の医師または後期研修医の3名で構成するシームで診療にあたります。
日立市は、東京医科大学に3年間にわたり5000万円の予算で“寄付講座”を開設することにしています。
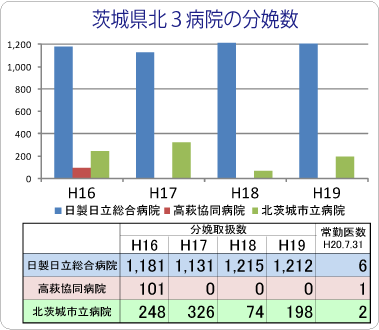 日製病院は、平成17年、18年には、年間1200件を超える分娩を取り扱ってきた県北地域の周産期医療の拠点病院です。常勤の産科医が派遣されていた東京大学の医局に引き上げれたため、平成21年4月から分娩の受け付けを休止。ハイリスク出産に対応する地域周産期母子医療センターの機能も休止しています。日製病院の産科休止を受け、市内の妊婦さん達の負担は非常に大きなもとなっていました。
日製病院は、平成17年、18年には、年間1200件を超える分娩を取り扱ってきた県北地域の周産期医療の拠点病院です。常勤の産科医が派遣されていた東京大学の医局に引き上げれたため、平成21年4月から分娩の受け付けを休止。ハイリスク出産に対応する地域周産期母子医療センターの機能も休止しています。日製病院の産科休止を受け、市内の妊婦さん達の負担は非常に大きなもとなっていました。
昨年4月以降、女性医師が婦人科で外来診療を受け持ち、10月には新たな男性医師を確保し、産科の再開に向けて準備を進めていましたが、待遇面や勤務体制などで病院当局と話し合いがまとまらず2人とも日製病院を離れました。
県は、阿見町に茨城医療センターを運営している東京医科大と地域医療への支援体制を協議。今年度から、東京医大に地域医療の充実を目的とした「寄付講座」を予算化するなど、連携を強めていました。来年度からは、“地域医療再生計画”による寄付講座の拡充などを行うことになっています。また、東京医科大学には、茨城県内の医師不足地域の病院で9年間勤務することを条件に、県が返済不要の奨学金(月額15万円)を支給する“地域枠”を設けるなど、パイプも太くなっています。
こうした信頼関係のもとに、3名の産科医師をチーム体制で派遣するという全国でも類例のない体制を敷くことが出来ました。



