 2月3日、公明党の山口那津男代表は、参議院本会代表質問に於いて、「第2のセーフティネット」構築の必要性を強く主張しました。
2月3日、公明党の山口那津男代表は、参議院本会代表質問に於いて、「第2のセーフティネット」構築の必要性を強く主張しました。
この中でも特に、老後の暮らしの柱となる年金では、無年金・低年金者の増大を食い止める対策の実行が「待ったなし」の緊急課題となっています。
このため公明党は1月22日の衆院予算委員会の論戦で、井上義久幹事長が(1)年金保険料の事後納付期間の延長(現行2年を5年に)(2)受給資格期間の短縮(現行25年を10年に)(3)低所得者への加算年金制度の創設(基礎年金を25%上乗せ)――の具体策を掲げたパネルを示しながら、公的年金の速やかな改善を主張。政府の前向きな答弁を引き出しました。
このうち受給資格期間の短縮について鳩山首相は「重要な発想だ。25年は長すぎるので検討したい」と答弁し、多くのマスコミがこれを報じました。首相のリーダーシップで検討を急ぎ、公明党の提案に沿った実現を期待するものです。
保険料の事後納付期間の延長については、長妻厚生労働相が「過去10年までさかのぼって納めていなかった国民年金保険料を払えるよう、法案の提出を検討している」と重ねて表明しました。10年は大いに結構だが、問題は実施のスピードです。有言実行を強く望むところです。
公明党が一貫して主張し続けている受給資格期間の短縮や保険料の事後納付期間の延長が実現すれば、新たに受給資格を得る人や、満額受給(現行は40年加入で月額6万6000円)できる人が確実に増え、老後の大きな「安心」につながります。
65歳以上の無年金者は現在、42万人に上っており、今後加入を続けても受給資格を得られない人を合わせると118万人にも膨れ上がる見通しです。それだけに、無年金者対策の切り札として、急ぎ実現しなければならない対策です。
一方、低年金者の問題解消も重要です。
介護保険総点検でも「国民年金だけでは介護施設には入れない。そこのところどう考えているのか?」という声が寄せられています。少なくても介護施設に入居できるような年金加算が必要です。
公明党は、現在5割(2分の1)の基礎年金の国庫負担割合を6割まで引き上げることで、低所得者の基礎年金額を25%程度上乗せする「年金加算制度」の創設を提案しています。これが実現すれば、基礎年金は満額で月8万3000円程度にアップします。
参議院代表質問:山口那津男(2010/2/3)
福祉や雇用のセーフティーネットから漏れた貧困層、低所得や単身の高齢者、ひとり親世帯など、社会的に弱い立場の方々を最優先で支援することが政治に課せられた使命です。
公明党は現行のセーフティーネットを拡充し、所得保障、住宅支援、就労支援等のトータルな支援策をいま一重、厚くすべきです。
第1に、職業訓練等の就労支援とその間の生活保障が重要です。
昨年ILOが発表した報告書では、わが国は失業給付を受けていない失業者の比率がOECD諸国の中で最も高いことが明らかになりました。
まずは雇用保険の適用範囲を拡大することが急務です。
また、公明党の推進で創設した、職業訓練中の生活費用を保障する「訓練・生活支援給付」は、より多くの方が利用できるよう拡充するとともに、制度を恒久化すべきです。
第2に、高齢期の所得保障の柱である年金制度の安全網を強化することが必要です。公明党がこれまで主張してきた、年金保険料の事後納付期間の延長は、今般、政府提出の国民年金法改正案に盛り込まれましたが、これだけでは支払い能力のある方しか救済できず不十分です。
事後納付期間の延長とともに、受給資格期間の短縮、さらには低所得者に年金額を上乗せする年金加算制度の創設を早急に実現すべきです。
第3に、ひとり親世帯や独居高齢世帯の増加といった今日的課題を踏まえ、こうした方々が安心して生活できるよう、給付面のみにとどまらずサービスの提供においても支援を強化すべきです。
ひとり親が安心して子どもを預けられる安価な保育サービスや、独居高齢者の安全を地域で見守るサービスなど、必要かつ十分な支援を行うべきです。
以上、わが党が提案する安全網強化の具体的な取り組みについて、総理の考えを伺います。



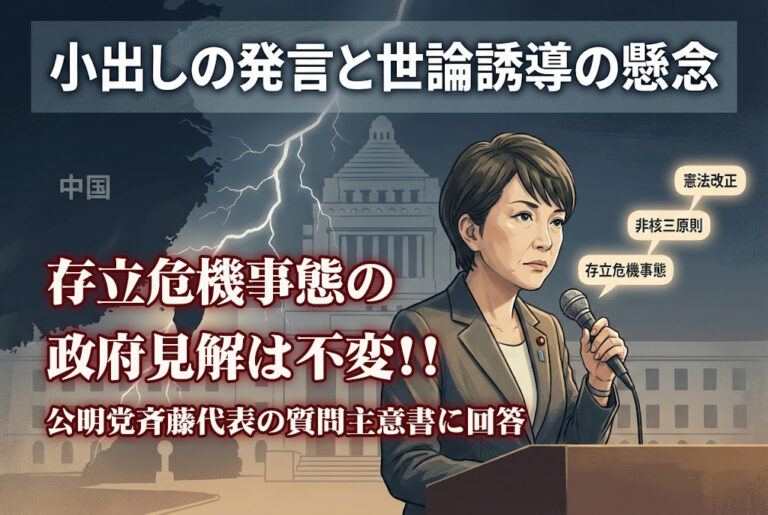
続き
■提案
▼「保険料を納めないとペナルティーを受ける」
国民年金に限らず保険料の未納は、「生活保護サービスを受ける権利」の放棄と位置付ける。
年金保険料を納付してないのに、生活保護を受給する場合は、未納分を換算して、支給額を減らすべき。
▼「生活保護受給世帯の使途をチェック」
『生活保護は公金とも言える。公金なのだから、その使途にチェックが入るべき』。
「何の目的で使われたか・最低限の生活を維持するため以外に使われていないか」をチェックするために、
生活保護の受給世帯には「通帳」と「1円単位で全ての領収書」を提出させ、
使途をチェックし、「最低限の生活維持以外に使われていたら、その金額分を次回の給付時に減額する」ようにしていくべき。
チェックは、自治体が行うと人件費がかさむため、民間委託すれば良い。
▼「何の努力もしないで自然に金が入り、生活保護>年金を改め、生活保護支給額を引き下げる」
そもそも、生活保護の支給額が高過ぎると思われる。
夫33歳・妻29歳・娘4歳の世帯に適用される月間生活扶助基準額は16万2170円。20・30代の単身者でも月額8万3700円。
住宅扶助も加算され、更には、出産費用を含む医療費は全額無料。子供の学用品、学級費、給食費、交通費も扶助対象。
終わり
続き
■重要な事は、『国民の公平感があって初めて、行政や社会保障の正当性が保たれる』ということ。
国民年金に限らず保険料の未納、税金の滞納は、「生活保護・行政サービスを受ける権利」の放棄。
「保険料を納めなくても生活保護、同じ行政サービスが受けられる」という《タダの意識》が広まると、自治体の扶助費が増加し、地域の社会保障制度が揺らぐ。
地域医療崩壊の原因の一つが、「病院のコンビニ化 = 市民の傲慢な意識の広まり」であることからも明らか。
日本で行政サービスを受けている外国人労働者には、税金滞納の際にはペナルティーがある。07年、入国管理のルールが厳しくなり、『ビザ更新の際には住民税の納税証明書の提出が求められる』ようになった。
日本人にもペナルティーを課すべき。
■《タダの意識》が広まった結果
【政治】 人件費削減で、3億2千万円削減に成功!→でも生活保護費が3億6千万円増…宮城・大崎市予算 http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1265269728/
http://mytown.asahi.com/miyagi/news.php?k_id=04000001002040004
続きます
続き
そうしなければ、未納者が「すすんで事後納付しよう」という気持ちは起きないと思われる。未納のまま生活保護を受給した方が、タダで楽なのだから。
年金制度そのものだけの改革を行っても、納付する意欲を削ぐ障害を取り除かなければ、効果はあまりないと思われる。
■生活保護の過剰保護は《不労所得・未納所得》環境を誘発する
生活保護の真の目的は「自立支援」。
生活保護とは本来、「働かざる者 食うべからず」を大原則とする社会の中で、『健常者と同じスタートラインに立つ事が難しい』人を対象としていたはず。
しかし、いつの間にか、「働いても一向に苦しい」勤労者や「年金保険料を納めた」納付者よりも、恵まれた《不労所得・未納所得》環境が保障される、不可解な状況が生じている。
続きます
■未納者の意識改革が伴っていない
●無年金者対策
▽「事後納付期間の延長…現行2年を5年に」
▽「受給資格期間の短縮…現行25年を10年に」
●低年金者対策
▽「低所得者に年金額を上乗せする年金加算制度の創設…現在5割(1/2)の基礎年金の国庫負担割合を6割まで引き上げることで、基礎年金を25%上乗せ。基礎年金は満額で月8万3000円程度にアップ」
確かに、この「国民年金制度の改革案」は、無年金者・低年金者対策としては良い。
しかし、これには「制度を利用する未納者の意識改革」が伴っていない。
アメはある(事後納付のメリット)が、ムチがない(現行の事後納付しなくても困らない環境から、事後納付しないと困る環境へ)。
■事後納付のメリットを作る改革と同時に、公的年金制度の周辺=生活保護の改革を行うべき。
例えば、▽「生活保護の支給額を引き下げる」 ▽「年金保険料を納めないとペナルティーを受ける」 ▽「生活保護受給世帯の使途をチェック」など。
『こうして、現行の「事後納付しなくても困らない、納付する意欲を削ぐ」環境をなくし、「事後納付しなければ困る」環境を作り出して、強制的に「未納者の意識改革」を行うべき』。
続きます