年金一元化・最低保障額など…新制度7原則決定
読売新聞(2010/6/29)
政府は29日午前、「新年金制度に関する検討会」(議長・菅首相)を首相官邸で開き、年金制度の一元化や最低保障年金の導入など、7項目にわたる新制度の基本原則を決定した。急速な少子高齢化など、社会構造の変化に対応した新たな年金制度の導入を目指すもので、政府・民主党は今後、与野党協議を呼びかけ、2013年に関連法案を提出することを目指す。
基本原則の柱は、現在の厚生、国民、共済の各年金を一元化して全国民が同じ制度に加入する年金一元化や、最低限の年金額が保障される最低保障年金の導入など。昨年の衆院選の民主党政権公約(マニフェスト)に基づく内容だ。
ただ、マニフェストでは最低保障年金を「月額7万円」と明記し、財源に消費税を充てるとしていたのに対し、今回の基本原則では「将来にわたり安定的財源を確保する」との表現にとどめるなど、具体的な制度設計への言及はほとんどない。政府は参院選後にも、各党に与野党協議を呼びかけるため、詳細をあえて盛り込まなかったとしている。参院選で消費税率引き上げが論点となっていることも背景にあるようだ。検討会は今年3月に初会合を開き、議論を進めてきた。
◆新制度の基本原則◆
- 年金制度の一元化
- 最低保障年金の導入
- 負担と給付の関係の明確化
- 持続可能な制度の構築
- 年金記録の確実な管理とチェック
- 未納・未加入をなくす
- 国民的議論で制度設計
民主党は、最低保証年金の創設を昨年夏の総選挙のマニフェストに盛り込みました。しかし、そのマニフェストの具体的な検討は遅れに遅れ、10カ月余りを経過して、やっと検討の前提となる7つの原則が示されました。
しかし、もうこの時点で最低保証年金の7万円という具体的な金額が削除され、その財源も示されませんでした。皮肉にも、民主党の年金案がいかに杜撰だったかを満天下に占める結果となってしまいました。
そもそも、民主党の年金案には大きな欠点がたくさんあります。
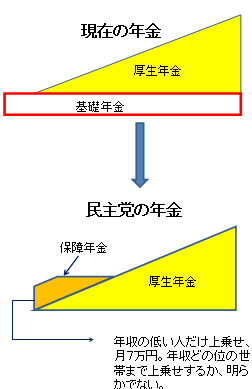
- 基礎年金はなくなり、中堅サラリーマン以上は年金額が少なくなります。
- 最低保障年金は年収200万未満の人と仮定して12兆円以上かかります。消費税で5%になります。(全員に7万円の保障年金を付けると24兆円必要です。)
- 国民年金の人は、サラリーマンの倍額保険料を払うことになり、もらう年金は同じです。保険料は「収入」の15%と言っています。(サラリーマンは雇い主が1/2の保険料を払って貰えますが、国民年金の加入者は保険料を全額支払う必要があります)
- サラリーマンの奥さんは、現在の制度では保険料を払わなくてもよいことになっています。民主党案では払うことになります。
- 民主党案ができたとしても、完全にでき上がるのは40年先の話です。
こうした実現不可能な政府案(民主党案)に対して、公明党は暮れせる年金を目指して、国民年金(基礎年金)だけの受給者の年金を25%程度加算する“加算年金制度”の創設を提案しています。
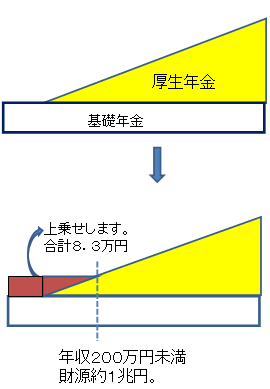
- 公明党の「100年安心年金」は、推測可能な数字から、計算されたものであり、年金制度の基盤は盤石であると言われています。
- 100年安心をして年金を受け取るためには、次の2つが必要です。①2050年までに、一人の女性から平均して生まれる子どもの数が1.39人以上になること。②経済が毎年1%位のなだらかな成長を続け、賃金もなだらかに増えること。
- 年収200万円未満の年金生活者には基礎年金をかさ上げして、8.3万円にします。また、掛け金の年限を25年以上から10年以上に短縮します。
民主党案は保障年金7万円の上乗せであり、上乗せをどれ位の年収までするのか明らかにしていません。年収200万円未満の高齢者世帯にすると仮定をしますと、高齢者世帯の50%を超えます。必要額は12兆円を超えます。昨年、山井厚生労働大臣政務官は、国民新党への説明で、必要額を13.5兆円と述べています。
したがって、それだけで消費税で5%上乗せが必要であり、消費税を10%にしても他の医療や介護、子育て等に対する財源がなくなることを意味します。
一方、公明党案では、基礎年金(満額で6.6万円)があり、年収200万円未満の高齢者世帯には、基礎年金額を8.3万円(8.3-6.6=1.7万円)まで上乗せを行います。そのため、必要な額は低く抑えられます。また、単身世帯には年収160万円未満で上乗せします。
公明党案では、基礎年金があるため、年収200万円未満の世帯は少ないし、世帯当たりの上乗せ額も少ないことから、総額で必要とする額も1兆円で済みます。



