人間と同じように、土地にも戸籍があります。それが地籍です。地籍を確定するために必要な作業が「地籍調査」です。
しかし、この地籍調査を実施済みの土地は、まだ半分にとどまっています。地籍が未整備なため、所有者間の紛争や、まちづくり、災害復旧の遅れなど、国民生活にも大きな影響があります。土地という限りある資源を、効率かつ有効に活用するために、地籍調査の迅速な実施は重要な課題です。
太閤検地以来、手つかずの場所も
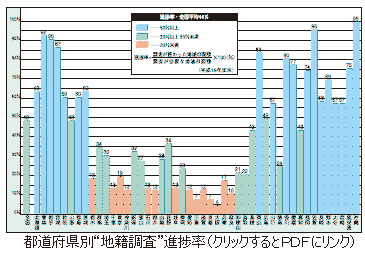 地籍は所有者、地番、地目、面積、境界といった土地所有の基本情報から成り立っています。土地一筆(土地登記の単位)ごとに、これらを確定するため実施する調査や測量が地籍調査で、結果は地籍図と地籍簿にまとめられます。
地籍は所有者、地番、地目、面積、境界といった土地所有の基本情報から成り立っています。土地一筆(土地登記の単位)ごとに、これらを確定するため実施する調査や測量が地籍調査で、結果は地籍図と地籍簿にまとめられます。
地籍調査は1951年に開始され、2007年度末で、要調査面積のうち、調査が終わったのは48%にとどまっています。特に1平方キロ当たりの人口密度が4000人以上の人口集中地区(20%)、山林、原野などの林地(41%)で遅れが目立ちます。都道府県ごとのバラツキも大きく、進ちょく率が最高の沖縄県99%に対し、最低の大阪府はわずか4%です。
16世紀に、豊臣秀吉が行った「太閤検地」以後の実態が把握できていない土地も多くあると言われています。
地籍は土地に関する行政活動、経済活動の最も基本的な情報ですので、地籍調査の未実施は、さまざまな非効率やムダを引き起こします。例えば、まちづくりです。道路や公園などの整備、市街地再開発事業のような面的開発では、土地の買収や交換が伴いますので、正確な地籍情報が欠かせません。東京の六本木ヒルズでは、約400筆あった境界の調査に4年間も費やされ、余分なコストがかかったと報告されています。
災害復旧にも影響があります。地籍調査の未実施地域で、地震や土砂崩れなどの災害が起き、土地の形が変わったような場合、元の記録がないために境界確認などに時間をとられ、復旧が遅れることになるのです。阪神・淡路大震災では、地籍情報がないため、土地を担保にした住宅再建資金の借り入れができなかったという話もあります。
ほかに地籍調査の目的として、固定資産課税の適正化や地理情報システム(GIS)への活用などがあります。さらに、森林管理の適正化も重要です。
地籍調査は土地所有者にとっても利点があります。
土地境界をめぐる紛争を未然に防いだり、土地取引や相続の円滑化、登記費用の節減などを通じて、個人資産の保全にも役立つことになります。
なぜ地籍調査が進まないのか?
行政や住民に必要性が十分に理解されていないことや、予算や職員の確保が難しいことなどが指摘されています。また、都市部では権利関係が複雑なこと、林地では土地所有者が地元にいないことなども、この地域で特に遅れを生じさせる原因です。
地籍調査は市町村等の自治事務ですが、担当者からは「実施体制を整備するための人件費補助が出ない」「財政悪化で着手に踏み切れない」などの声が出されています。
地籍調査の実施が遅れるほど、土地の境界を示す目印(物証)や、境界に関する人の記憶(人証)が失われていきます。
先の通常国会では、地籍調査の迅速化を図るため、改正国土調査促進特別措置法など関連2法が成立し、公明党が審議を主導しました。
公明党が進めた関連法の改正
今回改正された国土調査促進特別措置法と国土調査法のポイントは、地籍調査を都市部や山林で重点的に進めることです。地籍調査は、特にこれら両地域で遅れています。例えば、京都市のように0%と未着手の自治体も多く残されています。これが、都市再開発や森林整備が遅れる原因になっています。
そこで、都市部において官民境界情報の整備を促進したり、山村部の境界情報を保全するための基礎的調査を進めることを定めました。その上で、民間活力の導入を明記。地籍調査の進ちょくを図るため、自治体が調査・測量などを、土地家屋調査士など民間に委託できるようにしました。
この法律は、今年度からの第6次国土調査事業10カ年計画の基礎となるもので、今回の機会を逃すと地籍調査を促進する次の論議は10年後になってしまいます。地味な法律のためか、他党はあまり関心を払いませんでしたが、公明党は審議を終始リード。法律の運用が適切に行われるよう、「毎年度の進ちょく情報の公表」「民間委託の積極的な活用を図る」など、7項目の付帯決議を行いました。
地籍調査の進み具合は、実際の事業を受け持つ市町村の動向にかかっています。市町村が主体性を発揮することが何よりも重要です。
財源面でも、特別交付税により市町村の負担は実質5%と軽くなっています。法改正で導入された、都市部での官民境界情報整備のための調査などにも、国の予算が手当てされています。法案審議で私は国交省側から、「経費に関する自治体の相談に柔軟に応じる」という趣旨の答弁も引き出しました。
地籍調査は自治体が将来へ向けて発展していくための基礎です。首長がこうした認識を持ち、リーダーシップを発揮することが不可欠です。



