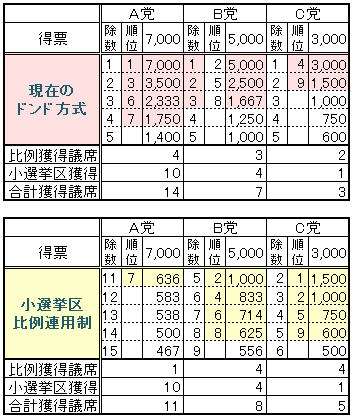 衆院選挙制度改革の中で公明党が提案している「連用制」とはどのような制度か、多くの方から質問をいただきます。昨年9月に1度ブログに掲載いたしましたが、もう一度、公明新聞の記事(2012/2/9付け)を参考に説明します。
衆院選挙制度改革の中で公明党が提案している「連用制」とはどのような制度か、多くの方から質問をいただきます。昨年9月に1度ブログに掲載いたしましたが、もう一度、公明新聞の記事(2012/2/9付け)を参考に説明します。
「小選挙区比例代表連用制」は、現行の小選挙区比例代表並立制に比べて、より民意を反映する選挙制度です。 小選挙区制は、1選挙区から1人を選ぶことで政権選択をしますが、2位以下の落選者の得票は議席に反映されず、いわゆる「死票」となってしまいます。
例えば、2005年の“郵政選挙”では小選挙区で、自民党が得票率47.8%で議席の73%を獲得。2009年の“政権交代選挙”では民主党が得票率47.4%で議席の74%を得ています。
つまり、得票率が半分にも満たない政党が4分の3の議席を占めてしまう。このように、政党の得票率と議席率との差が開きやすく、民意が反映されにくいのが小選挙区制なのです。
この“欠陥”を補うために、並立制も政党の得票分だけ議席数に反映される比例代表を組み合わせていますが、定数480のうち、小選挙区が300を占め、比例代表は180に過ぎないため、民意の反映という点では極めて不十分な制度と言えます。
これに対して、連用制は並立制の投票の仕方などを変えずに、小選挙区と比例代表という二つの制度の間に「つながり」を持たせることで、いわば“一つの制度”とすることで、並立制の欠陥を是正するものです。
どのように「つながり」を持たせるかと言うと、比例代表の議席を決める際、小選挙区で議席を得た政党はその議席数分を配分したものとし、小選挙区で多くの議席を得た政党ほど、比例議席を獲得しにくいようにするわけです。
連用制を導入した場合、並立制で40%台の得票率で70%台の議席率が、50~60%台の議席率まで下がり、民意の反映がかなり補正されることになります。成田憲彦駿河台大学法科大学院教授も「投票価値の不平等や小選挙区制の“罠”を脱し、国民的合意形成の政治を実現することができる」と指摘しています。
各党は、2月25日までに制度改革、「1票の格差是正」、定数削減を同時決着することで合意しています。制度改正が待ったなしの状況にあって、並立制から迅速に移行できる連用制は現実的な制度改革案と言えます。
連用制について「中小政党に有利」との指摘がありますが、並立制はあまりにも「大政党に有利」でした。選挙制度改革は、日本社会にある多様な民意をどう国会に反映しているかという「理念」をもとに議論を深めるべきです。公明党が提案する、より民意を反映する制度により、格差是正はもちろん定数の大幅削減も実現できます。



