3月末までの退職者は100万円、4月以降140万円の減額
2月13日までに、茨城県職員の退職金減額問題について、県と職員労組との間の交渉が妥結しました。
国は、国家公務員の退職手当水準が民間の平均より約400万円高い状態を是正するため、1月から段階的に減額しています。国家公務員と同様に、地方自治体にも地方公務員(教員、警察官を含む)の退職手当の減額を要請していました。しかし、埼玉県や佐賀県など複数の自治体で、3月末に定年退職を迎える職員、特に教員が、減額前に駆け込み退職する事態が多く発生し、批判の対象となっています。
茨城県が組合と妥結した内容によると、3月から段階的に現行の退職手当(平均約2740万円)を、国と同様に約400万円引き下げます。条例改正の施行日から3月末まが約100万円の減額、4月から9月末まで約140万円減、10月から2014年6月末まで約280万円減、7月以降約400万円の減額と、の4段階で引き下げます。
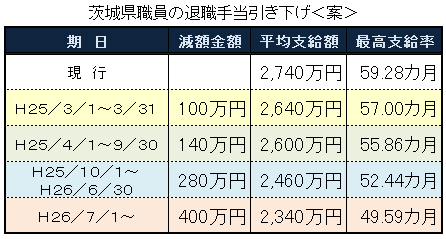
今年度末の退職予定者は787人。県は当初、減額幅を平均140万円減としていましたが、100万円減に激変緩和することで、組合と交渉が成立しました。この退職金の引き下げで、約12億円の人件費を削減することが出来ます。
こうした動きを受けて、茨城県議会では27日開会の第1回定例県議会で、優先的に審議を行う事になります。当日の議会運営委員会で、各会派の了承が得られれば、即日、知事からの提案を受け、委員会審議を経て、採決を行う見込みです。県議会で認められれば、3月1日から退職金減額のための条例が施行されます。
井手よしひろ県議は、この退職金の見直しは積極的に進めるべきと考えています。また、今回の退職手当の減額問題に起因して起こっている早期退職問題は、60歳の誕生日を過ぎると退職日である年度末までの間は、自己都合で退職しても退職手当が減額されないという制度の問題があると考えています。東京都や長野県、鳥取県ではこのような制度はありません。茨城県も民間との格差是正を本気で考えるなら、制度の再検討が必要と強く主張します。



