 平成23年3月11日、東日本大震災からもうすぐ2年が過ぎようとしています。この間、多くの被災を被った方々と対話を交わすと、「あの福島第1原発の事故さえなかったら、復興はもっとスムーズに進んだろう」ということばが、必ず聞かれます。大震災とそれによる津波で、東京電力福島第一原子力発電所は、いまだかって経験したことのない全電源喪失の状況に陥り、水素爆発、メルトダウン(炉心溶融)に至りました。これにより、大量の放射能が放出され、数十万人に及ぶ近隣住民が先祖伝来の土地を離れ、数百万人の国民が放射能汚染と将来の健康被害に対して深刻な不安を抱くに至りました。“原子力発電は多重に防御され、絶対に重大事故は起こらない”との原子力神話は脆くも崩れ、政府や原子力や医療の専門家に対する信頼も揺らいでしまいました。現に原発が立地する東海村などの地域では、住民間の相互不信や意見の衝突も激しくなっています。
平成23年3月11日、東日本大震災からもうすぐ2年が過ぎようとしています。この間、多くの被災を被った方々と対話を交わすと、「あの福島第1原発の事故さえなかったら、復興はもっとスムーズに進んだろう」ということばが、必ず聞かれます。大震災とそれによる津波で、東京電力福島第一原子力発電所は、いまだかって経験したことのない全電源喪失の状況に陥り、水素爆発、メルトダウン(炉心溶融)に至りました。これにより、大量の放射能が放出され、数十万人に及ぶ近隣住民が先祖伝来の土地を離れ、数百万人の国民が放射能汚染と将来の健康被害に対して深刻な不安を抱くに至りました。“原子力発電は多重に防御され、絶対に重大事故は起こらない”との原子力神話は脆くも崩れ、政府や原子力や医療の専門家に対する信頼も揺らいでしまいました。現に原発が立地する東海村などの地域では、住民間の相互不信や意見の衝突も激しくなっています。
その結果、日本のエネルギー政策は根本から見直す必要に迫られています。
と同時に、茨城県議会議員である私の所には、毎日のように東海第2発電所の廃炉を求める方からメールや電話、文書をいただきます。反対に、原子力発電関連のお仕事を生業とされる方からは、「安全性を確保して早期に再稼動させるべきだ」とか、「老朽化した原発は早急に廃炉にして、より安全性の高い高効率の原発を新規に建設すべきだ」とのご意見も頂戴します。
私たちにとって、総論としての日本の原子力エネルギー政策の課題、具体論としての東海第2発電所の再稼動(または廃炉)の課題は、別々に議論できる問題はありません。ここでは、現時点での私の見解を、整理してみたいと思います。
国民は「原子力に依存しない社会の実現」を望んでいる
原子力発電の将来をめぐっては、「脱原発か、否か」で世論が二分されているような報道があります。しかし、そういった二者択一の議論を多くの国民は望んでいません。様々な世論調査などをみてみると、より多くの国民のコンセンサスは「原子力に依存しない社会の実現」ではないでしょうか。しかし、それに向けての「実現可能性」や「いつまでに達成するか」についてはまだ世論も定まってはいません。“2030年代に原発ゼロ”という前民主党政権の決定に、いかに客観性がないか、多くの国民は気付いています。また、同時に原子力政策を定める張本人である政府や原子力の専門家に対して、国民の不信感は極限に達しており、その不安解消なしには、今後の国の方向性を決めることが出来ない状況であるということです。
この3点を考慮し、最も重要なことは、国民の信頼回復を最優先に、実現可能でかつ具体的課題を着実に解決していく政策を示していくことです。それは、なによりも福島第1原発の事故原因の徹底的な究明であり、事故の完全収束に他なりません。そしてそれには、福島の復興にむけての除染や賠償、健康管理なども当然含まれます。実際の被害のあるなしにかかわらず、心理的な不安や風評による被害の回復も、当然含まれます。
こうした一連の取り組みに対して、国内外に対し取り組みの透明性を確保する「第三者機関」が必要だと思います。また、地域住民への丁寧な説明や意見を聞き取る組織も大事です。
原発ソフトランディングのための「政策移行期間」が必要
日本の原子力政策は、昭和30年来「原子力基本法」の下、これまで拡大一辺倒で進められてきました。日本で最初に原子の灯が点った茨城県は、その県歌「茨城県民の歌」に『世紀をひらく原子の灯』と原子力礼賛のメッセージを託しました。この原子力発電が、日本の高度成長を支え、公害問題解決からCO2削減という環境対策に大きな貢献をしてきたことも否定できません。
しかし、ここで「原子力に依存しない社会」を目指すとすれば、当然ながら原子力エネルギーを社会基盤としていた制度や産業インフラをすべて見直していく、覚悟が必要です。日本丸という巨大な船の舵を急激に切ったとしても、その巨体が進路を変えるには時間が掛かります。急激に舵を切ることは、船自体の転覆に繋がる懸念もあります。
私は、原子力発電の『ソフトランディング』という発想がどうしても必要だと思います。そして、その軟着陸のための「政策移行期間」がどうしても必要です。国はしっかりとした「原子力に依存しない社会」への政策を立案し、その上で激変緩和策や実行計画のロードマップを作成するための期間です。今、この「政策移行期間」の実態が見えてこないことが、国民に不安をもたらしている最大の要因ではないかと思います。
まず、国内50基ある原子炉をいつまで使うのか、反対にいつ廃炉にするのかというロードマップを明らかにする必要があります。国の原子力規制委員会は、この夏までに“再稼動の条件”を示すことになっています。同時に、原発稼動の40年ルールを厳格に運用することも必要です。この2つの“物差し”をもとに、一つひとつの原発を棚卸しする必要があります。誰もが、客観的に認識できる物差しで、今後の日本のエネルギー政策を俯瞰していくべきです。
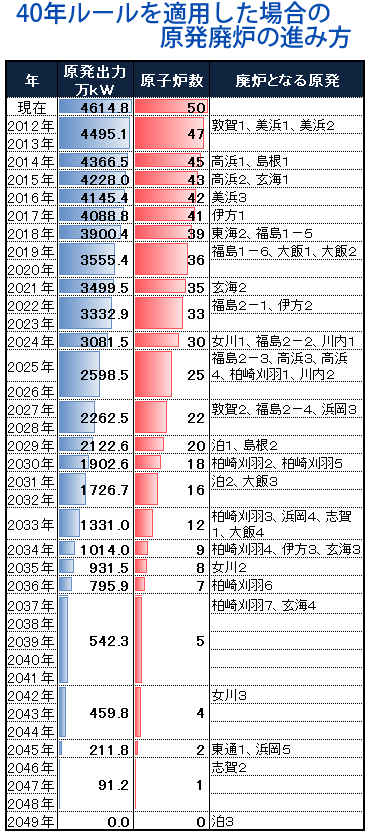
今こそ、核燃料サイクル政策の抜本的見直を
原発の廃炉が簡単に出来ない理由に、日本の「核燃料サイクル」の問題があります。今まで、日本の原子力政策は核燃料サイクル確立と高速増殖炉実用化を大きな柱としてきました。つまり、日本の核燃料サイクルは、全量再処理が前提だったのです。使用済み燃料の処分方法は、再処理か貯蔵しか認められていません。途中、中間貯蔵も認められましたが、これは、の使用済み燃料が再処理されることが前提であり、再処理が進んでいなければ、中間貯蔵も極めて困難なのです。日本では使用済み燃料の「直接処分」は、現行法上は不可能なのです。
今後、原子力に依存しない社会を実現するのであれば、核燃料サイクルは回らなくなります。当然、核燃料サイクル政策を抜本的に見直さなくてはなりません。
しかし、この急激な変更は、青森県をはじめとする立地地域との約束や電気事業等への影響などを考えると簡単にはいきません。
リサイクルしないということは、直接処分ということになります。使用済みの核燃料や使っていない核燃料を、国内に1箇所に集めることなど出来ませんので、各原発の立地場所などに分散して、半永久的に貯蔵しなくてならなくなります。こうしたドラスティックな変化に、原発が立地する地域は果たして対応できるでしょうか?技術的にも制度的にも、住民の理解の上にも困難な問題が待ち受けています。
国の原子力委員会では、「再処理か直接処分か」の二者択一の議論から脱却すべく、「再処理・直接処分併存政策」を提言しています。まず、直接処分の技術開発を進めるとともに、制度として直接処分を可能とすることで、使用済み燃料の取り扱いに柔軟性が生まれるとの提案です。今後、再処理を継続する場合でも、とてもとても計画量を確保することは出来ないでしょう。一方で、いきなり直接処分に移行するのも現実的ではありません。そこで、「中間貯蔵」という考えが重要になります。「中間貯蔵」を核燃料サイクルの中心に据えていくことが最も現実的で戦略的な方向です。
 福島第1原発でも、「乾式キャスク」(使用済みの燃料を金属製の容器=キャスクに封印する方法。自然の空気の流れで冷却するために外部電源は不要です)が津波にも安全であることが実証されました。核セキュリティの面からもプール貯蔵より優位と考えられる。事実、世界中の多くの国がこの「乾式キャスク」方式を採用しており、こうした政策への転換も議論すべきです。
福島第1原発でも、「乾式キャスク」(使用済みの燃料を金属製の容器=キャスクに封印する方法。自然の空気の流れで冷却するために外部電源は不要です)が津波にも安全であることが実証されました。核セキュリティの面からもプール貯蔵より優位と考えられる。事実、世界中の多くの国がこの「乾式キャスク」方式を採用しており、こうした政策への転換も議論すべきです。
また、「高レベル放射性廃棄物処分」政策の転換も不可欠です。いわゆる「トイレなきマンション」として批判されてきた原子力政策を見直すことが必要なのです。今までの考え方は、核燃料サイクル政策をもとに作られてきているので、高レベル放射性廃棄物も直接処分は考慮されていません。これまで以上に、幅広い国民との対話を通じて、広範な合意形成を図るプロセスを設計する必要があります。このためにも、やはりある程度の「移行期間」が必要なのです。
国際的視点も重要。プルトニウムはどう減らすのか
実は、原子力政策は日本の国内問題だけでは済まない重要な国際問題なのです。特に、核燃料サイクルは、核兵器の潜在的保有能力に直結するものであり、国際政治上きわめて機微な技術・施設です。特に、日本は非核保有国として、唯一濃縮・再処理施設の両方を保有しており、今までの再処理の結果、日本国内に約10トン、ヨーロッパに約35トン、合計で45トンものプルトニウムを所有しています。
私は「原子力発電所からできるプルトニウムを使って原子爆弾が作れる」といった誤った議論に加わる気はありませんが、プルトニウム問題を離れてエネルギー問題を解決できないことは、充分に承知しているつもりです。
原発に依存しない社会を実現するとすれば、このプルトニウムをどうするのか、という大きな課題に直面することになります。現在の計画では、15~18基の既存の軽水炉でMOX燃料(原子炉の使用済み核燃料中に1%程度含まれるプルトニウムを再処理により取り出し再利用する燃料)として利用することになっていますが、これも将来、高速増殖炉(FBR)が実用化されることを前提としています。FBRが実用化されないならば、使用済みMOX燃料の処分も再検討の必要があります。
公明党は、プルサーマルも含めて高速増殖炉の研究に慎重な姿勢を示しています。
国はまず、「利用目的のないプルトニウムは所有しない」原則を厳守し、核不拡散・核セキュリティの観点から、プルトニウムを慎重に扱うべきです。
東海第2原発の再稼動は想定できない
最後に具体論としての「東海第2原発の再稼動問題」に触れてみたいと思います。
私は、昨年の県議会代表質問で橋本昌知事に以下のような提言を行いました。
茨城県議会代表質問(2012/3/5)
東海第二発電所の再稼働に当たっては、国民の安全の確保、不安払拭が何よりも重要であり、茨城県議会公明党としては、再稼働の条件を3つ明示しました。すなわち、①福島第一原発事故の収束、原因の徹底究明。②15メール級の津波に対する対策など、震災・津波対策が完了していること。③UPZの見直しに伴い、30キロメートル圏の原子力防災情報伝達体制や防災拠点の整備、避難道路などの整備が完了していること。この3点の条件が満たされないのであれば再稼働は認められないというのが私ども県議会公明党の基本的な姿勢です。(中略)
テレビやマスコミでは、東海第二発電所の廃炉か再稼働かというまさに二者択一的な議論が横行しています。しかし、私は、茨城県の将来を見据えた冷静な議論が今必要だと考えています。東海第二発電所には、その雇用として900人以上が存在し、定期点検中には1,300人以上の作業員が業務に携わると聞いています。毎年、東海村の歳入のうち、10億円超がこの東海第二発電所からの収入だと言われております。東海第二発電所を再稼働させるにしろ、廃炉にするにせよ、建築後40年を迎える2018年にはこうした雇用や税収は見込めなくなるわけであります。こうしたポスト原発を見据えた戦略が今こそ必要であると考えます。
私は、全くの個人的見解ですが東海第2発電所の再稼動は出来ないと思っています。国も、再稼動を検討する対象に、東海第2原発や女川原発を入れていないとされています。
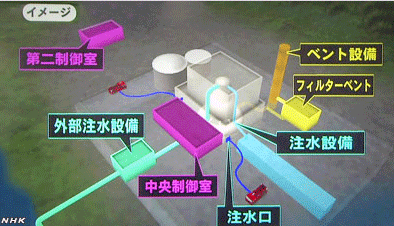 今後、津波対策のための防潮堤や過酷事故時のフィルター付ベント装置、予備の中央制御室(第2制御室)等を設置する費用と期間(すでに東海第2原発は稼動34年目です)を計算すると、はたして東海第2発電所は経済的にペイするのか?
今後、津波対策のための防潮堤や過酷事故時のフィルター付ベント装置、予備の中央制御室(第2制御室)等を設置する費用と期間(すでに東海第2原発は稼動34年目です)を計算すると、はたして東海第2発電所は経済的にペイするのか?新たに30キロ圏内に設定されたUPZ内に居住する106万人余りの県民をどのように避難させるのか?
こうした事実を冷静に受け止めると、再稼動という選択肢はありません。
今必要なことは、単に、東海第2発電所の廃炉を声高に叫ぶことではなく、そこで働く方の雇用や地域の活性化、ひいては日本原子力発電という特別な企業の今後のあり方を、国と県、そして地域がいったとなって考えることではないでしょうか。
(注:以上は茨城県議会議員井手よしひろの個人的見解であり、公明党および公明党県本部の見解や意見を代表するものではありません。また、この考え方はいかなる市町村議会での公明党地方議員の政策判断に、影響を与えるものでもありません)



