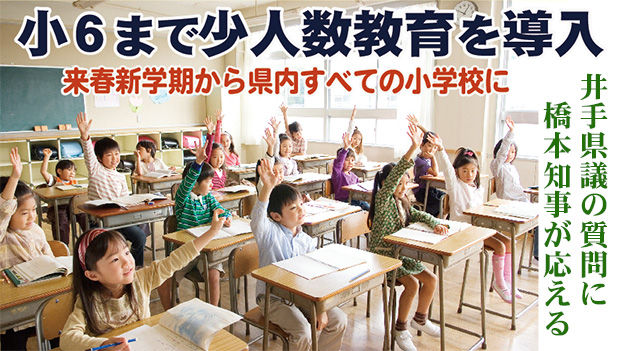
10月9日、県議会代表質問に、井手よしひろ県議が登壇。井手県議は橋本知事の教育立県いばらきを目指す取り組みについて質問。小学1年生から6年生まで全ての学年に「少人数教育」を拡大するよう提案しました。
橋本知事は、「本県独自の少人数教育は、一定の成果が表われてきた。これらの成果をより確実なものにするため、小学校全学年で実施していきたい」と回答。さらに、井手県議は、「茨城県の義務教育の現状を考えると、できれるだけ早く、来年4月から導入すべきではないか」と重ねて質しました。橋本知事は「できれば来年度から実施したい」と、平成26年度から実施する方向を明確にしました。
茨城県独自の少人数教育は、平成17年度から小学校1年生に導入。翌18年度には2年生までに拡大されました。国の基準では、一学級40人と定員が定められている中で、その定員を35人とするものです。一学年が1、2クラスの小規模校に対しては、学級分割を行わず、非常勤講師を配置して、ティームティーティグを行う制度です。
学級定員を35人に、1学年2クラス以下の小規模校はティームティーチング導入
平成22年度から、国の少人数教育拡充策を受けて、小学4年生まで拡大されました。国の方針により小学1・2年生はすべて35人以下の学級編成。来年度から3~6年生は、茨城方式での学級編成となります。
少人数教育の拡大には、一学年あたり百人の教師や非常勤講師が必要となります。二学年で二百人の新らたな教員などの確保が必要です。
橋本知事は、定年退職者の再任用を促すほか、国が来年度概算要求に盛り込んだ教員の加配定数などを活用しながら人材を確保する考えを示しました。
約7億円増となる人件費などは、雇用創出基金や国の加配措置の活用などにより、所要財源の確保を図ることにしています。



