
日立市の新交通システム「ひたちBRT」がEST交通環境大賞「優秀賞」を受賞しました。
環境に優しい交通システムの普及を目指すEST普及推進委員会は、「第5回 EST交通環境大賞」(主催:EST普及推進委員会、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団、後援:国土交通省、警察庁、環境省、一般社団法人日本自動車工業会、公益社団法人日本バス協会、一般社団法人日本民営鉄道協会)を決定。EST交通環境大賞は、地域の交通環境対策に関する取組み事例を発掘し、優れた取組みの功績や努力を表彰するとともに、その取組みを広く紹介し、普及を図るために、平成21年度に創設したものです。
第5回の大賞【国土交通大臣賞】には「富山市の公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」が、おなじく大賞【環境大臣賞】には「両備グループの公共交通利用で、歩いて楽しいまちづくり運動」が選ばれました。「ひたちBRT」は大賞に次ぐ高い評価を受けました。
日立市が進めている「ひたちBRT」導入の取組みは、国内における鉄道廃線敷きにバスを走らせる先進事例のひとつです。鉄道を維持できなくなった地域で定時性を確保したバスを維持することで、マイカーからの転換や環境負荷の低減が期待されています。地方における鉄道維持が困難な都市での選択肢のひとつとなる取組みであると評価されたました。
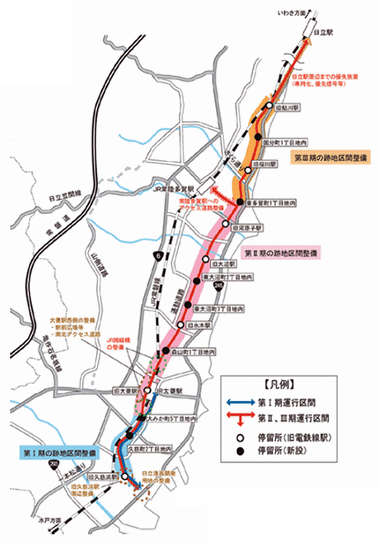 日立電鉄線の廃線跡地を専用道路に改修して、昨年(2013年)3月に開業した日立市のバス高速輸送システム「ひたちBRT」は、好調な滑り出しをみせています。平日1日当たりの平均利用者数は、13年11月までの9カ月のうち5カ月は、採算ラインの470人をクリアしました。6月と9月のように500人を超えた月もありました。専用道の活用による定時性の向上や運行本数の増加が利用者増に繋がっています。
日立電鉄線の廃線跡地を専用道路に改修して、昨年(2013年)3月に開業した日立市のバス高速輸送システム「ひたちBRT」は、好調な滑り出しをみせています。平日1日当たりの平均利用者数は、13年11月までの9カ月のうち5カ月は、採算ラインの470人をクリアしました。6月と9月のように500人を超えた月もありました。専用道の活用による定時性の向上や運行本数の増加が利用者増に繋がっています。
「ひたちBRT」の計画区間は市内を南北に走る約8.5キロの廃線跡地で、日立市は3期に分けて専用道を整備します。既に開業した第1期区間は、延長1.3キロの専用道に一般道を組み合わせた計3.2キロの区間です。
専用道の区間は2005年3月に廃止された旧日立電鉄線の線路跡で、廃線後に橋梁やレールなどが撤去されたうえで市に無償譲渡されました。第1期区間(JR大みか駅から日立おさかなセンター間)には当初から橋梁がなく、早期の道路整備が可能でした。
第2期区間(JR大みか駅~JR常陸多賀駅)は2016年ごろ、第3期区間(JR常陸多賀駅~旧日立電鉄鮎川駅)は20年ごろの運行開始を目指しています。
専用道の整備と保有・管理、および車両の購入は日立市が行います。総事業費は約44億円で、日立市が国の補助を受けて行います。バスの運行は日立電鉄のバス事業部門を引き継いだ日立電鉄交通サービスが担当しています。いわば、公設民営方式の交通システムです。
「ひたちBRT」では、歩道付きの専用道と停留所のほか、一般車両の誤進入を防ぐ運行管理システムなどを整備しました。専用道はバスしか通らないので、1日当たりの計画交通量は道路構造令の区分で最少の500台未満となります。したがって、舗装仕様は市町村道の中で最も低いグレードで済みます。整備コストは1km当たり約5億円で済む計算です。これは、一般に1キロ当たり数十億円以上とされるモノレールやLRT(次世代路面電車)の整備費に比べてはるかに安くて効率的です。インフラの維持管理費もLRTなどに比べて抑えられる見通しです。
BRT導入の目的は、渋滞対策だけではありません。日立市は、鉄道や幹線道路である国道6号からやや離れた西側の丘陵ぶに大規模な戸建て住宅地が広がっています。こうした団地を結ぶ、いわば肋骨方向の公共交通機関が脆弱で、住民は自家用車を主な移動手段としています。
今後の高齢化で自家用車の利用が難しくなった際に、老後を過ごす場所としてBRTの沿線を選んでもらうことを、日立市は想定している。また、BRTを背骨として整備して、肋骨方向へのコミュニティバス路線の充実で、新たなネットワークの構築を検討しています。
現在、2015年度中の完成を目指して、JR大みか駅とJR常陸多賀駅間の工事が順調に進んでいます。この間には森山町1丁目、旧水木駅、東大沼町3丁目、東大沼町2丁目、旧大沼駅、旧河原子駅、東多賀町1丁目の7つの停車場が整備されることになっています。
また、第3期工事終了時には、日立駅までの用地を確保して、専用道を延伸することも検討されています。市の需要予測では、BRTを鮎川駅跡から日立駅まで延伸することで利用者は25パーセント増え、投資効果があるとみています。



