お泊まりディサービス事業者は114。1年を超える連泊を受け入れている事業者が6つ。
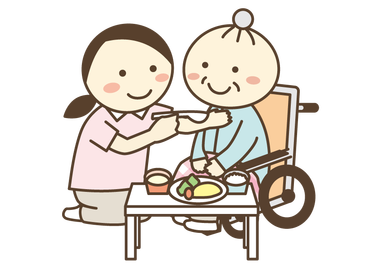 8月27日、茨城県長寿福祉課は「指定通所事業所で実施する宿泊サービスの実態調査」について、その結果を公表しました。
8月27日、茨城県長寿福祉課は「指定通所事業所で実施する宿泊サービスの実態調査」について、その結果を公表しました。
いわゆる「お泊まりディサービス」といわれる、介護保険の枠外の高齢者宿泊サービスの実態を把握して、適切な指導や対応を行うべきであるとの井手よしひろ県議の予算特別委員会での質問を契機に実施されたものです。
お泊りデイサービスとは、日中に介護保険の通所介護(ディサービス)を高齢者が利用し、夜間そのままそこに泊まるサービスのことです。
日中のデイサービスは、介護保険に基づき提供されるサービスのため、職員の基準や設備での基準が定められています。しかし、お泊りディは介護保険外で提供されるサービスなので、全国一律の法的基準がありません。したがって、利用料や宿泊室の広さ、防火対策が事業所によってまちまちです。プライバーシーの保護や安全対策、夜間の介護職員の配置など様々な課題が指摘されています。
お泊りディの宿泊料は、1泊あたり(食事代込み)で1000円から5000円と幅があります(1500円から2000円が全体の31.2%でした)。ディサービスの部屋(機能訓練指導室など)で布団を引いて雑魚寝をするようなところからパーテーションを作ってプライバシーの配慮を行うところまで様々です。
お泊りデイが広がった背景は、介護保険で宿泊ができる高齢者施設が慢性的に足りないことが、最大の原因と考えられます。お泊りディのメリットは、家族の介護負担を減らすことができるため介護をされている家族に有効なサービスです。
反面、安全サービスの基準が施設任せとなっているためドラブルや事故の危険性がある。居室の狭さからプライバシー保護が困難。行政が指導できない体制であり、事故などの実態も把握しきれない。などの問題があります。
今回の茨城県の調査結果を概観してみると、アンケートの回答した通所介護サービス事業者735事業の内、宿泊サービス実施していると回答した通所介護事業所は114事業所あり、その割合は15.5%でした。
宿泊させている居室は、専用の居室を設けている事業所が全体の21.1%。専用居室と機能訓練室等の両方使用している事業者が34.2%。専用の居室を持たず機能訓練室のみを使っている事業所が半数近く(44.7%)ありました。多人数での宿泊になる場合のプライバシーの確保について、大部分の事業所でカーテンやパーテーション等によりプライバシーを確保していましたが、8.2%は配慮をしていないと回答しました。男女別に居室を分けていない事業者が22.7%もありました。
平成26年5月の利用状況を聞いた項目では、1人当たりの平均宿泊日数は、1~5泊が28.9%、6~10泊が5.3%、11~20泊が最も多く32.5%、21~30泊も20.2%もありました。31日間全泊も2.6%ありました。これまでの最大連泊数では、1年以上(366泊以上)が6事業所(5.3%)もありました。
利用料金は、1泊1000~1500円が18.3%、1501~2000円がもっとも多く31.2%、2001~3000円が24.8%、3001~5000円が20.2%、5001円以上も5.5%もありました。かなり利用料金に幅がある現実が明らかになりました。
宿泊時間帯の職員の配置状況は、1人が77.2%と大半を占めていました。2人以上配置していたのは22.8%に止まっています。1人しか配置していない事業所は、急病などで医療機関などに搬送しなくてはいけない場合、居室を見守る人がいなくなり、対応が十分に出来なくなる懸念があります。また、介護福祉士やヘルパーなどの資格を持っていない人が配置される場合も9.6%もあることが分かりました。
事故発生時に市町村に報告していない事業所が18.4%もあり、回答していない事業を含めると30.7%に上りました。スプリンクラーを設置している事業所は30.7%しかありませんでした。



