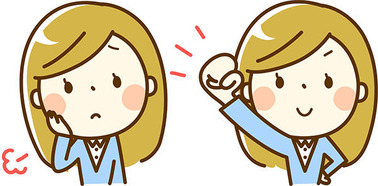 困難な状況に絶えず直面する現代社会。「心が折れる」というような言い方を多くの人が使うようになったのはいつ頃からでしょう。 一昔前は「挫折する」というような表現をしていたと思うのですが、「心が折れる」というと、物事に失敗しただけではなく、精神面でも深く傷ついて立ち直れない状態をあらわしているようで、より深刻な印象を受けます。
困難な状況に絶えず直面する現代社会。「心が折れる」というような言い方を多くの人が使うようになったのはいつ頃からでしょう。 一昔前は「挫折する」というような表現をしていたと思うのですが、「心が折れる」というと、物事に失敗しただけではなく、精神面でも深く傷ついて立ち直れない状態をあらわしているようで、より深刻な印象を受けます。
現代は仕事の悩み、人間関係の悩み、経済的な困難、健康上の問題など生きる上でのさまざまな困難があり、それらをどう乗り越えるかという能力が求められる時代です。
そんな時代に注目されているのが「レジリエンス(resilience)」という言葉です。
レジリエンスとは「復元力、回復力、弾力性」というような意味ですが、最近では「困難を乗り越える力」とか「挫折から回復する復元力」としてとらえられ、個人だけではなく、企業や組織にも求められるリスク対応管理能力とされています。
ストレスとレジリエンス
精神的に圧迫を受けている状態を表すのに、いまでは普通に「ストレス」という言葉を使いますが、ストレスというのはもともと物理学の用語で、「外の力による歪み」を意味していました。レジリエンスは、そのストレスに対して「外力による歪みを跳ね返す力」という意味で使われていた言葉です。
心理学でレジリエンスという概念が注目されたのは、第二次世界大戦でホロコーストを経験した孤児たちの研究だといわれています。ホロコーストという筆舌に尽くし難い逆境を経験した孤児たちの中には、心の傷を負い、そのトラウマのためにその後の生活でも不安にさいなまれたり生きる気力を持てない人々もいました。しかし、一方ではそのような経験を乗り越え、前向きに生きて幸せな家庭を築いた人もいたのです。
同じ厳しい経験をしながらその後、立ち直る人と立ち直れない人。その違いを調べるうちに「レジリエンス=心の回復力」という概念が見えてきたのです。
しなやかな人と折れやすい人
ある心理学者は「レジリエンスには、思考の柔軟性が必要である」と語っています。厳しい状況でもネガティブな面だけを見るのではなく、ポジティブな面を見いだすことができる柔軟性という意味です。
そして楽観性が大事。悲観的なものの見方で現状を見れば、悪い方へ悪い方へ考えが転がっていきますが、楽観的な人は、厳しい状況の中でも何かの希望を見いだして、それを目標に進んで行くことができます。また、そこには前進するための努力・忍耐力も必要な資質として求められるでしょう。
視野の広さ、大局観もレジリエンスのためには必要です。困難な状況の中で下を向いて目先のことだけを考えるのではなく、目線を高く上げて全体を見渡す気構えでいましょう。
そのためには自分を低く考えないこと。プライドを持つことは自分を大切にするためにも大事なことです。
「強い」というと、頑丈で硬いというようなイメージを持ちますが、本当の心の強さとは「柳に雪折れなし」という言葉にあるようにしなやかさを持った心のありようのことなのです。
会社の人間関係、経済的な心配、家族の問題、仕事の悩みなど、厳しい環境を乗り越えるためにも、ただ強いだけの「メンタルタフネス」ではなく、しなやかに対応できる「折れない心」が求められている時代といえるでしょう。
大規模災害への「レジリエンス」
東日本大震災、つくば市の北条の竜巻被害、伊豆大島や広島の土砂災害、また直近では御嶽山の噴火災害など、自然の脅威に「いかに備えるか」「危機に直面した時にどう対応し、どう回復を図るのか」との観点に基づいた取り組みが急務であり、社会の「レジリエンス」を高める必要性が叫ばれるようになってきました。
先にも述べましたが、レジリエンスとは、元来、物理学の分野で、外から力を加えられた物質が元の状態に戻ろうとする“弾性”を表す用語です。その働きを敷衍(ふえん)する形で、環境破壊や経済危機のような深刻な外的ショックに対して “社会を回復する力” の意味合いでも用いられるようになりました。
災害の分野においては、防災や減災のように「抵抗力」を強め、被害の拡大を抑えていく努力と併せて、甚大な被害に見舞われた場合でも、困難な状況を一つ一つ乗り越えながら、復興に向けて進む「回復力」を高めることを重視する考え方と言えます。
「強力な社会的レジリエンスの存在するところには、必ず力強いコミュニティが存在する」と、識者が指摘するように人的側面への注目が非常に重要です。地域に住む人々のつながりや人間関係のネットワークなどのような、ソーシャル・キャピタルを日頃からどう育むかという点が、重要な鍵を握っています。



