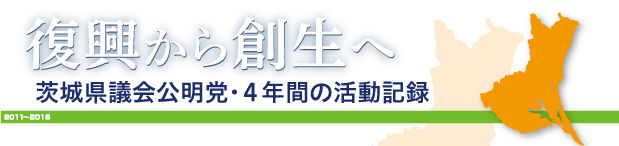
第一回目は、田村けい子県議のレポートです。
 東日本大震災、つくばの竜巻被害、豪雨による各地での土砂災害、御嶽山の噴火等、相次ぐ災害を見るにつけ、私たちの文明社会のあり方を深く考えさせられます。自然の猛威の前に、いかに人間が無力か、どれだけ目覚ましい経済発展を成し遂げ、科学技術が発達した国でも、被害の拡大を食いとめるのは容易ではないという現実。快適さ、便利さを追求し過ぎたがゆえの環境破壊の結果とも言われる異常気象。このような現実を直視すると、自然との共生という視点が重要さを増していると思います。
東日本大震災、つくばの竜巻被害、豪雨による各地での土砂災害、御嶽山の噴火等、相次ぐ災害を見るにつけ、私たちの文明社会のあり方を深く考えさせられます。自然の猛威の前に、いかに人間が無力か、どれだけ目覚ましい経済発展を成し遂げ、科学技術が発達した国でも、被害の拡大を食いとめるのは容易ではないという現実。快適さ、便利さを追求し過ぎたがゆえの環境破壊の結果とも言われる異常気象。このような現実を直視すると、自然との共生という視点が重要さを増していると思います。
持続可能な社会の実現のために、今私たちは何をなすべきか。温暖化対策や生物多様性の保全など、環境に対する取り組みは我が県にとっても重要な課題です。

絶滅種・絶滅危惧種は県内でも増加
世界では今、53000平方キロメートルの森林が毎年減っているほか、多くの国で水不足が生じ、砂漠化の影響も、地球の陸地の25%に及んでいます。温室効果ガス排出量はふえ続けており、気侯変動に歯どめがかからなければ、これまで確認されている生物種全体のうち、3分の1以上が絶滅するおそれがあると言われています。温暖化の防止とともに生物多様性の保全は、地球的な課題となっています。
茨城県自然博物館によると、筑波山において、1981年に生育が確認されていた絶滅危惧植物は34種ありましたが、1995年以降の調査では9種と激減。また、下妻市の砂沼を最後の自生地として生育が確認されていたコシガヤホシクサは、野生から絶滅してしまいました。このように県内においても絶滅種、または絶減のおそれのある動植物が数多く存在しています。
私たち人間も、数ある生物の一種として生態系の一員であり、生態系の恵みに浴しつつ生存して来ました。ところが、近代文明の発達につれて、開発や生物資源の過剰な利用によって自然が改変され、多くの生物種が絶滅の危機に瀕しています。そのため、生態系がもたらす恵みを持続的に受けられなくなってしまうのではないかと懸念されています。
生物多様性地域戦略
このような厳しい状況を受けて、1992年にブラジルで開催された国連環境開発会議において、地球上の生物多様性を包括的に保全するため、「生物多様性条約」が調印されました。
国はこれを受けて、1995年に「生物多様性国家戦略」を策定、2008年には「環境基本法」の理念に則り「生物多様性基本法」を制定しました。2010年には「生物多様性国家戦略2010」を、2012年には、「愛知目標」や東日本大震災の経験を踏まえて「生物多様性国家戦略2012=2020」を閣議決定しました。これによると、2020年までにすべての都道府県が生物多様性地域戦略を策定することを目標としており、2014年11月末時点で、茨城県を含め33都道府県で策定済みとなっています。
茨城県においては、環境や生物多様性にかかわる法律や生物多様性国家戦略を受けて、2013年に「第三次茨城県環境基本計画」を策定しました。そして「環境基本計画」の一部を生物多様性地域戦略に位置付けるとしていました。しかしながら、私は、県内では、開発等に伴う自然破壊によりいくつかの重要な生態系が消滅し、多くの生態系で生物多様性が低下し、場所によっては回復不可能な危機に瀕していることや、生物多様性の保全には県民を巻き込んだ運動論が必要との観点から、議会においても、生物多様性地域戦略の必要性を訴えてまいりました。
 平成24年第三回定例会での私の代表質問に対する知事答弁で「県といたしましては、まず、現在改定を進めております、環境部門の最上位計画であります第3次茨城県環境基本計画において、生物多様性保全に関する基本方針を明確に示し、その上で、具体的な目標や施策を盛り込んだ地域戦略を策定してまいりたいと考えております。」との答弁を引き出すことができました。
平成24年第三回定例会での私の代表質問に対する知事答弁で「県といたしましては、まず、現在改定を進めております、環境部門の最上位計画であります第3次茨城県環境基本計画において、生物多様性保全に関する基本方針を明確に示し、その上で、具体的な目標や施策を盛り込んだ地域戦略を策定してまいりたいと考えております。」との答弁を引き出すことができました。
策定に当たっては、外部に丸投げするのではなく、「地域の自然や郷土文化に配慮し、生物多様性を知り、守り、持続的に利用していくための論理とともに、県民に対しその具体的な対策・対応を示す」ことが重要と訴えるとともに、「地域戦略は、策定されただけでは実効性を持つわけではなく、確実に実践されてこそ生きてくるものと言えます。美しい郷土を次の世代に引き継げるよう、実効性のある戦略となるよう望みます」と要望しました。
そして、県内の有識者による「策定委員会」が結成されました。策定委員会を中心に、環境団体へのアンケートや、県内5地域で実施した「茨城の生物多様性を考える集い」でのアンケート調査等も加味し、策定委員が、自ら分担執筆し、平成25年10月「茨城の生物多様性」の策定に至りました。
全国でも3例目、生物多様性センター開設
この戦略の中で、設置が必要とされている「生物多様性センター」についても、議会や予算要望で、粘り強く働きかけてきました。その結果、このほど、県庁内に「生物多様性センター」が設置されることとなりました。これは、都道府県としては、千葉県・愛媛県に次いで全国で三番目のセンターとなります。
茨城県には、自然に関する教育施設として、自然博物館、大洗水族館、霞ヶ浦環境科学センターがあります。それぞれ独自の取り組みで、環境に関する研究・普及啓発を行っており、重要な役割を果たしています。これらの施設を、生物多様性という横串でつなぎ、連携の拠点としての機能を備えます。
また、県には、自然保護や生物多様性の保全にかかわる数多くのNPOがあります。さらに企業活動においても生物多様性への配慮が必要になってきます。これらの多様な主体との連携・協働を推進し、関係機関の調整を行い、複数の関係機関が個別に進めてきた、保全に関する情報の収集、解析、それらに基づいた施策の提案、県民への情報提供、啓発、教育活動を統合的に進める拠点として位置付けられています。
「生物多様性センター」が、茨城県の環境行政を進めるセンターとなることを期待しています。
(レポート作成:田村けい子県議)



