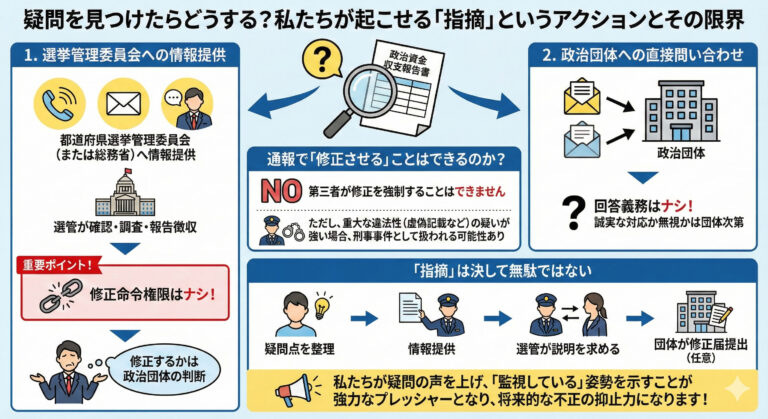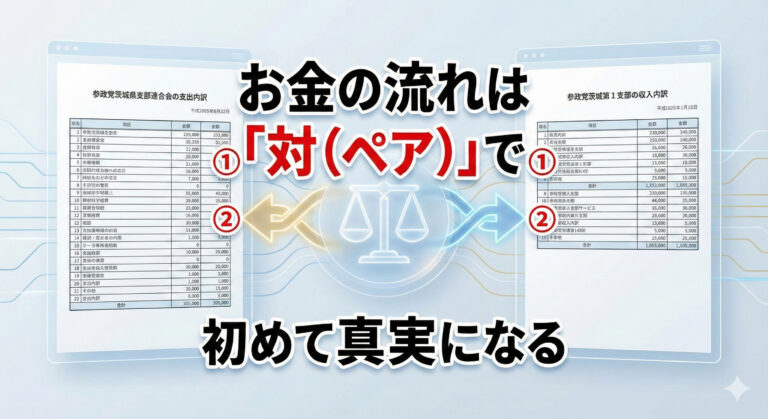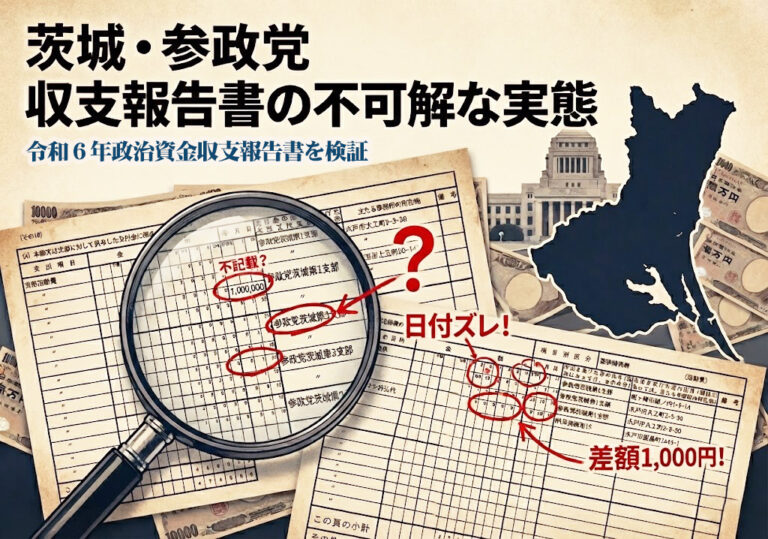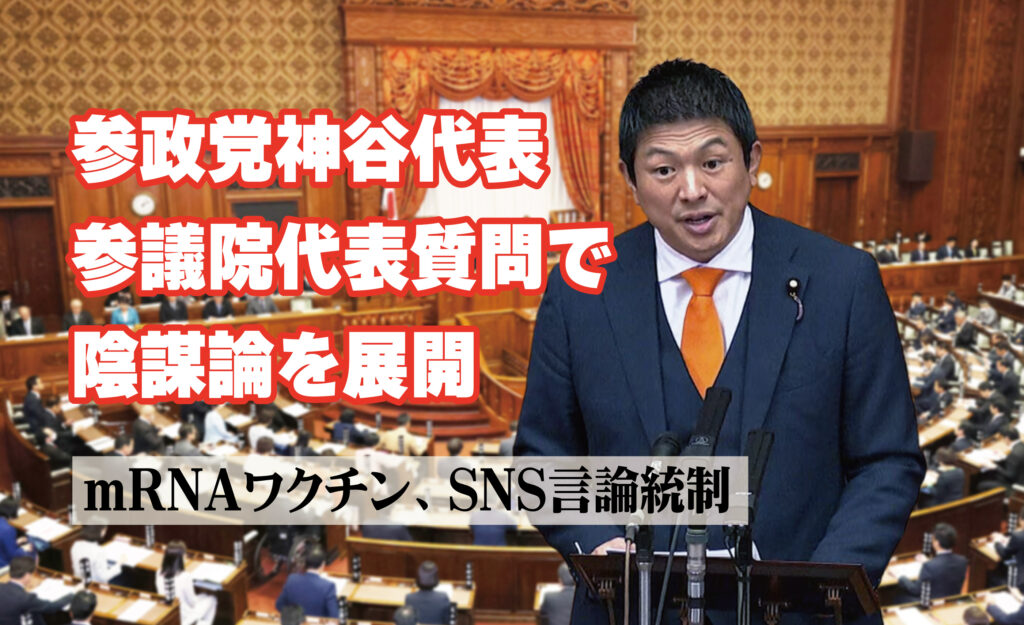
11月6日の参議院代表質問で、参政党の神谷宗幣代表が新型コロナのmRNAワクチンや言論統制について質問しました。ところが、その発言内容は、科学的根拠の乏しい憶測や、海外情報を断片的につなぎ合わせた“陰謀論”の色合いが強く、国会の場で行う質問としては極めて問題のあるものでした。
神谷代表は、「アメリカではmRNAワクチンの新規投資を停止し、年1回の接種推奨をやめた」と主張しました。しかし、米国政府はワクチン開発の体制を縮小したわけではなく、変異株対応や感染症全体への備えにシフトしているにすぎません。「停止」や「撤退」といった表現は、事実をゆがめた誤解を招くものです。
さらに、「日本では超過死亡が10万人増えている」との発言もありました。確かに、コロナ流行以降の死亡者数は増加しましたが、その要因は感染そのものや医療体制の変化、高齢化など多岐にわたります。ワクチンが原因だと断定する科学的根拠はありません。
それにもかかわらず、国会という公式の場で「ワクチンによる被害の可能性」を示唆する発言を繰り返すのは、国民の不安をあおるだけで、建設的な議論とは言えません。
また、神谷代表は「SNSでワクチンと書くと削除される」「言論統制があったのではないか」とも語りました。だが、YouTubeやX(旧Twitter)などの民間プラットフォームが、虚偽情報の拡散を防ぐために一部の投稿を制限したのは、公共の安全を守るための対応です。政府が裏で操作していたという証拠はどこにもありません。
にもかかわらず「政府による言論弾圧」といった印象を国会でばらまくのは、まるでフェイクニュースを公式に読み上げているようなものです。
政治家の発言には重みがあります。ましてや代表質問は、政党としての立場と理念を国民に示す重要な機会です。
それを使って、科学的根拠の薄い主張や、SNSで拡散される疑似情報をなぞるような演説をするのは、政党としての自殺行為にほかなりません。
参政党が「国民の声を代弁する」と言うのなら、まずは正確なデータに基づく政策議論を行うべきです。
感情や陰謀で政治を動かす時代ではありません。国会は事実をもとに議論を積み上げる場所です。そこを取り違えるなら、国民の信頼を得ることは決してできないでしょう。
FactChek-1
アメリカのワクチン方針は本当に変わったのか?
「投資停止」と「推奨中止」の真相
最近、日本の国会でも「アメリカがmRNAワクチンへの新規投資を停止し、年1回の接種推奨もやめた」という発言が取り上げられ、話題となっています。
このニュースは、アメリカ政府がこれまでのパンデミック対応から大きく舵を切ったことを示しており、非常に注目されています。しかし、この発言には「概ね事実である部分」と、「少し解釈が異なる部分」が混在しています。
一体アメリカで何が起きているのか、その背景にある賛否両論も含めて、詳しく見ていきましょう。
1. 「新規投資の停止」は概ね真実
結論から言うと、これは「概ね事実」です。
2025年8月、アメリカの保健福祉省(HHS)は、これまで進めてきたmRNAワクチン開発に関する複数の国家プロジェクト(総額約5億ドル、日本円で数百億円規模)を中止、または縮小することを発表しました。
HHSは公式に「新規のmRNAベースのプロジェクトは開始しない」と明言しています。この決定の背景には、HHS長官が「mRNAワクチンは、重症化を防ぐ効果はあったものの、上気道(鼻や喉)での感染を防ぐ上では期待されたほどの効果を示せなかった」という見解を示したことがあります。
つまり、将来の新しいパンデミックに備えるため、多額の公的資金を投じてmRNA技術の研究開発を続けることは一旦停止する、という大きな判断が下されたわけです。
2. 「年1回の接種推奨」はやや不正解
次に、「年1回の接種推奨をやめた」という部分についてですが、これは「やや不正確、あるいは単純化しすぎている」側面があります。
確かに、2025年10月、CDC(米国疾病予防管理センター)は、これまでの方針を大きく転換しました。 以前は「すべての人に(年1回など)一律の接種を推奨する」という形(Blanket Recommendation)でしたが、これを停止したのです。
しかし、「接種自体をやめた」わけではありません。 新しい方針は、「個人ベースの意思決定(individual-based decision-making)」を重視するというものです。
これは、「一律に全員が打つべき」と言うのではなく、「あなたの年齢や健康状態、現在のリスク要因などを考慮して、医師とよく相談した上で接種するかどうかを判断してください」という形に変わったことを意味します。
政権側はこれを「インフォームド・コンセント(十分な説明と同意)が戻ってきた」と説明しており、一律の推奨が、かえって国民と医療者が個々の状況について話し合うことを妨げていた、と考えているようです。
ただし、アメリカかかりつけ医協会(AAFP)や米国小児科学会(AAP)など、一部の主要な医療専門家団体は、引き続き(推奨の強弱はあれど)接種を推奨する声明を出しており、アメリカ国内でも対応が一本化されているわけではない、というのが現状です。
3. アメリカ国内で起きている激しい議論
このHHS長官による「投資停止」と「推奨方針の変更」は、アメリカ国内で非常に激しい賛否両論を巻き起こしています。その論点は、真っ二つに分かれています。
反対・懸念する声(科学界・公衆衛生の主流派)
多くの科学者、医学界、公衆衛生の専門家からは、強い反対と懸念が示されています。
「非科学的だ」という批判 「ワクチンは重症化や死亡を劇的に減らした」という膨大なデータがあるにもかかわらず、「効果がなかった」と結論づけるのは非科学的であり、現実を無視している、という厳しい批判です。
「将来の安全保障への懸念」 mRNA技術は、次のパンデミック(例えば鳥インフルエンザなど)が発生した際に、最も迅速に対応できる「切り札」と考えられていました。その研究開発を停止することは、アメリカを将来の脅威に対して無防備にする、という安全保障上の懸念です。
「専門家への不信」 HHS長官が、CDCの諮問委員会の専門家たちを解任し、自らが選んだ人物(一部は反ワクチン活動家と見なされている)に入れ替えたことも、科学界からの強い反発を招いています。「公衆衛生が政治化されている」というわけです。
賛成・支持する声(政権・一部の層)
一方で、この決定を支持する声も確かに存在します。彼らの論拠は、ワクチンの有効性そのものよりも、「政府への信頼」や「個人の自由」に置かれています。
「失われた信頼」という現実 政権内部からも「科学的な有効性とは別に、もはや国民の信頼が失われたプラットフォームに、これ以上公的資金を投じるのは無駄だ」という意見が出ています。過去の義務化や政府の対応のまずさで、mRNA技術そのものへの不信感が根深く残っており、公衆衛生の「ツール」として機能不全に陥っている、という戦略的判断です。
「個人の決定権の回復」 前述の通り、「一律に押し付ける」のではなく、「個人が医師と相談して決める」という形に戻すことは、インフォームド・コンセントという医療の基本に立ち返るものであり、正しい姿だ、という支持です。
FactChek-2
「ワクチン動画削除」と「政府の圧力」
新型コロナウイルスのパンデミックを巡っては、今も様々な議論が続いています。その中でも特に根深いのが、「ワクチンに関する情報発信が制限されていたのではないか?」という問題です。
最近、「アメリカ政府がSNS企業に圧力をかけていた」という話と、「日本でもYouTubeの動画が削除されていた」という話が、まるで一つの同じ「言論統制」であるかのように語られることがあります。
しかし、この二つの出来事は、その「主体(誰がやったか)」と「背景」が全く異なります。この違いを理解することは、私たちが「言論の自由」や「情報の管理」について考える上で、非常に重要です。
アメリカで起きたこと:「政府」による介入の疑惑
アメリカでは現在、「バイデン政権が、SNS企業に対して憲法違反の圧力をかけたのではないか」という点が、裁判で厳しく争われています。(「Missouri v. Biden」訴訟などが有名です)
訴訟資料や内部告発(いわゆる「Twitterファイル」など)によって、ホワイトハウスやCDC(疾病予防管理センター)、FBIといった政府機関が、Meta(Facebook)やGoogle(YouTube)、X(旧Twitter)などの巨大テック企業に対し、「これは誤情報だ」と見なした投稿の削除や、拡散の制限を(時には非公式な形で)強く要請していたことが明らかになっています。
これがなぜ大問題になっているかというと、アメリカでは「政府が言論の内容に介入すること」は、憲法修正第1条(言論の自由)によって厳しく禁じられているからです。政府からの「要請」が、実質的な「圧力」や「脅し」であったとすれば、それは民主主義の根幹を揺るがす重大な憲法違反になり得ます。 アメリカでの議論の核心は、まさにこの「政府による介入」なのです。
日本で起きていたこと:「企業」による規約の適用
一方、日本でも、「YouTubeでワクチンのことに言及したら、動画が削除された」「AIに検知されないよう『注射』や『Wkch』といった隠語で発信せざるを得なかった」という現象が広範に見られました。これは事実です。
では、これも「政府の圧力」だったのでしょうか?
ここが決定的な違いです。 日本で起きていたこれらの削除は、基本的に「YouTube(Google)という民間企業」が、自社で定めた「グローバル(全世界共通)ポリシー」に基づいて行った「コンテンツ管理」の結果です。
YouTubeはパンデミック期間中、「WHO(世界保健機関)や各国の保健当局(日本の場合は厚生労働省など)の公式見解と矛盾する医学的誤情報」を禁止するポリシーを全世界で適用しました。 この「企業の物差し」に触れたとAIやモデレーターが判断した動画が、日本国内でも削除されていたのです。
なぜ、この二つが「すり替え」られるのか
ここで、論理の「すり替え(混同)」が起こりがちです。
- 事実A: アメリカで「政府」がSNSに圧力をかけていた。
- 事実B: 日本で「YouTube(企業)」が動画を削除していた。
この二つの事実を並べて、「だから、日本でも政府(あるいはアメリカ政府の影響下)による言論統制が行われていたに違いない」と結論づけてしまうのは、論理の飛躍です。
もちろん、日本政府がプラットフォームに対し、非公式な「お願い」や「要請」をしていた可能性を完全に否定することはできません。しかし、アメリカで問題になっているような「政府による組織的な介入」が日本でもあったという具体的な証拠は、今のところ明確に示されていません。
私たちが日本で直面したのは、主に「巨大な民間企業(プラットフォーム)が、自社の規約に基づいて、世界中の言論を一律に管理することの是非」という問題でした。
「政府による憲法違反の言論介入」と、「グローバル企業によるコンテンツポリシーの適用」。 どちらも「自由に発言できない」という点では同じように見えるかもしれませんが、その問題の所在と、私たちが議論すべき相手は、全く異なっているのです。