要介護区分を6段階から8段階に
厚生労働省は12月22日、介護保険制度改革案の全体像を発表しました。要介護度の軽い人を新予防給付対象に移行、家事援助などを制限したうえでトレーニングなどをし、要介護度の進行を防ぐことや、2005年10月から施設入所者の食費、家賃などの居住費を、原則、自己負担にすることがなど、給付の抑制を目指した内容となっています。
2005年1月の通常国会で改正案が提出されることになります。
新たに導入される介護予防対策では、「予防重視型システムへの転換」を目標に、現行の要介護認定で「要支援」「要介護1」とされた軽度の人向けに、心身の状態の改善や悪化防止を目的とする「新予防給付」を創設します。軽度の要介護者には、原則として従来の介護サービスは給付せず、給付は、新予防給付のサービスに限定されます。新予防給付のメニューは、筋力向上トレーニング、転倒予防訓練、口腔ケア、栄養指導などの新サービスと、従来の訪問介護や通所介護に予防効果を持たせた「予防訪問介護」「予防通所介護」などとなります。新予防給付の導入に伴って要介護状態の区分が現行の6段階から8段階に細分化されることになります。
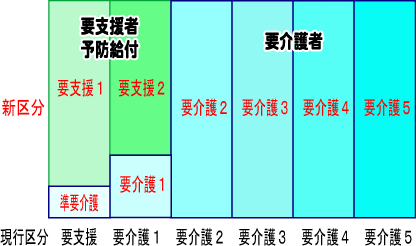
軽度の要介護者は増加が著しく、給付費膨張の一因となっています。更に、家事代行など従来のサービスが、かえって介護状態悪化を招くと指摘されており、介護状態の改善を目指すことを重視しての制度改革となりました。
特別養護老人ホームなどの施設での利用者負担について、給付を抑制し自己負担を増やすことになりました。具体的には、食費と、部屋代や光熱水道費などの居住費(ホテルコスト)を全額自己負担とすることになります。
また、市町村ごとに地域の事情に合わせたサービス提供を可能にする仕組みである「地域密着型サービス」を導入します。市町村が事業者の指定権限を持ち、必要に応じてサービス量を決定できるようにします。原則的に介護保険での利用者は、その地域住民に限定されます。認知症(痴呆性)高齢者グループホーム、定員30人未満の介護付き有料老人ホーム、夜間対応型訪問介護などが対象となります。
さらに、サービスの質の向上を目指し、事業所の指定や、ケアマネジャーの資格に更新制を導入することなども盛り込まれました。
一方、低所得者対策も盛り込まれました。保険料段階に「新第2段階」(年金収入が概ね基礎年金以下など)については、現行の高額介護サービス費の月額上限を引下げる(月額上限2万5000円→1万5000円)など負担軽減を行います。
<参考リンク>介護保険制度改革の全体像(PDF:54KB)
<参考リンク>厚生労働省のHPより「介護保険制度改革の全体像」

【2005/2/5更新】厚労省が国会に提出する改革案の概要を入手しました。それによると、全体像で示された8段階の介護区分中、準要支援に当たる区分は廃止され、7段階に整理されました。つまり、要支援では従来の介護サービスは全く受けられなくなるということです。詳しくは、「介護保険制度改革法案の来週国会提出へ」をご覧下さい。



