準用介護は設けず、7段階の介護区分
介護保険制度改革関連法案の閣議決定、国会提出が迫ってきました。私たち地方議員にとって介護保険の改革は非情に身近で、関心の高い問題です。地方の声がどのように法案に反映してくるか期待と不安が高まっています。
そのような中、今回の改革のポイントともいえる保険給付と要介護状態区分の考え方が、12月に公表された「介護保険制度改革案の全体像」より、一層ドラスティックに変わっていることが分かりました。
それは、12月の全体像では介護状態区分を現行の6段階(要支援・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5)から、現状の要支援・要介護1を2分割して8段階(要支援1・要支援2・準要介護・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5)に細分化することが示されました。そして、要支援1と要支援2に新予防給付を導入するとしていました。
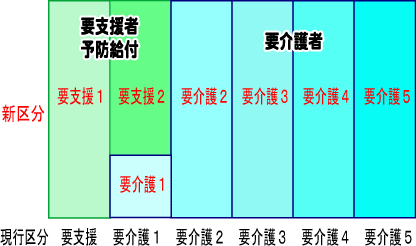
しかし、今回、国会に提案される内容では、準要介護という区分が無くなり全体で7区分とされるイメージが掲載されています。すなわち、要支援に該当する者は、従来の介護サービスの提供が受けられず、全てが新予防給付の対象となります。
また、家事代行サービスは、生活機能を低下させるものとして、原則的に行わないと明記し、例外的に行う場合でも、必要性について厳格に見直した上で期間や提供方法を検討すると但し書きを付けています。
一定の移行措置が実施されると思われますが、介護度が低い人に対する見直しは、新予防給付の具体像が見えない中、急激すぎるような気がします。
ただし、介護区分の設定は介護保険法本体ではなく、厚労省の省令で定められます。今後の国会での審議過程での見直しを大いに期待するところです。
 参考:<介護保険改革案>厚生労働省が全体像を公表
参考:<介護保険改革案>厚生労働省が全体像を公表




始めまして。
83歳の母は足腰が弱ってほとんどベットにいます。
親の介護はとても重要です。
井手さん、がんばってください。