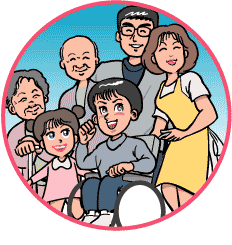 5月11日、障害者自立支援法案の審議が衆院厚生労働委員会で始まりました。身体、知的、精神3障害へのサービスの一元化や利用料の1割自己負担などを盛り込んだ自立支援法に対して、利用者の負担増に対する懸念が相次いで出されました。
5月11日、障害者自立支援法案の審議が衆院厚生労働委員会で始まりました。身体、知的、精神3障害へのサービスの一元化や利用料の1割自己負担などを盛り込んだ自立支援法に対して、利用者の負担増に対する懸念が相次いで出されました。
厚生労働省のホームページにも、自立支援法の詳しい内容がアップロードされました。
 参考:障害者自立支援法について(厚生労働省のHPより)
参考:障害者自立支援法について(厚生労働省のHPより)
精神障害者も支給の対象
自立支援法には、障害者自身が選択し契約する「支援費制度」の理念を受け継ぎ、現行では対象とならない精神障害者も含めて、全ての障害者が公平にサービスを受けられるよう、福祉サービスを一元化します。これにより、障害種別によるサービスではなく、介護、自立支援、医療などの各機能別にサービス類型を再編し、障害者の適性や必要性に応じてサービスを選択・申請し、市町村の審査を経て「自立支援給付」を決定されることになります。
意欲ある人が働ける環境に
福祉サービスの再編に加え、障害者の就労に重点を置いた支援策も見直します。具体的には、一般就労を目指して職場実習などの訓練を行う「就労移行支援事業」を創設するなど、福祉の側から支援を強化します。また、既存の施設を柔軟に運営できるよう規制緩和するほか、空き店舗や民家などの地域資源を有効活用できるよう設置基準を緩和。小規模の自治体でも設置しやすく改正し、より身近なサービス拠点の整備を促すことにしました。
将来にわたる制度を安定化
福祉サービスの向上に伴い、今後も利用者の増大が見込まれることから、法案に国と都道府県の負担義務が明記されました。法律に基づく義務的経費に転換されるので必要な財源が確保され、障害者福祉にとっては画期的な意義を持ちます。支援費制度が財政的に破綻した反省から、サービスの利用量が予算を超過すれば、補正予算を組んで補うことになります。
その一方で、利用者負担を所得に応じて決定する現行の「応能負担」から、原則としてサービス料の1割を負担する「応益負担」に転換されます。介護保険と同じように、増大する費用を相互に支え合う仕組みに転換されます。その際、障害年金などの所得に応じて負担の上限を設け、過大な負担になる人には、配慮やキメ細かな経過措置を設けることにしています。
この自立支援法について、個人的に4つの課題があると思います。国会での議論の中で、しっかりとよりベターな結論を導き出してもらいたいと思います。
1.利用者負担は世帯単位でなく本人の所得を基本にした上限額の設定
2.精神障害者の通院医療費における低所得者への十分な配慮(通院医療費公費負担制度<32条>問題)
3.最重度の障害者への介護サービス水準の確保
4.高齢者の介護保険との一元化も視野に入れた長期的障害者福祉像の議論




はじめましてです。
精神保健福祉に従事している
がちゃぴん。と申します。
『自立支援法』で検索して辿り着きました。
あつかましくも、『自立支援法』に関する記事を
トラバさせていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。