4月1日以降、新たな受給者は発生せず
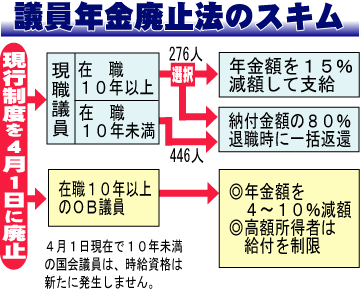 自民、公明の与党両党が提出した国会議員互助年金(議員年金)の廃止法が2月3日の参院本会議で自民、公明両党の賛成多数により可決、成立しました。
自民、公明の与党両党が提出した国会議員互助年金(議員年金)の廃止法が2月3日の参院本会議で自民、公明両党の賛成多数により可決、成立しました。
この法律の成立により、現行制度は、4月1日に完全廃止され、以後、新たな年金受給権は発生しません。
現行制度の廃止に伴う清算措置として、衆参両院議員全体(722人)の約3分の2に当たる受給資格を持たない在職10年未満の議員(446人)は、退職時に納付金(掛け金)総額の80%を一括して受け取ることになります。受給資格を持つ在職10年以上の議員(276人)は、(1)現行水準から15%減額した年金を受給(2)納付金総額の80%の一括返還――のいずれかを選択します。
議員OBについては、退職時期に応じて4~10%減額した年金を支給します。ただし、高額所得者には給付に制限を設けました。この清算措置によって、議員年金に充てられる国庫負担額(現行制度で年間約21億円)は、最終的にゼロとなる計算です。
民主党など一部では、この年金廃止案はまやかしであるとの指摘もあります。しかし、廃止時点ですでに年金の受給資格を持つ議員に対して、無条件でその権利を奪うことは、憲法でうたう財産権を侵害する懸念もあり、個人の選択の幅を持たせる必要があります。
議員年金の在り方をめぐり、公明党は、2004年2月に党内に「議員年金・秘書問題検討ワーキングチーム」を設置。現行制度の廃止と抜本改革を一貫して訴えてきました。また、青年局も、署名運動で集めた約272万人分の署名を添え、04年6月、衆参両院議長に廃止を求める要望書を提出するなど、議員年金廃止のリード役を担いました。
最終的に国庫負担ゼロへ、「現職」は3分の2が即廃止
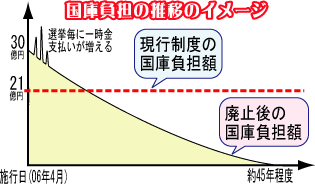 議員年金は、国庫負担が約7割に上るのは不公平だなどとの国民批判の高まりを受けて、2004年2月から国会で本格的な見直し論議が始まりました。公明党は一貫して庶民の目線から「現行制度の廃止・抜本改革」を訴え続け、今回、議員年金廃止法を実現させることができました。制度廃止により、国会議員の加入する年金は、今後、自営業者の皆さんが入っている国民年金のみとなります。
議員年金は、国庫負担が約7割に上るのは不公平だなどとの国民批判の高まりを受けて、2004年2月から国会で本格的な見直し論議が始まりました。公明党は一貫して庶民の目線から「現行制度の廃止・抜本改革」を訴え続け、今回、議員年金廃止法を実現させることができました。制度廃止により、国会議員の加入する年金は、今後、自営業者の皆さんが入っている国民年金のみとなります。
今回成立した法案は、現行制度が完全廃止され、批判が強かった年間約21億円に上る国庫負担を最終的にゼロになるようにしました。ただ、廃止に伴う清算措置は必要で、年金の受給権が発生する「在職10年」かどうかで現職議員の清算方法が異なります。
受給権のない在職10年未満の議員(446人)は、納付金(掛け金)の80%を退職時にまとめて返還します。これにより、現職議員の約3分の2は議員年金が即廃止となります。残り3分の1の在職10年以上の議員(276人)は権利が発生しているため、同じく80%の一括返還か、15%減額した年金受給かの選択制となります。
また、受給資格をもつ議員OB(525人)についても、退職時期によって4~10%減額して年金支給を続けるほか、高額所得者に新たな減額措置も講じています。
在職10年以上の現職議員が、例えば69歳から年金受給を開始し、平均余命の間、受給されると仮定すれば、廃止法施行後4、5年は600人弱まで増えますが、その後減少に転じ、20年後には200人を割り込み、45年後には1人もいなくなると試算されています。つまり、国庫負担金が文字通りゼロになります。
「制度存続」批判は感情論、国会議員といえど年金受給権は侵害できず
受給者が残ることで「事実上の存続案」との批判もありますが、これは感情論に走り過ぎていると言わざるを得ません。制度廃止の議論は、法律に基づいて年金受給権を認められた現職議員と議員OBがいることを踏まえることが大前提です。「議員年金はすべてけしからん」と感情論に任せて、年金受給権を取り上げたらどうなるか。既に認められた権利を喪失させることになり、憲法第29条で保障されている財産権を侵害する恐れがあります。
そうなれば、「憲法違反だ」との訴訟騒ぎになり、国が敗訴する可能性も十分にあります。ですから、この年金受給権に切り込むことは、法治国家としては難しいと言わざるを得ません。
その財産権の問題を避けて廃止法を批判するのは“ためにする批判”であり、無責任です。国民に間違った認識を与えかねません。廃止法成立により新たな受給権が発生することは一切なく、その意味でも「存続」ではなく「廃止」なだと思います。
民主党は、与党案に比べて現職議員すべての年金受給を放棄した案だと胸を張っていましたが、廃止法の成立が迫ってくると党内から不協和音が一気に噴き出し、「筋論も大事だが、生活も大事」などとの本音も漏れ始めています。返還金受け取りか年金受給かの選択についても、「民主党の議員年金受給者が相次いだ場合、民主党は『理想を振りかざしただけ』などの批判の矢面に立たされかねず」(2月3日付毎日新聞)と指摘されています。
前原誠司民主党代表は「私は年金受給を選択しない」と宣言したものの、党独自に受給自粛の申し合わせすらできていません。こうした党内のバラバラぶりを見ても、民主の対案は国民受けを狙ったパフォーマンスに過ぎないと言えます。
議員OBの年金も民主党案は「3割カット」としていますが、これでは財産権侵害の恐れがあります。にもかかわらず、民主党案が「廃止案」で、与党案は「温存案」であるかのような論調も見受けられます。民主党案でも現行の7割相当の年金が支給されるわけですから、与党案を存続案と言うなら、民主党案も存続案と言うことになります。



