6月1日、厚生労働省の人口動態統計(概算)が公表され、合計特殊出生率(一人の女性が生涯に産む子供数の推定値)、2005年は1.25となり、前年の1.29を下回り過去最低を更新しました。
合計特殊出生率は、昭和40年代、第2次ベビーブーム期を含め、ほぼ2.1台で推移していましたが、50年に2.00を下回ってから低下傾向となり、平成17年には1.25となりました。
年齢階級別に内訳をみると、上昇傾向にある35~39歳はほぼ横ばいですが、前年上昇に転じた30~34歳が再び低下したほか、低下幅の大きい25~29歳を含め、29歳以下で前年より低下しました。出生順位別にみると、前年上昇に転じた第2子が再び低下し、どの出生順位も低下しています。
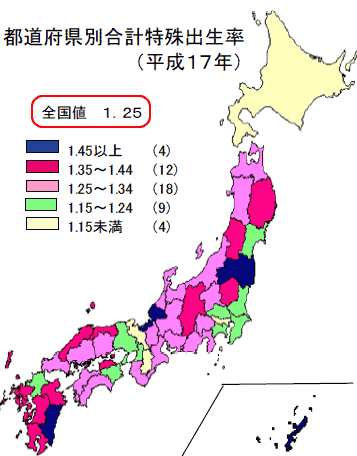 都道府県別にみると、合計特殊出生率が高いのは沖縄県(1.71)、福井県(1.47)、宮崎県(1.46)、福島県(1.46)等で、低いのは東京都(0.98)、奈良県(1.12)、京都府(1.13)、北海道(1.13)等大都市を含む地域でした。東京が初めて1.00を割ったことも注目されます。
都道府県別にみると、合計特殊出生率が高いのは沖縄県(1.71)、福井県(1.47)、宮崎県(1.46)、福島県(1.46)等で、低いのは東京都(0.98)、奈良県(1.12)、京都府(1.13)、北海道(1.13)等大都市を含む地域でした。東京が初めて1.00を割ったことも注目されます。
一方、出生数と死亡数の差である自然増加数が初めてマイナスとなり、日本が人口減少社会に突入したことが統計の上から裏付けられました。06年の自然増加数は、マイナス2万1408人で、前年の8万2119人より10万3527人減少し、自然増加率(人口1000対)は-0.2で、前年の+0.7を下回り、自然増加数とともに、統計の得られていない昭和19年から21年を除き、現在の形式で調査を開始した明治32年以降初めてマイナスとなりました。
出生数が死亡数を下回った県は前年は25道県でしたが、平成17年は36道府県となり、出生数が死亡数を上回った県は、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、滋賀県、大阪府、兵庫県、福岡県、沖縄県の11都府県となりました。
茨城の合計特殊出生率1.24、全国平均を下回る
茨城県の合計特殊出生率は、5年連続過去最低の1.24となり、統計を取り始めた1950年以降初めて全国平均を下回わりました。全都道府県中では、第35位と前年の29位より多きく順位を下げました。出生数は2万4244で戦後最少となりました。
死亡数は、25,840人で前年より1,496人増加しました。反面、乳児(1000人当たり2.8人)や新生児(1.4人)の死亡率は低下しました。
婚姻件数と離婚件数は共に減少しました。婚姻件数は、15,534件で前年を390組下回りました。離婚件数は、5,833件で前年より172組少なくなりました。
 参考:平成17年人口動態統計月報年計(概数)の概況
参考:平成17年人口動態統計月報年計(概数)の概況



