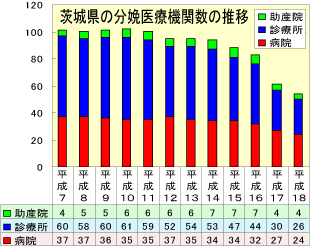 1月21日、日立市内の日立シビックセンターで、茨城県医師会主催の県民フォーラム「お産をする場所がない!」が開催されました。現在、医師不足は社会的に大きな問題となっています。特に産科医、小児科医の不足は深刻な状況にあります。茨城県の県北地区では、出産を受け付けている産科の医療機関は3つしかなく、まさに「お産をする場所がない」のが現状です。
1月21日、日立市内の日立シビックセンターで、茨城県医師会主催の県民フォーラム「お産をする場所がない!」が開催されました。現在、医師不足は社会的に大きな問題となっています。特に産科医、小児科医の不足は深刻な状況にあります。茨城県の県北地区では、出産を受け付けている産科の医療機関は3つしかなく、まさに「お産をする場所がない」のが現状です。
こうした現状を受け、今回「産科医療」をテーマにた県民フォーラムが開催されました。基調講演は、文仁親王妃紀子様のご出産で有名な愛育病院院長の中林正雄先生が行い、産科医を取り巻く厳しい現状が具体的な資料をもとに説明されました。特に、産科医の減少と産科医療施設の減少は顕著であり、すべての医師の中での産科医の割合は、1984年に8.0%あったものが2002年には4.2%と半減しました。産科医療機関は、84年の9613箇所から02年には6452箇所とほぼ3分の2に減少しました。その減少の理由について、中林医師は以下のような8項目を指摘しました。
産科医および分娩施設数減少の理由
基幹病院
- 過酷で不規則な勤務
- 女性医師の割合増加による実労働時間の減少
- 医療訴訟の多発
- 低収入
診療所
- 医師の高齢化
- 医療訴訟の多発
- 授産師・看護師の雇用難
- 低分娩料による経営難
中林医師はこうした現状分析の上で、基幹病院と2次医療機関、1次医療機関との機能を明確にしること、産科医の労働条件の改善、産科医療に対する公的補助の増額などを提案しました。
特に、産科オープンシステムの導入と助産師の育成を進めることが、産科医療を守るために必要だと強調しました。
産科オープンシステムとは
分娩の安全性を向上させるために、病院の設備とスタッフを地域の診療所の医師に開放(オープン)して、共同して病院を利用するシステム。これまでに、病院と診療所の連携(病診連携)を一層進展させたシステムで、妊娠検診などは身近な地域の診療所で行い、分娩は高度な周産期医療機関で行う。この場合、出産も地域の診療所の医師が立ち会い、退院まで病院の医師と共同で管理する。
また、その前段階としてセミオープンシステムも提案されています。これは、妊娠36週頃までの妊娠検診は診療所で受け、それ以降はオープン病院で受ける。出産はオープン病院で行い、病院の医師が立ち会うシステムです。
また、その前段階としてセミオープンシステムも提案されています。これは、妊娠36週頃までの妊娠検診は診療所で受け、それ以降はオープン病院で受ける。出産はオープン病院で行い、病院の医師が立ち会うシステムです。
助産師不足の現状と対策
日本産婦人科医会の平成18年の緊急調査結果によると、分娩取り扱い施設(病院が1247施設、診療所が1658施設)の内、助産師の充足率は、病院が84.7%、診療所が63.5%、全体で71.1%となっています。実数では、病院での不足数が1515人、診療所で4203人、全体で6718人と分析されています。
こうした慢性的な助産師不足を解消するために、日本産婦人科医会では産科診療所で働く正看護師のために、1年間の夜間助産師育成カリキュラムを提唱しています。
こうした動きを受けて、水戸市医師会は夜間助産師学校の開校準備を進めています。教育期間1年で20人を受け入れる予定です。看護師が助産師になるには、6か月以上の専門教育を受け、国家試験に合格する必要があります。
こうした慢性的な助産師不足を解消するために、日本産婦人科医会では産科診療所で働く正看護師のために、1年間の夜間助産師育成カリキュラムを提唱しています。
こうした動きを受けて、水戸市医師会は夜間助産師学校の開校準備を進めています。教育期間1年で20人を受け入れる予定です。看護師が助産師になるには、6か月以上の専門教育を受け、国家試験に合格する必要があります。
日立で県医師会フォーラム 安心な出産環境模索
茨城新聞(2007/01/22)
200人が意見交換
「お産をする場所がない!」をテーマに、安心して出産できる環境づくりを目指し、県医師会県民フォーラム(茨城新聞社共催)が二十一日、日立市幸町の日立シビックセンターで開かれた。産科医や助産師などが産科医療を維持するため意見発表。参加した二百人は危機的な状況にある出産を取り巻く環境の打開策を考えた。
県民フォーラムは秋篠宮家の長男、悠仁さまご誕生のときの主治医、中林正雄愛育病院長が、産科医の減少や高齢化が進んでいる現状などを報告。県医師会の石渡勇常任理事も、県や県北の周産期救急医療の問題点を提起した。
こうした問題点を踏まえ、産科医らが意見発表。日立市の産科医、瀬尾文洋さんは安全で快適な出産、育児情報交換の場の提供などの取り組みを挙げながら「子は日本の宝。宝を少なくしてはいけない。出生数と経済力は関係があり、経済の回復を願う」と語った。
日本助産師会県支部長の川崎ます子さんは、助産師の少なさを嘆きながらも、「三十、四十代が頑張っている。今後、茨城も良くなるので、気軽に声を掛けてほしい」と要望した。
日立製作所日立総合病院の産婦人科主任医長の山田学さんは、十年間の出産数や救急患者、母体搬送の増加を紹介した後、「日立総合病院の常勤医師は減り、近隣の中核病院も医師不足で縮小。産婦人科医不足は当分続く」と予想した。
県保健福祉部次長の泉陽子さんは、周産期医療対策や医師確保対策を述べ、「産科医の増加、病院への定着がないと体制維持は困難と、危機感を持っている」と語った。




大変失礼いたしました。
情報の確認が中途半端であったようです。
早速訂正いたしました。
下記は誤りです。現在のところ設立を検討している段階で開校は決まっていません。
>全国初の夜間助産師学校が06年4月に水戸市内に設立されました。