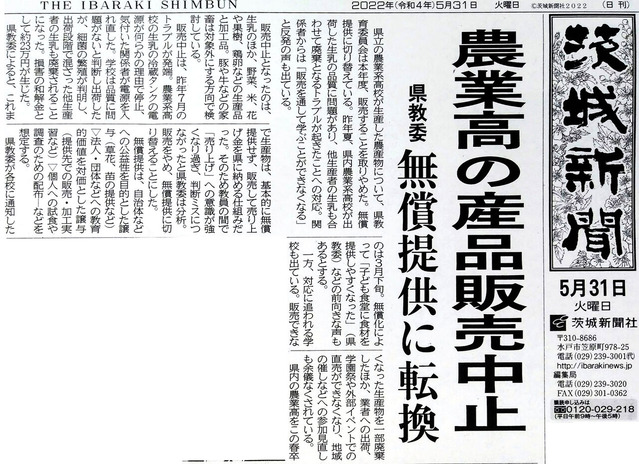バイマスエネルギーのサイクル構築を目指す先進的取り組み
 8月29日、井手よしひろ県議はたかさき進県議と共に行方市を訪れ、沖洲地区のひまわり栽培の状況を視察しました。
8月29日、井手よしひろ県議はたかさき進県議と共に行方市を訪れ、沖洲地区のひまわり栽培の状況を視察しました。
行方市沖洲の国道355号に面する、三昧塚古墳の反対側の約4ヘクタールの畑では、麦の裏作としてひまわり24万本を栽培しています。
行方市では、つくば市の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構中央農業総合研究センターと連携し、バイオマス資源循環研究の一環として2004年から、油生産に適したヒマワリ「ハルリンゾウ」の栽培を始めました。
この地域では麦を5月下旬に収穫し、6月中旬にひまわりの種を蒔きます。ひまわりは8月中旬に満開となり、この光景は観光的にも集客力があります。9月下旬に収穫し、その後、乾燥させ油を搾ります。11月下旬には、麦が蒔かれます。ひまわりは、地力を回復する効果があり、麦との連作に向いています。
行方市の取り組みの特徴は、ひまわりを栽培->種から食用のひまわり油を製造->ひまわり油を販売し使用した廃油を回収->バイオ・ディーゼル燃料(BDF)として再生->農器具用の燃料として使用というサイクルを地域内に作ろうとしていることです。
ヒマワリは9月下旬ごろ収穫され、約6000キロの種から、約1200リットルの油が得られる見込みです。研究センターから搾油機械一式を初めて借り、収穫したすべての種を使いひまわり油を試作します。11月には、食用油の瓶詰サンプル商品が完成する予定です。
このプロジェクトを中心となって進めてきた行方市役所の高塚博玉造総合窓口課長は、「まだどうしても製品の単価が高くなるのが現実です。その値段でも買っていただけるような価値のある製品が出来るかがポイントだと思います」「栽培用の機械や搾油機などの購入は、ある程度のスケールメリットが必要であり、県などが中心となって提供してほしい」「環境問題、資源の問題を考えるとバイオマスの活用はこれから益々必要になり、茨城県がそのトップランナーとなるためにも、こうした事業を積極的にリードしてほしい」などと語りました。
9月議会では、農林水産常任委員会などで、ひまわりや菜の花によるバイオマス活用について、県の姿勢を質す予定です。