乳がん検診進まず 補助額が普及左右
朝日新聞(2008/7/3)
県内の市町村で、乳がんの検診が進んでいない。乳がんの早期発見に有効なマンモグラフィー検診は、40歳以上を対象とした女性の受診率(05年度)が約10%と全国43位だった。自治体の補助額や、実施期間に大きな開きがあるため、各市町村の受診率は数%~76%超と大きな差がある。(清水大輔)
厚生労働省によると、市町村別の受診率は05年度、常陸大宮市が76・6%、東海村が54・2%、結城市が27%だった。全国平均の17・6%を超えたのは44市町村のうち13自治体しかなく、龍ケ崎市や筑西市は2%そこそこで常陸太田市は1%に満たなかった。
がん検診はもともと国の補助事業で、国と県、市町村が3分の1ずつ費用負担していた。しかし、98年度に市町村の一般財源に任され、検診にかかる個人の負担額に開きが生じ始めた。県保健予防課によると07年度では、無料の東海村をはじめ、500円程度で受けられる常陸大宮市や城里町などがある一方で、水戸市やつくば市などでは2千円以上かかる場合がある。
同課は毎年、ピンクリボンやねんりんピックなどの催しごとに検診受診を呼びかけているが、市町村の「懐事情」が、検診の普及状況を左右する傾向が見られる。
乳がん検診対象者は自治体が指定した病院などで受ける以外は、公民館などでの集団検診が身近で一般的だ。県内の公民館などを巡回する「検診バス」は、県内3医療機関に数台しかない。
また、同課の調べでは、07年度の検診の実施時期は、常陸大宮市や行方市、取手市が月をまたいで複数設けているのに対し、龍ケ崎市や茨城町などは、ひと月のうちの数日~数週間に限定している。
厚労省や県は検診について、「40歳以上を対象に2年に1度の実施」を奨励している。しかし、利根町のように補助対象が50歳以上の自治体もある。町内には「乳がんは40~50代に多い病気。40代から受診できれば安心も増す」と話す主婦(57)もおり、町は「幅広く検診を受けてもらうために今後、40歳からのマンモ検診導入を検討したい」としている。
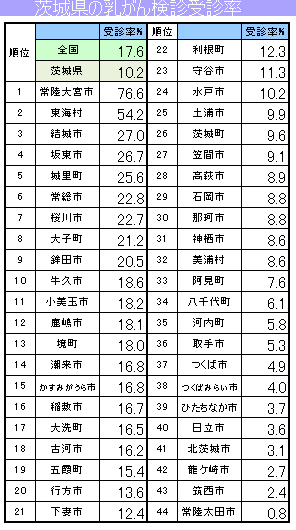 朝日新聞の記事をキッカケに、7月4日、井手よしひろ県議は県保健福祉部に資料の提出を求め、県内市町村の乳がん検診の実施状況と受診率の関係を聞き取り調査しました。
朝日新聞の記事をキッカケに、7月4日、井手よしひろ県議は県保健福祉部に資料の提出を求め、県内市町村の乳がん検診の実施状況と受診率の関係を聞き取り調査しました。検診の受診率が最も高い常陸大宮市は76.6%、反対に一番低い常陸太田市は0.8%と、隣り合った二つの市が対照的な結果となっています。常陸大宮市の場合、検診の対象に制限がないことが特徴です。したがって、女性全員が対象ということで、集団検診の受診啓蒙も行き届いているのかもしれません。常陸太田市も極端に条件が悪いわけではありません。この受診率の開きは、実際に現地調査を行う必要性があるかもしれません。
一般的には、自己負担が少ないほど受診率が高くなるはずですが、自己負担額だけでは受診率の高低を説明することは出来ません。その意味では、朝日新聞の「乳がん検診進まず 補助額が普及左右」との見出しは、ポイントがずれているかもしれません。確かに、乳がん検診は市町村が単独事業として実施している事業のため、財政力が豊かな東海村は、自己負担を撤廃しています。受診率も54.2%と県内で2番目に高くなっています。反面、大子町は自己負担額が1300円から2300円と割高でありながらも、受診率は2割を超えています。
限られて予算の中でも、受診する側の利便性を考えた市町村の取り組みに、受診率向上の秘訣があるようです。



