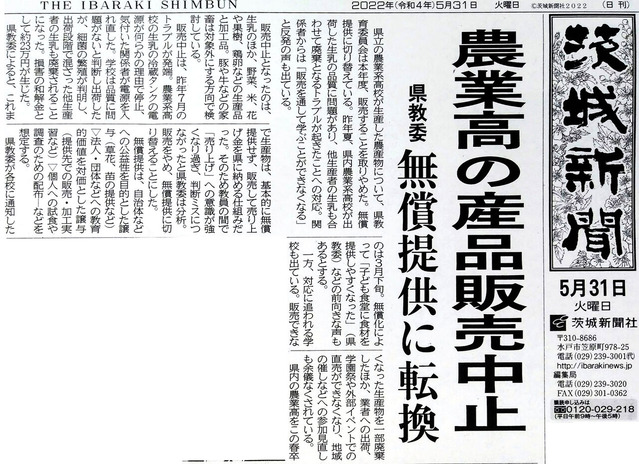4月24日、農林水産省と経済産業省は、光や温度を制御してレタスやイチゴといった野菜などを栽培する全国の植物工場の数を、2011年度末までに現在の3倍の150に拡大する目標を発表しました。建設費の補助や工場で使用する照明の技術研究などを通して民間企業を支援。消費者の国産志向の高まりを背景に企業参入を促し、普及を目指す計画です。
4月24日、農林水産省と経済産業省は、光や温度を制御してレタスやイチゴといった野菜などを栽培する全国の植物工場の数を、2011年度末までに現在の3倍の150に拡大する目標を発表しました。建設費の補助や工場で使用する照明の技術研究などを通して民間企業を支援。消費者の国産志向の高まりを背景に企業参入を促し、普及を目指す計画です。
植物工場のメリットは、作物を取り巻く環境を情報技術(IT)などで制御し、季節や天候に左右されずに安定供給できること。経産省によると、ことし4月現在の工場数は50に上ります。(以下のマップは、経済産業省の委託を受けて(株)三菱総合研究所が実施した「植物工場実態調査」に基づき、ホームページ等の公開情報をもとに作成したもの。農林水産省のHPより転載いたしました)
これまでも農業者団体が植物工場を建設する際、建設費の補助はありましたが、今回は民間企業が工場のリース方式などで参入する場合、建設費の半額を助成する制度なども設けています。農水省は助成費など総額96億円を2009年度補正予算案に計上しました。
(農林水産省:21年度補正予算【96億2500万円】)
①植物工場における野菜の生産コストを3割縮減
②植物工場の設置数を100箇所増
<内容>
1.民間企業等の競争展示・研修による植物工場関連技術の実証・普及等の取組を支援
大学等を対象として、植物工場のコスト縮減や生産性向上に向けて、民間企業等がコンペ方式での技術実証・展示や人材育成のための研修を行う拠点を整備します。
モデルハウス型植物工場実証・展示・研修事業:36億6500万円
2.農業者団体等による植物工場の導入を支援
主に農業者団体を対象として植物工場の導入支援を行うため、整備事業、地区推進事業により支援します。
植物工場普及拡大支援事業:33億7600万円
3.民間企業等による植物工場のリース導入を支援
主に民間企業を対象として植物工場の導入支援を行うため、リース事業、地区推進事業により支援します。
植物工場リース支援事業:25億9600万円
植物工場とは
植物工場は、施設内で植物の生育環境(光、温度、湿度、二酸化炭素濃度、養分、水分等)を制御して栽培を行う施設園芸のうち、環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御と生育予測を行うことにより、野菜等の植物の周年・計画生産が可能な栽培施設です。大別すると、閉鎖環境で太陽光を使わずに環境を制御して周年・計画生産を行う「完全人工光型」と、温室等の半閉鎖環境で太陽光の利用を基本として、雨天・曇天時の補光や夏季の高温抑制技術等により周年・計画生産を行う「太陽光利用型」の2種類があります。
植物工場の起源は、昭和32年(1957年)にスプラウトの一貫生産を行ったデンマークのクリステンセン農場だと言われています。北欧は日照時間が非常に短い季節があるため、補光型の植物生産が以前から行われ、それを基礎として、オランダ等の欧州各地で高度な施設園芸が発展してきた経緯があります。
現在国内に50の植物工場が稼働
経済産業省の委託事業として、三菱総合研究所が、国内の完全人工光型及び太陽光・人工光併用型植物工場の実態調査を行いました。それによれば、現在、野菜及び花き(苗を含む)を生産している施設は全国で50カ所(完全人工光型:34カ所、太陽光・人工光併用型:16カ所)となっています。
生産されている品目は、現状では生育期間が短く、植物体のほぼ全てを商品化できるサラダナ、リーフレタス等のレタス類やハーブ等の葉菜類が中心で、その他では花き、野菜・花卉の苗などとなています。
植物工場を運営する事業者の代表的な事例として、完全人工光型ではマヨネーズ製造のキューピー、太陽光・人工光併用型ではJFEライフ株式会社があります。キューピー社は、閉鎖環境において、完全人工光で農薬を使用せずにサラダナ、リーフレタス、ハーブ等の養液栽培を行い、自社の野菜販売網を活用して量販店向けに年間を通じて定価で販売しています。
茨城県内にも工場を持つJFEライフ社は、ガラス温室において太陽光と人工光を併用してリーフレタス等の養液栽培を行い、サラダ、惣菜等の加工業者や高級量販店等と提携して年間を通じて販売しています。
植物工場の特徴(利点と可能性)
| 生産技術 | ・施設内の快適な環境で、比較的軽労働が中心 |
| ・環境制御で生育や品質を調節 | |
| ・生産者の勘と経験だけでなく、環境と生育のモニタリングと生育予測に基づき、計画的・安定的に生産 | |
| ・栄養成分、機能性成分の強化 | |
| ・農薬や肥料、水分の使用量を低減 | |
| 販売 | ・加工・業務用として歩留まりが高く、食品残渣等を縮減 |
| ・虫や異物の混入が少なく、洗浄や調製作業を省けるため、コストの縮減が可能 | |
| ・台風等の気象災害時にも定価で安定供給が可能 | |
| 立地・建築 | ・立地場所を選ばず、非農地、栽培不適地での農業生産が可能 |
| ・空き店舗、空きオフィス、空き工場、空き倉庫などへの設置も可能(完全人工光型) | |
| ・多段化による高度な空間利用(完全人工光型) |
植物工場への注目の高まり
近年、植物工場に対し、大きな関心が集まっています。その理由は、第一に中国等の外国産食材の安全性に対する不安の高まりを背景として、安全・安心な国産食材を求める消費者意識が高まっていることが挙げられます。実際、農薬を使用しない等、栽培方法に特徴のある農産物については、2~3割までであれば割高でも購入したいという調査結果もあります。このような消費者意識の高まりを受け、小売店のみならず、近年、需要が拡大している加工食品や外食を製造・提供する事業者においても、生産履歴が正確に明示できる食材に対するニーズが高まっています。
また、近年、高品質の食材を消費者に提供するため、流通・小売段階でのコールドチェーン化が進展していますが、生産段階については、露地栽培が多いこともあり、この対応が遅れており、サプライチェーン全体で評価した場合、効率性を損なう要因となっています。植物工場の活用に伴い、生産段階からのコールドチェーンへの対応も容易になると期待されています。
植物工場は、閉鎖的な環境において、生産履歴を正確に把握・記録し、農薬を全く使用せずに生産することも可能です。また、適切な温度管理の下での生産・出荷が可能であり、特に完全人工光型植物工場で生産された野菜は、虫や異物の混入が少ないことを特徴となっています。そのため、「洗わずに食べられる」ことをセールスポイントにしている事例も見られます。これらの特徴が高く評価され、消費者の積極的な理解も急速に進んでいます。
2つ目には、食料供給の安定性を高めるという点も理由として挙げられます。野菜の需給バランスは、短期的な変動が大きいとされますが、台風や水不足等の天候不順によって、露地野菜の価格が高騰した場合でも、植物工場産農産物であれば定価での安定供給が可能です。また、中長期的な視点で考えた場合、我が国の農業は、担い手の高齢化や後継者不足、耕作放棄等が進む中で、国産食材のニーズの高まりに必ずしも対応しきれていません。野菜作農業については、専業農家が創意工夫を重ね、他品目と比較して高付加価値な農業経営を実現してきたと言えますが、近年は、農業生産額は減少傾向となり、結果として輸入食材の浸透が進む結果となっています。ニーズの高い国産食材を中長期的に安定供給していくための新たな体制整備が求められており、植物工場はその一翼を担うものと期待されています。
これらを踏まえ、国産食材の供給・調達の新たな選択肢として、植物工場への注目と期待が高まっています。

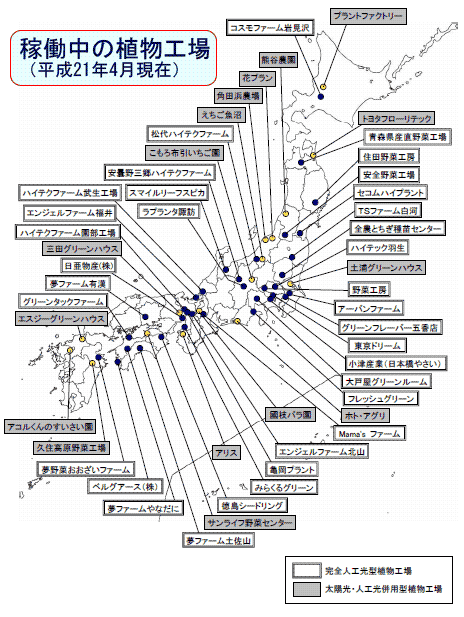
 参考:
参考: