新型インフルエンザ流行のピークは10月上旬
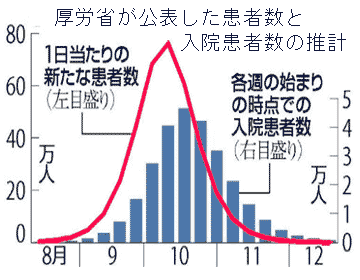 8月28日、新型インフルエンザの患者数がさらに増え、今後も患者数の急速な拡大が想定されることから、厚生労働省は、各自治体に医療体制の整備を要請しました。
8月28日、新型インフルエンザの患者数がさらに増え、今後も患者数の急速な拡大が想定されることから、厚生労働省は、各自治体に医療体制の整備を要請しました。
厚労省が医療体制整備の参考にするために作成した仮定の流行のシナリオによると、流行のピークは10月になり、1日当たり約76万人の患者が新たに出て、全国の入院患者は最大時で4万6400人に上る可能性があるとしました。
試算は海外の流行状況や感染率などから、季節性インフルエンザ感染者の約2倍にあたる国民の平均2割、都市部などでは3割が発症すると想定しています。今シーズンの入院率を全患者の1.5~2.5%(38万人~64万人)、インフルエンザ脳症や肺炎など重症者の発生率を0.15~0.5%(3万8000人~12万8000人)として算出しました。
患者数のピークは流行開始8週間後になるとし、国内での流行開始(8月10~16日)に当てはめると、10月上旬ごろに来ることになります。入院患者のピークは患者数のピークから約1週間遅れ、全国の入院患者は4万6400人に達する。国民の3割が感染すると、入院患者は6万9800人に上ります。死者数の試算はありませんが、米国の想定では入院患者の約30人に1人が死亡しており、2300人余りの死亡者が出る可能性があります。
都道府県には、診療所での夜間診療延長なども準備するよう指導しています。ぜんそくや糖尿病など持病がある人は医療機関で感染する恐れがあるため、医療機関に対して電話による診療、持病の薬を長期間使えるよう一度に処方することも求めています。
1学級2名の新型インフルエンザ感染で学級閉鎖
 茨城県では、8月21日、県危機管理連絡会議が開催され、2学期が始まる9月以降、1学級に2人以上の新型インフルエンザ患者が発生した場合、学級閉鎖とすることが報告されました。季節性のインフルエンザでは、2割以上の患者が発生した場合、学級閉鎖としていたが、基準を大幅に厳しくして蔓延を防ぐ方策とします。
茨城県では、8月21日、県危機管理連絡会議が開催され、2学期が始まる9月以降、1学級に2人以上の新型インフルエンザ患者が発生した場合、学級閉鎖とすることが報告されました。季節性のインフルエンザでは、2割以上の患者が発生した場合、学級閉鎖としていたが、基準を大幅に厳しくして蔓延を防ぐ方策とします。
国の指針が変わり、患者全員に遺伝子検査を実施しなくなった7月24日以降、夏休みに入ったにもかかわらず、中学校や高校、大学、児童クラブなど県内80カ所で新型インフルエンザが集団発生していたことが報告されています。最も集団発生が多かったのは高校で23カ所、次いで中学校が16カ所、大学が11カ所などとなっています。夏休み中、部活動などで感染したとみられています。
8月31日からの新学期を前に、県は、各学校に対し、①手洗いやうがいに努める、②発熱などの症状がある児童や生徒には、無理して登校せず医療機関を受診するよう指導する、③欠席者の把握を正確に行い、医療機関でインフルエンザと診断された場合は速やかに学校に連絡するよう生徒に周知徹底する、④1学級で2人以上の患者が発生した場合、速やかに保健所に連絡する―などを指導徹底しています。
茨城県は86万7千人分のタミフル、リレンザを備蓄
一方、県は8月26日、新型インフルエンザの治療薬タミフル10万1100人分を追加備蓄したことを発表しました。国の「対策行動計画」改定に伴い、中外製薬(東京)から買い増ししたもので、今回購入分と、7月に購入したリレンザ約1万200人分、2006年、07年の両年度に備蓄したタミフル24万6千人分を合わせ、約35万7300人分の治療薬が備蓄されことになります。
今回の追加備蓄により、国と流通備蓄分の治療薬のうち本県で利用可能と想定される51万人分と合わせると、県民の29%に相当する86万7千人分が確保されたことになります。
28日に公表された新型インフルエンザの流行に関する厚生労働省の試算は、想定される一つのケースに過ぎません。外岡立人・元小樽市保健所長(読売新聞2009/8/29付け)によると、「今回の試算は、通常の季節性インフルエンザの2倍程度の感染者が出るという前提で計算されている。しかし、大流行している豪州では通常の5倍以上の感染者が発生しており、根拠がない」と指摘されています。
通常のインフルエンザの5倍の発症者がでると、86万人の治療薬では、なお不足することになります。
2学期の授業が始まり、小中高校生などに集団発生が広がると、患者数のピークは試算より早い時期に来る恐れもあります。
まずは、手洗いや咳エチケットの励行など一人ひとりが感染予防に気をつけることが重要です。



