政治資金規正法の改正で、政治家の責任問う
 井手よしひろ県議は、1月27日、JR大甕駅前でおこなった県議会報告で、国会議員の政治とカネの問題について、4つの具体的な提案を行いました。以下、その要旨をご紹介します。
井手よしひろ県議は、1月27日、JR大甕駅前でおこなった県議会報告で、国会議員の政治とカネの問題について、4つの具体的な提案を行いました。以下、その要旨をご紹介します。
国会では平成21年度2次補正予算が衆議院を通過し、議論が参議院に移りました。一方、鳩山由紀夫総理大臣、小沢一郎民主党幹事長の政治と金にまつわる問題は、不信が深まる一方で、抜本的な再発防止策の議論までには至っていません。
それにしても、民主党をはじめとする与党三党の「政治とカネ」の問題に対する姿勢は、厳しく批判されるべきです。予算案が大事だから疑惑追及は後回しでいい、と言わんばかりの姿勢は改めるべきです。公明党は、予算も疑惑も徹底して議論すべきと主張しています。これは両方をきちんとやってほしいとの国民の声であり、国会は今こそ与野党が党派を超えて自浄作用を発揮しなければなりません。
さらに、民主党内から疑惑解明の声が上がらず、検察やマスコミに対する言動を見ると、むしろ疑惑を封じ込めるような力が働いている。民主党として、積極的に自浄能力を発揮していただきたいと思います。
鳩山首相、小沢幹事長の犯罪立証は司法に委ねるべきですが、道義的、政治的な責任を問う場が国会です。まずは、公明党はじめ野党が求める「政治とカネ」の問題に関する集中審議の開催に、与党が応じることが必要です。このため、第2次補正予算案の衆院委での採決に先立ち、民主、自民、公明の3党国対委員長で協議し、衆院予算委で「政治とカネ」の問題を含めた集中審議を2月半ばをめどに実施することを確約させました。また、党首討論も2月中に必ず行うことでも合意しました。疑惑解明へ、この機会も十分に使っていくことが大事です。
そのうえで、再発防止に向けての具体的な取り組みが必要です。
そのポイントとして、4点指摘したいと思います。
監督責任の過失があれば政治家の公民権停止
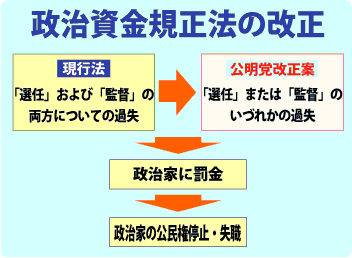 一点目は、政治資金規正法の改正です。現行の政治資金規正法は、会計責任者が収支報告書の虚偽記載などの不正を犯した場合、政治家本人は「選任」と「監督」の両方に責任がないと罰せられません。つまり、会計責任者を選んだ時に将来、不正行為を働くかどうかの予見にまで過失がないと罪に問えないのです。こんなことは、実際にはあり得ませんから、事実上“ザル法”といっても過言ではありません。
一点目は、政治資金規正法の改正です。現行の政治資金規正法は、会計責任者が収支報告書の虚偽記載などの不正を犯した場合、政治家本人は「選任」と「監督」の両方に責任がないと罰せられません。つまり、会計責任者を選んだ時に将来、不正行為を働くかどうかの予見にまで過失がないと罪に問えないのです。こんなことは、実際にはあり得ませんから、事実上“ザル法”といっても過言ではありません。
そこで、公明党は、虚偽記載などの不正を抑止するために政治資金規正法の改正案を国会に提出しました。政治家の監督責任に過失があれば、公民権を停止させるよう制裁を強化し、より実効性を高めることをめざしています。
衆院予算委では、井上幹事長が今国会での成立を訴えたのに対し、鳩山首相は「前向きに検討すべきだ」と述べています。各党に協力を呼び掛け、ぜひとも成立を期したいと思います。
政治資金収支報告書に政治家の署名・捺印
二点目は、あまり注目されていませんが、政治資金規正法に基づく政治資金の収支報告書の宣誓欄に、政治家本人の署名捺印を義務付けることが必要だと主張します。
1月25日の衆議院予算員会では、自民党の町村信孝元官房長官が鳩山首相に対して、「一度も(政治資金収支)報告書を見たことがないのか」と質問しました。これに対し、鳩山首相は「秘書を全面的に信頼していたので、安心して任せてしまっていたのが実態だ」などと答弁しました。
また、東京地検の参考人聴取後の記者会見で、小沢一郎民主党幹事長が配布した書面には、「◇収支報告書の記載について:私は、本件不動産に関する収支報告書の記載については全く把握していませんでした。また、収支報告書の記載内容について、相談されたり、報告を受けたこともありません。◇収支報告書の内容の確認について:常々、担当秘書には、政治団体の収支についてはきちんと管理し、報告するように言っていましたが、実際に私自身が帳簿や収支報告書を見たことはありません。担当秘書を信頼し、実務については一切任せておりました。担当秘書から、各政治団体ごとの収入支出と残高などの概要について報告を受けることはありましたが、収支報告書の内容を一つ一つ確認したことはありません」との記載があります。
現行の政治資金収支報告書は、一番の責任者である政治家本人が確認せずとも、提出が認められています。政治家の署名捺印は、資金管理団体を解散するときのみ義務付けられているの過ぎません。政治家が自らの資金管理団体の収支報告書に責任をとらないというような、国民からみると理解できない現状は変えなくてはなりません。
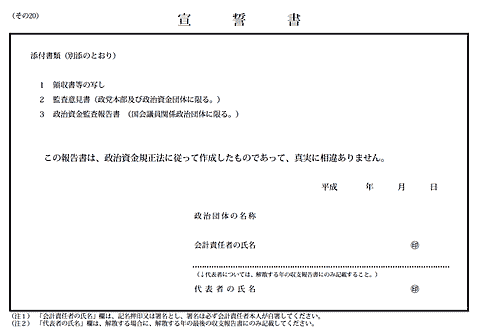
企業・団体からの政治献金を禁止
3つ目のポイントは、「企業・団体献金の禁止」です。公明党がマニフェストに掲げた企業・団体献金の禁止については、与野党の協議機関設置を呼び掛けています。「企業・団体献金の禁止」については、民主党もマニフェストに掲げており、すぐにでも実現出来る環境は整っているはずです。実現に向けて、積極的に検討を進めていくべきだと考えます。
政党助成金法の見直し
4点目が、政党助成金法の改正です。1月20日、公明党と自民党は、政党助成金法の改正案を衆議院に共同提案しました。
この改正は、政党が解散決定後に政党交付金の残額を他の政治団体などに寄付する“返納逃れ”を禁止することが目的です。さらに、既に解散した政党の交付金の残額を国庫に返納することができるようにするため、国会議員やその候補者が国に寄付することを禁じた公職選挙法の適用除外規定も盛り込みました。
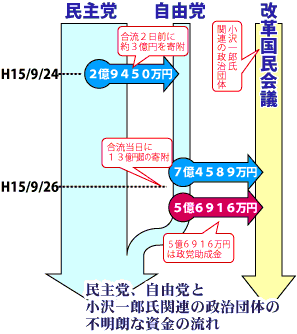 小沢一郎民主党幹事長をめぐる一連の政治資金疑惑の中には、ゼネコンからの資金提供の問題と政党助成金を含む、政党から政治団体への不可解な金の流れがあります。特に、自由党と民主党の合併時の不明瞭な資金の流れには疑念が晴れません。2003年に民主党と自由党が合併し、自由党が解党されるその日に、自由党は小沢代表の政治団体「改革国民会議」に対し、5億6000万円の政党助成金を含む約13億円を寄付しています。
小沢一郎民主党幹事長をめぐる一連の政治資金疑惑の中には、ゼネコンからの資金提供の問題と政党助成金を含む、政党から政治団体への不可解な金の流れがあります。特に、自由党と民主党の合併時の不明瞭な資金の流れには疑念が晴れません。2003年に民主党と自由党が合併し、自由党が解党されるその日に、自由党は小沢代表の政治団体「改革国民会議」に対し、5億6000万円の政党助成金を含む約13億円を寄付しています。
国民の税金から交付される政党助成金は、政党が解散するときには余った分を国に返却するのが国民の常識です。しかし、その常識を覆して、自由党の政党助成金の残金は、小沢幹事長の関連団体に流れました。さらに、それを国庫に返却しようとすると、公職選挙法によって禁止されている寄付ということになってしまうのです。こうした不合理を無くすことが、改正の目的です。
この改正案は、昨年(2009年)4月に公明党などが衆院に提出。7月に公明、自民、社民の賛成多数で衆院を通過しましたが、衆院解散に伴い廃案となっていました。今回、民主党が改正のどのような立場を取るか、一端賛成した社民党が連立の中でどのような対応をするかが注目されます。
以上、4つの視点で早急に予野党が、胸襟を開いた議論を開始することを求めるものです。
鳩山首相と小沢幹事長をめぐる「政治とカネ」の問題。両氏はそれぞれ釈明会見を開きましたが、疑惑は深まる一方です。
元秘書が虚偽記載で起訴された鳩山首相は、実母からの総額約12億6000万円、一日換算で50万円に上る資金提供の使い道をいまだに説明できていません。首相は、22日の衆院予算委員会で「資料が検察から返ってきた時に、事務所費など示せるところは示したい」と答弁しており、可能な限り早期に公表すべきです。
一方、秘書らが政治資金規正法違反(虚偽記載)で逮捕された小沢幹事長は、土地代金に充てた4億円の原資について説明は、二転三転しています。
2007年の記者会見で小沢氏は「政治献金」と説明。ところが、昨年秋から疑惑報道が再び噴出すると「金融機関からの借り入れ」となり、その後、16日の党大会では「個人の資金」と変わった。さらに23日の記者会見では、家族名義の口座から引き出した現金が含まれていたことを明らかにしました。
両氏に共通しているのは“秘書に任せていた”とのひと言で済まそうとしている姿勢です。国民の大半が説明に納得していない現状を踏まえれば、両氏は明確な説明責任を尽くすべきです。



