政府は4月30日の閣議で郵政見直し関連法案を決定し、国会に提出しました。法律成立後には政令改正も行い、日本郵政の公的な性格を強める方針です。従来の民営化路線を覆すほか、中小企業への融資が滞るなど、多くの問題点が指摘されています。
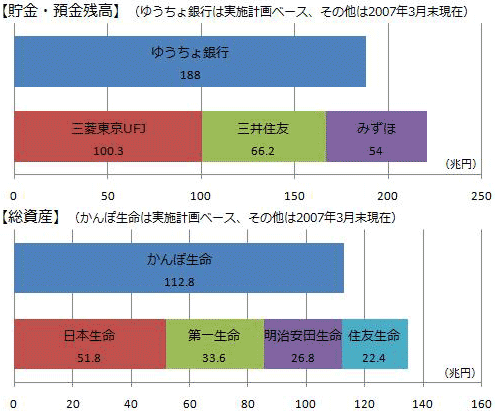
「民営化」路線を覆す、2005年衆院選の民意を無視して良いのか?
郵政見直しの問題は何より、政府が掲げる「官から民へ」の理念を覆し、従来の民営化路線を大きく転換したことです。2005年の衆院選で民営化を支持した民意の無視は許されません。
郵政民営化は、国が郵便貯金や簡易保険で集めた巨額な資金を民間に移し、経済を活性化させることが目的です。
しかし、法案では日本郵政グループ5社を3社に再編し、ゆうちょ銀行やかんぽ生命保険に対する政府の関与を残す結果となりました。
その上、政府は法律成立後に、政令を改正し、郵便貯金と簡易生命保険の利用限度額をそれぞれ2000万円(現行1000万円)、2500万円(現行1300万円)に引き上げる方針です。
これは「官製金融」の肥大化にほかならず、「民業圧迫」との批判は免れません。
米国とEU代表部の駐日大使は、民間金融機関との公平、公正性の観点から、WTO(世界貿易機関)の協定に違反する可能性を警告した書簡を、平野博文官房長官らに送付しています。
中小企業融資が停滞、郵貯へ民間預金の流出進む
第2の問題点は、中小企業への融資が滞る恐れがあることです。
郵貯の預入限度額が引き上げとなれば、地方銀行や信用金庫、信用組合など地域金融機関の預金が郵貯へ流れていく可能性が高くなります。郵貯には、どんな事態でも政府が貯金を保護する「政府保証」があると信じられているためです。その結果、地域金融機関の貸し出し余力は減り、中小企業への融資が滞りかねない。郵貯の資金を中小企業に貸し出すことは出来ず、結果的に”中小企業いじめ”の政策になってしまいます。
また法案では、金融2社の新規事業について、これまでの「許可制」から「届け出制」に変更し、事業拡大を容易にしました。
国の借金が増加する恐れ、膨らむ郵政資金が国債の受け皿に
第3の問題点は、郵貯や簡保に集まった資金の運用手法です。現在は国債での運用が中心ですが、今後膨らむ資金も国債運用となれば、国債の”受け皿”となりかねません。政府の安易な国債発行を許し、借金が973兆円(2010年度末見通し)にも上る厳しい国家財政をさらに悪化させる懸念が生じます。
運用手法に関しては、政府内から病院や学校などの公共施設の整備や、海外の社会資本整備への投融資、国家ファンドの創設による海外投資などに活用する案が出ています。
これは、かつて予算のムダ遣いを生んだ「財政投融資」(財投)の復活に他なりません。財投とは、政府が郵貯や簡保の資金を使って特殊法人などに投融資をしていた事業。国会などのチェックが十分に及ばず「第二の予算」としてムダな事業や天下りの温床となっていました。
政府が進める郵政見直しは、民間主導で郵政資金の透明化、効率化を進める目的に反するものです。



