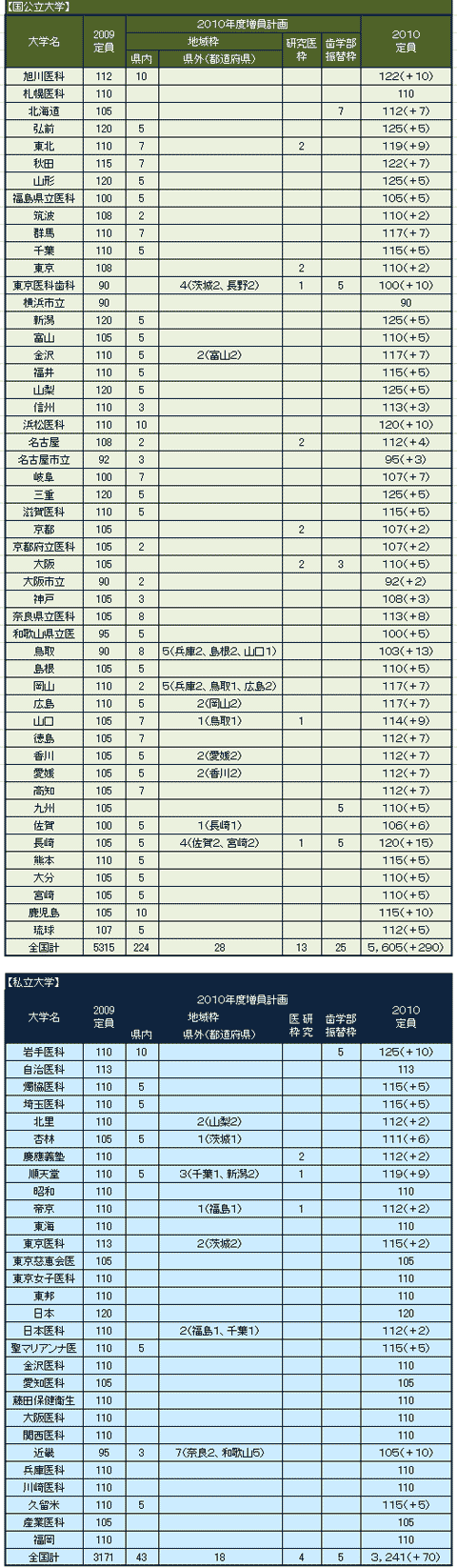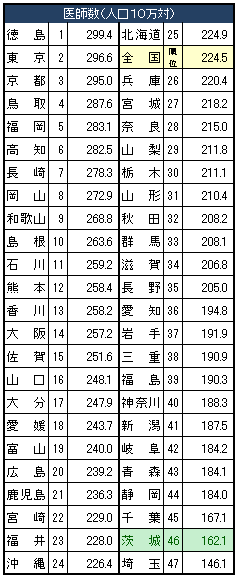 茨城県の医師総数は、「平成20年末の医師・歯科医師・薬剤師調査」によると、4805人であり、人口10万人当たりでは162.1人です。
茨城県の医師総数は、「平成20年末の医師・歯科医師・薬剤師調査」によると、4805人であり、人口10万人当たりでは162.1人です。
全国平均は224.5人であり、全国第46位と下から2番目の慢性的な医師不足の状況にあります。
この医師不足の大きな原因として考えられるのは、医学部の不足が考えられます。人口300万県民に対して、茨城県内での医師の養成を行っているのは、筑波大学しかありません。
全国的にみても、人口10万人当たりの医師数が全国下位にある千葉県や埼玉県においても、県内に医科大学が1校しかなく、医師の確保を進める上では、医科大学の誘致が喫緊の課題であると考えられます。
一方で、国は医科大学の新設を未だに認めておらず、医師不足の解消に抜本的な手が打たれていません。
このような現状の中で、各地の大学で医学部新設へ向けた動きが出始めています。
文部科学省は80年以降、医学部新設を認めていません。しかし、民主党は医師不足対策として医学部の新設、医師定数の5割増しも掲げており、いつになったら具体的な方針変換が行われるのか、批判の声も上がっています。
ただ、民主党の支持母体の一つである日本医師会は医学部新設に反対しており、今後の議論の行方は不透明なままです。
現在、医学部新設を検討しているのは、北海道医療大(北海道当別町)、国際医療福祉大(栃木県大田原市)、聖隷クリストファー大(浜松市)の私立3大学といわれています。いずれも学内に検討委員会を設け、定員やカリキュラムなどを協議しています。また、公立はこだて未来大(北海道函館市)も、函館市が識者らでつくる懇話会を設置し、新設の可能性を検討しています。
北海道医療大は入学定員60~80人を想定。大半を歯科医や薬剤師、看護師などが対象の編入枠とし、医師不足が深刻な道東地域への即戦力の供給を指向します。
国際医療福祉大は、現在の医学部設置基準の上限である定員125人程度を想定しています。
聖隷クリストファー大は、4年制大学卒業者を対象とした「メディカルスクール」の創設も視野に入れてといわれています。
医学部の設置は1979年の琉球大が最後で、それ以降、医師が過剰になるとの将来予測などから新設を認めてこなかった経緯があります。
民主党は昨夏の衆院選に向け公表した政策集で、医師養成数の1.5倍増を掲げ、「看護学科等を持ち、かつ、病院を有する大学の医学部設置等を行う」とマニフェストにうたっています。
成20年(2008)医師・歯科医師・薬剤師調査の概況

全国の医学部と定員