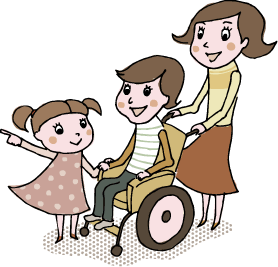 昨年の臨時国会では改正障害者自立支援法が成立しました。
昨年の臨時国会では改正障害者自立支援法が成立しました。
障害者自立支援法は、障がい者が地域で自立した生活ができるよう支援する法律です。障がい別(身体・知的・精神)でバラバラだった旧来の福祉サービスを一元化し、障がいの程度に応じて利用者本位のサービスを提供する仕組みを構築するのが目的。2006年に施行されました。
しかし、介助や介護のサービス量に応じて原則1割の自己負担を課す「応益負担」を導入したため、収入の少ない障がい者がサービス利用を控えざるを得なくなるなど、多くの課題もあったことも事実です。
そこで公明党は、施行後も即座に減免措置を重ね、生活保護受給世帯は負担ゼロ、市町村民税非課税の低所得世帯には月1500~3000円の負担上限を設ける(今年度から無料としています)など、現場の声に真摯に対応してきました。
今回の改正法のポイントの第1は、利用者負担について、所得に応じた「応能負担」を原則としました。利用者負担の上限額は、公明党が推進した度重なる対策で既に大幅に引き下げられており、実質的に「応能負担」になっていますが、これを法律上でも明確化し、現行の負担水準を維持しました。利用者負担の実質的な負担率は、国保連の取りまとめによると0.37%(2010/7)となっています。また、今まで別々に利用者負担の上限額が設定されていた「障害福祉サービス」と「補装具」も、それぞれの費用を合算し、負担を軽減できるようになります。
第2に、自閉症などの「発達障害」を支援対象に含めることを明記。「高次脳機能障害」も大臣告示や通知で明確にされます。
ほかに、*総合的な相談支援体制の強化、*障がい児らが利用する「放課後デイサービス」の創設、*障がい者向けグループホーム・ケアホームの居住費の助成――など、地域での自立生活支援の充実を盛り込んでいます。
これまで障害者自立支援法改正案は、自公政権時代には衆院が解散し廃案、前通常国会でも鳩山首相辞任騒動で審議未了の廃案となりました。
公明党が原案を作り、09年3月に提出した改正案から今回成立した改正法まで、一貫して成立を推進してきました。公明党は「地域で自立して暮らせる社会に」との法の趣旨を実現するため、野党になっても各党を説得し“接着剤”の役目を果たしてきました。特に“ねじれ国会”の状況下で成立に導くことができたのは、山口那津男代表をはじめ公明党が「断固、臨時国会で成立させる」との揺るぎない姿勢で民主・自民両党を説得したからであり、その取り組みには、障がい者団体から評価の声をいただいています。
政府・民主党は、現行の自立支援法にかわる新法施行(2013年8月の予定)までの“つなぎ”と位置付けていますが、これは大きな認識の間違いだと考えます。新法で対応するのだから法改正は必要ないとの主張は「3年後に新築の家ができるから“雨漏り”の修理は必要ない」というようなものです。「改善できる点は、すぐ見直すべき」というのが、現場の生の声を聞いてきた公明党の考えです。“つなぎ”であれ何であれ、障がい者の自立した生活を実現する、現実的な対応が最優先だと考えます。
現在の負担軽減措置が恒久化され、応能負担が原則となります。
○福祉サービスの対象に発達障害等が明確化されます
福祉サービスの対象として明確でなかった発達障害等が明文化されます。
○高次脳機能障害が福祉サービスの対象に
大臣告示や通知で福祉サービスの対象として明確化されます。
○グループホーム・ケアホームへの家賃等に対する助成制度が創設されます
グループホーム・ケアホームは、地域での欠かすことができない暮らしの場となっています。現在、その家賃等が重い負担となっていますが、この負担を軽減する助成制度が創設されます。
○障害児の発達支援・家族支援が強化されます
障害種別にかかわらず身近な障害児施設を利用できるとともに、障害児施設の発達支援の専門スタッフが保育所等を訪問し、支援する仕組みもできます。また、放課後等デイサービス事業が制度化されます。
○相談支援体制などが強化されます
障害福祉サービスをより受けやすくするための相談支援事業の充実と地域自立支援協議会の基盤整備が図られます。



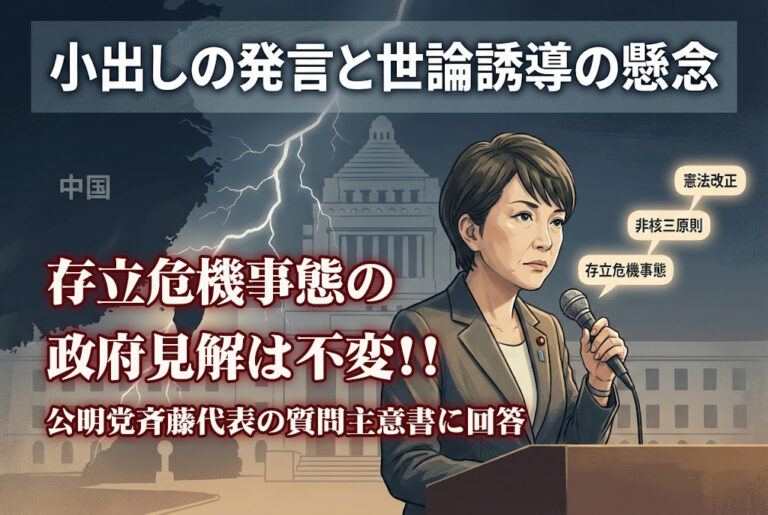
障害福祉サービスをより受けやすくするための相談支援事業の充実と地域自立支援協議会の基盤整備が図られます。