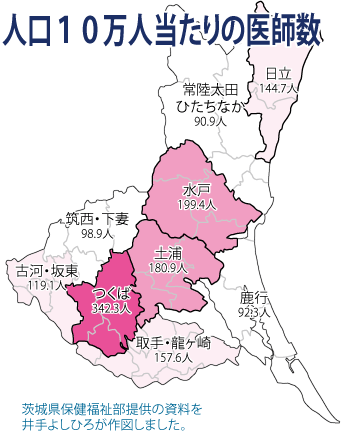 元旦から朝日新聞の茨城版に「生老病死」という特集が掲載されています。--高齢人口の急増、長引く不況と地域・経済格差の拡大、借金まみれの財政、弱まる家族や地域社会の絆……。社会の様々な変化によって、これまでの「命と健康のセーフティーネット」がほころび、医療や福祉の網からこぼれ落ちる人たちが出ている。私たちはこの社会で、どう生を全うできるのだろう。茨城の「生老病死」を見つめる--とのリードが冠されたこの特集記事。茨城の医療の現状を冷静に捉えた、良質の企画となっています。
元旦から朝日新聞の茨城版に「生老病死」という特集が掲載されています。--高齢人口の急増、長引く不況と地域・経済格差の拡大、借金まみれの財政、弱まる家族や地域社会の絆……。社会の様々な変化によって、これまでの「命と健康のセーフティーネット」がほころび、医療や福祉の網からこぼれ落ちる人たちが出ている。私たちはこの社会で、どう生を全うできるのだろう。茨城の「生老病死」を見つめる--とのリードが冠されたこの特集記事。茨城の医療の現状を冷静に捉えた、良質の企画となっています。
 参考:特集「生老病死」第1部(朝日新聞:茨城版)
参考:特集「生老病死」第1部(朝日新聞:茨城版)
特に、元旦号のいわばその企画記事のイントロダクションともいえる「医療に格差・南高北低」との特集は、東大医科学研究所の上昌広特任教授と県立健康プラザの大田仁史管理者との投稿は、茨城県の医療の現状を鋭く指摘し、県が目指す方向性を具体的に示してくれています。このブログでは、その記事を引用紹介します。
人材育成考えるとき
日本の人口千人あたりの医師数は2.1人です(経済協力開発機構調べ)。米英が2.5人、独、仏などが3.5人ぐらい。メキシコが1.8人、トルコが1.5人です。日本国内は西高東低で西日本は米英並み。茨城県内の分布図をみると、「つくば医療圏」以外はすべて全国平均以下。メキシコ、トルコに負ける地域が大半です。
何人に対して医学部が一つかを比較すると、九州、中国、四国、北陸は100万から130万人程度。茨城は296万人に一つ。茨城、千葉(619万人)、埼玉(359万人)の3県は悲惨です。
医学部偏在の原因は、1県1医大政策で小さな県が多い西日本に手厚くなったことや、戊辰戦争で官軍につかなかった地域が、教育機関をつくる上で冷遇されたことなどがあります。
偏在解消は短期的ではいかんともしがたい状況ですが、この地域には財政力のある自治体が存在します。茨城でいえば、原発のある東海村、鹿島港とコンビナートの神栖市などです。ただ、医学部をつくるノウハウはありません。
今、中東やアジアの新興国に、米国の名門大学が進出しています。お金はあるけれどノウハウはない新興国は、海外のブランドを呼ぶ。自前でつくらなくてもいい。明治政府の日本も、お抱え外国人を大量に呼んで大学をつくっていったのです。
ブランドを呼んだ成功例が千葉県浦安市。ディズニーランド誘致で日本屈指の富裕な市になりました。「浦安園」ではなかったのが大きい。千葉県では今、空港で財政力のある成田市がブランドの医大誘致に動いています。
高度人材養成機関を誘致すれば、全国、世界から人が集まります。各国エリートの留学生がきて、グローバルな人脈が広がるとビジネスもしやすくなります。
茨城はポテンシャルがある地域なのに使い切れておらず、もったいない。将来への最大の投資は、駅前再開発ではなく人材の養成です。県民が本当に考えなくてはいけないときだと思います。
東大医科学研究所持任教授上昌広さん
かみ・まさひろ
兵庫県出身。
国立がんセンター中央病院から現職。専門は医療ガバナンス諭。
「現場からの医療改革推進協議会」事務局長。42歳。
高齢化「自助」が肝心
茨城の有訴者率(症状を訴える人の率)と治療を受けた受診率が低いのは、行くところ(病院や診寮所)が少ないからでしょう。高齢者の統計では、茨城は短命で、障害を持つ人(治療を受けて、障害を負っても生き残った人)が少ないグループに入ります。医療が整っていないということです。
一方、高齢化率は高い。2035年、県全体の65歳以上の割合の推計は(関東各都県で最高の)35.2%。今の大子町と同じぐらいになります。
超高齢社会の問題は「波」ではなく、団塊世代の「津波」でやってきます。第1波は2015年ごろの年金問題。きちんと支給されるかどうか分かりません。第2波は25年ごろで医療・介護を受ける人がどっと増えます。第3波は35年ごろの「多死」時代です。一度に多くの方が死に直面することに、社会は対応できるでしょうか。
今のままでは「制度」という堤防を整えるだけでは乗り切れない。
たとえ医者の数を増やしても、面積が広く人がばらばらに住む地方では、なかなか開業しない。状況はすぐに良くはなりません。
発想を変え、津波を低くすることが必要です。それには、できる限り自分で自分の身を守らなくてはいけません。体操をしたり栄養に配慮した食事にしたり。医者が増えるまで待つのではなく、自助、互助で、津波を少しでも崩し、時期をずらすことです。
国は介護を在宅中心にやろうとしているけれど無理です。効率的に、施設重点主義を考えなくてはならない。まとまって暮らしていなければ、お世話をしきれません。私は施設に廃校の校舎を借用することを提案しています。
学校は元々、給食をつくる炊事場がある、廊下の幅が広い、避難場所の体育館があるなど設備が整っている。あとはエレベーターをつけるぐらいです。新たに土地を購入して建設するより、ずっと安くできるはずです。
今、市町村がそれに賛成しないのは介護の費用で財政がパンクするから。だから国も県もみんな協力しないといけません。結局は税金ですから、国民の幸せのために、効率よく使うことが大切です。
県立健康プラザ管理者大田仁史さん
おおた・ひとし
香川県出身。リハビリ医療の第一人者で、田中角栄元首板の主治医も務めた。県立医療大付属病院長などを歴任し、2005年から現職。74歳。



