 4月29日、公明党政調会長の石井啓一衆議院議員(党県本部代表)は衆院予算委員会で、東日本大震災による地盤の液状化について、政府の「災害被害の認定基準が実態に対応していない」と指摘しました。住居の床が少しでも傾斜すれば居住が困難になりますが、現行の認定基準では「床の傾きが念頭に入っていない」として、全面的見直しを求めました。
4月29日、公明党政調会長の石井啓一衆議院議員(党県本部代表)は衆院予算委員会で、東日本大震災による地盤の液状化について、政府の「災害被害の認定基準が実態に対応していない」と指摘しました。住居の床が少しでも傾斜すれば居住が困難になりますが、現行の認定基準では「床の傾きが念頭に入っていない」として、全面的見直しを求めました。
これを受けて、5月2日、内閣府は「り災証明書」発行の際の判定方法を示した「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」を見直 し、都道府県を通じて全市区町村に通知しました。
新基準のポイントは、1.傾きによる判定の追加、2.基礎の潜り込みによる判定の追加――の2点です。
従来の指針では、20分の1(重りを付けた長さ120センチのひもに対して、柱が鉛直方向から6センチ以上傾いた状況)以上の傾きが「全壊」。60分の1以上20分の1未満の場合(6センチ未満2センチ以上)は、一律に柱 と基礎で計15%損壊していると計算したうえで、屋根や設備など他の損害割合を加えて20%以上40%未満なら半壊、40%以上50%未満は大規模半壊、 50%以上は全壊と判定していました。しかし、液状化被害では柱と基礎以外に損害が見られないことが多く、また、傾きも2センチ以下のがほとんどで、大半が半壊にも認定されませんでした。
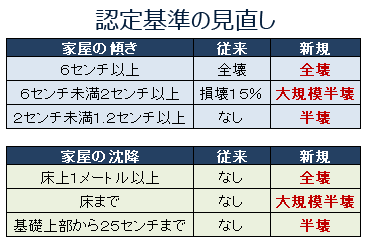 今後は、全壊の扱いは従来通りですが、6センチ未満2センチ以上の傾きを大規模半壊、12センチ未満1.2センチ以上を半壊と判定します。
今後は、全壊の扱いは従来通りですが、6センチ未満2センチ以上の傾きを大規模半壊、12センチ未満1.2センチ以上を半壊と判定します。
また、住宅の基礎などが地面に潜り込んでしまうようなケースについては、潜り込み量が床上1メートル以上は全壊、床までを大規模半壊、基礎の上部から25センチまでを半壊と判定することになりました。
この基準の見直しで、内閣府は液状化被害による被災者生活再建支援法の対象が、現在の数百軒から数千軒に増える見込みととしています。
しかし、これによって液状化被災者の住宅再建が大きく進むとも考えられません。それは、「被災者生活再建支援法」では、たとえ全壊判定が出ても、住宅を新築しなくては上限の300万円が支給されないからです。基礎の修理やジャッキアップなどによる補修の場合は、200万円しか支給されません。千葉県などは、県が上乗せして支援を行うことを検討しているようですが、国が災害復興基金などの一刻も早い造成を図る必要があります。



