東日本大震災では、首都圏の各地で液状化の被害が発生しました。液状化被害は首都圏の臨海部だけでなく、内陸部の造成地でも発生し、住宅や道路、上下水道などに大きな被害が出ています。
内閣府によれば、千葉県や茨城県だけで住宅約1万8000棟、約42万平方キロで、被害が確認されています。
しかし、液状化は被害の把握が難しく、まだ全体的な数字が把握できていないのが実情です。「被災者生活再建支援法」に基づいて行われる住宅の被害認定は、建物が壊れている度合いが基準なので、住宅の倒壊を伴わない液状化被害は、これまで「一部損壊」としか扱われてきませんでした。
これに対し、公明党などの強い要望が功を奏し、内閣府は5月2日に20センチの高音に対して水平方向に1センチの傾きがある場合(傾き5%以上)を「全壊」、60センチの高さに1センチの傾き(傾き1.67%以上)で「大規模半壊」、100センチの高さに1センチの傾き(1%以上)で「半壊」との新基準を設けました。また、住宅の沈下(潜り込み)に対しても、新たな基準が設けられました。
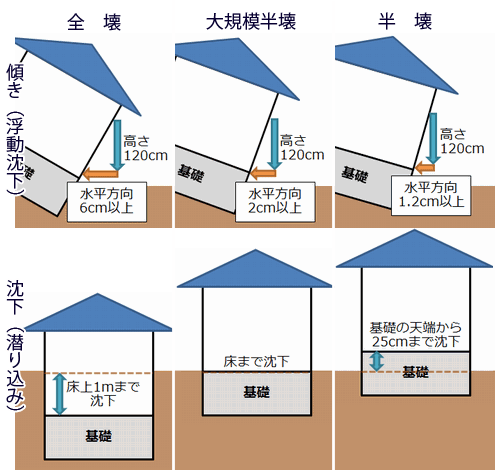
現在、この新基準をもとに自治体で調査が行われていますが、対応が遅いと言うしかありません。政府には、被災者の立場に立って、実態調査を急ぎ、正確な情報をもとにして早く対応する責任があります。
新基準が設けられましたが、被災者生活再建支援法では「半壊」の場合、支援金支給の対象になりません。このために、心身ともに大きな被害を受けながら、支援の手が伸びていない被災者が多くいます。
液状化の場合、実際は「半壊」(100センチの高さに1センチの傾き:1%)でも、居住者にめまいや吐き気などの健康被害があるといわれます。これでは、建物が壊れていないと言っても、生活することは難しい。健康被害が出るという「100センチの高さに1センチの傾き」であっても被害に認定し、支援するべきとの声が、正に現場の声です。
液状化で傾いた住宅の修復には地盤対策だけでも300万円、傾斜修復を合わせれば少なくても500万円以上の費用が必要と言われています。現行法では対象範囲が狭く、十分な手当てができていません。法改正を含めた対策が必要です。
被災者を救済できる仕組みづくりや、液状化ハザードマップの作成、建築確認の際の液状化対策の義務化などの実現に取り組む必要があります。



